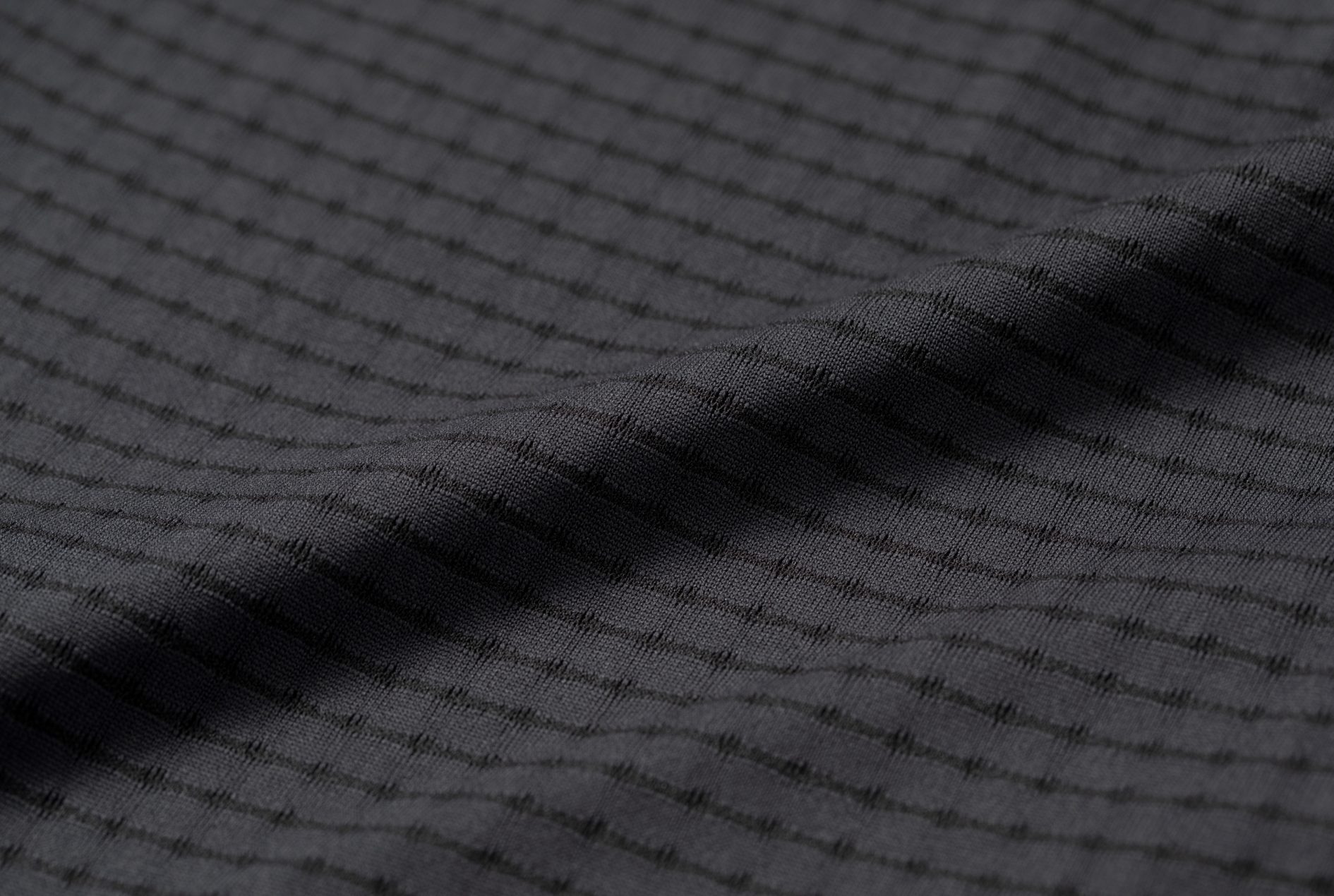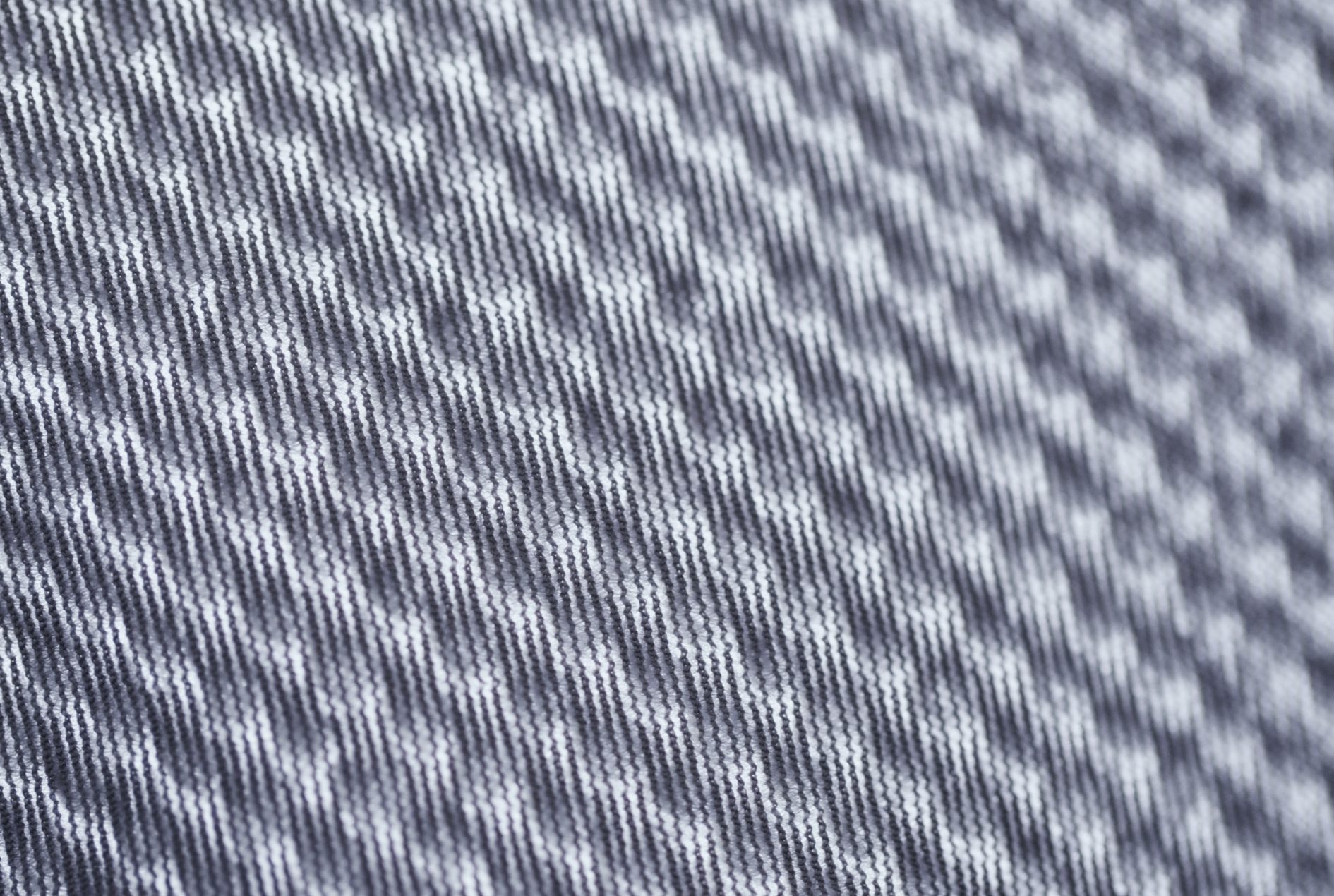ON THE EDGE
プロの国際山岳ガイドとして己を律する「教官」が問う、山の危機管理
日本ではまだ数が少ない国際山岳ガイドの資格を持ち、山岳救助では講師としてその経験を後進に伝える長岡健一。「国際ガイドになるために山を登っていた」という長岡がプロのガイドとして独立したのは47歳と遅咲きだ。しかし山のキャリアは50年以上に及ぶ。その間に、スキーSIAゴールド資格の取得、鮎釣りでは日本一に輝くなど、とことん探求を突き詰め自然への視野を広げてきた。最近ではパラグライダーのガイドとして空までその活動範囲に入ってきた67歳に、山岳ガイドとしての想いを訊いた。歯に衣着せぬ発言は、数々の現場を経験した者だからこそ口にできるものである。

猟のための沢登りが山の原点
長岡さんの山や自然との出会いについて教えてください。
群馬で生まれ育ったのですが、狩猟をしていた祖父や父に連れられて10代の頃から山に入っていました。もう50年も前ですね。狩猟で山に入るというのは、沢登りの典型をやるようなものです。雪から水をとったり、沢の水を飲んだり、魚を釣ったり、山菜を採ったりして獲物を追いかける。持っていくものは、生米と醤油と味噌と塩、それぐらいのものでしたから、山の生活術が自然に身についたんですね。
一方で沢は昔から事故が多いのです。実は住まいから100メートルぐらいのところに、群馬県の山岳警備隊の救助隊長をされていた馬場保男さんがいらっしゃって、一緒に沢の搬出方法を模索するなど救助活動を手伝うようになりました。そうこうしているうちに群馬県連の救助隊長を任されるようになり、20年近くやりましたね。
山岳ガイドとしての活動に加え、山岳救助でも後進の育成に努められているのはそういう経緯があったのですね。
今は立山にある国立登山研修所で山岳遭難救助研修会の主任を務めて8年になります。ここ数年は仕事の約1/3が消防学校とか警察学校での山岳救助関連、残り2/3がガイド関連の仕事です。救助のあとにガイドを始めたので、キャリアとしては遅咲きですね。

マッターホルンでたしなめられた20代
救助活動と山岳ガイドは共通する部分も多く、それでいて要求されるスキルは別物だと思います。救助活動は必然的に関わるようになったとして、ガイドを志すきっかけには何があったのですか?
これは自分の恥でもあるのですが……20代、大学生のときヨーロッパに行ったんですよ。1ドルが360円で、片道77万円くらいかかる時代。お金を工面して現地に着いて、ジーパンとなんてことのない靴でマッターホルンを登ったんです。身体能力が多少あったものですから登れてしまったのです。そうしたら向こうのガイドらしき人が、ドイツ語で顔を真っ赤にして俺を怒るんですよ。何言ってるか分からないから逃げるけれど、それでも追い掛けてきて、何か言ってくる。
よその国の人間の俺みたいなのに対して、すごい真剣に怒る。その時は嫌で嫌でしょうがなくて、なんだこの国はと思いました。でも、それが国際ガイドの方だったんです。こういう風に、家族のように真剣に怒ってくれるガイドがいることに衝撃を受けました。それから少し時間が経ちますが、ガイドになるからには絶対に国際ガイドを目指そうと。中途半端ではなく、仕事として国際ガイドをやるんだと決めていたんです。国際ガイドになるために、ヨーロッパに渡りグランドジョラス北壁、アイガー北壁、ドリューを登りました。楽しさのためではなく、ただガイドになりたい一心でしたね。
「だから駄目なんだ」と言える人間はいるのか
ガイドを目指す原体験はマッターホルンでドイツ語で諭されたことだと伺いましたが、長岡さんがガイドをする理由として、かつての自分のような無鉄砲な登山を減らしたい、という思いもあるのでしょうか。
正直、後付けにはなりますがそれはあります。よく山に精通した人やベテランが山で亡くなったときに、誰も何も言えない空気がありますよね。例えば若い人で無鉄砲に登る人間に対して批判はするけれども、名の知れた登山家にしっかりと対峙して向き合って、おまえこれだから駄目なんだよって言える人間はいるのかっていうと、いないんです。事故を起こした後にみんな批判をするだけなんですよ。「無謀なことをして」とか「こんなときに雪山に入るなんて」って。
それを自己責任だと言う人間は、その人が山の関係者ならその人こそ無責任だと俺は思うんです。自分が自分に課する自己責任と、第三者が人に言う自己責任って俺は違うと思う。もし山に精通して、山を愛する仲間だったら、やっぱり厳しいことでもしっかりと言える人間っていうのがいなくちゃいけないなと感じていて、自分はそういう風になりたいなと。
だから国際ガイドの検定委員も10年ぐらいやりましたけども、ずいぶん落としましたし、落とした人間はみんな俺を嫌ってますよ。でも全然気にしない(笑)。やっぱり国際ガイドは登れて滑れて、体力があるっていうのは当たり前で、そこから何を伝えるか、何を考え方として持っているかっていうのが、すごく大事だと思っていますので。その意味で、言いにくいことでもちゃんと伝えられる人間でいたい。
国際ガイドになるハードルの高さがうかがえます。具体的にはどんな技術や心構えが必要になるのでしょうか。
国際ガイドの試験では俺も落とされました。それが悔しくて、食ってかかるわけじゃないんですが、なんで落ちたんですかとその時検定員をされていた近藤邦彦さんに尋ねたんです。
「君は技術はあるけれど、全部個人技だ」って言われました。「それは国際的なスタンダードじゃない。そういうことをやっているといつか不具合が起きるから、スタンダードを覚えなさい」と。その時は、このおじさん何を言ってるんだろう? と理解できなかったですね。
ただ、よくよく考えていくと日本の登山は井の中の蛙で、簡単に考えてしまうところがある。日本では八の字を結ぶと末端処理しろって言うじゃないですか。ヨーロッパでは末端処理をしないのが主流です。これに関しては私が登山研修所の主任になってから、テストをしました。八の字をダブル・オーバー・ハンドでしっかり結んでいっても、300回ぐらいでほどけるんですよ。でも、しっかりした八の字を結べば1万回近く振ってもほどけない。なら、末端処理をしろというのはどういうエビデンスで言っているのか?
それはもう慣例というか、自己流ですよね。基本的にグローバルスタンダードはCE規格というヨーロッパ基準です。これを理解しろと近藤さんはおっしゃられていたのです。日本の技術そのものは確かに素晴らしく高いものがある。ただ浪花節のように根性論が先立つ側面がどうしてもある。日本は当時でたかだか40年、今でさえ50年ぐらいの歴史ですけども、ヨーロッパは2世紀半ですからね。

国際ガイドは、人格も問われる
長岡さんは「教官」といわれるほどに、後進の指導にも妥協がないことで知られていますが、やはり国際ガイドの基準を考えると、指導も厳しくなる。
なりますね。プロのガイドはお金をもらうわけですから。日本では手を挙げればプロになって、明日から仕事が始められてしまう。そしてそれを頼る人は多いので、仕事はある。けれどもそうやって入ってくる仕事に追われていると、技術的な感覚や、プロガイドとしてのコンプライアンスが失われていく。じじくさい言い方で申し訳ないですが。だから後進のガイドには徹底的にコンプライアンスを伝えます。
例えば、2日間続くガイドならウェアは必ず洗えと。汗臭いウェアでお客様と一緒に登るなと。それは結婚式にTシャツを着ていくくらい恥ずかしいことだぞ、と。どんなに忙しくても必ず洗えと。プロ意識を持って仕事をするんだと伝えました。
山の技術だけでなく、そうした身なりだとか、人格だとかも問われるということですね。
ヨーロッパではガイドの社会的地位が確立されていますから。人間としてちゃんとしている人しかなれないんです。講師としてどれだけ教えた経験があるかとか、3親等に犯罪を犯した人がいないことを証明する無懲罰証明書の提出が義務付けられていたり。その分、山小屋を安くしてくれたり、ロープウェーを優先的に乗れたりと仕事がしやすいように配慮してもらえる。一方で、自分がやったことはガイド全体のこととして見られる、という意識を国際ガイドは常にもって仕事をしていますね。言動や行動は常に見られている。
忘れられない2つのガイド
ガイドとして仕事をしていると、山と向き合うのと同時に、お客さんとも触れ合うことになります。ガイドをされていて印象的なお客さんはいらっしゃいますか。
よい思い出がひとつ、そうでないのがもうひとつあります。良い思い出は、77歳のご年配のお客様で、百名山の最後に平ヶ岳を登りたいというご依頼でした。それも御池側からという、距離が長く厳しいルートを希望されていました。なんでも、その方が昔お父さんと一緒に登ったのがそのルートだったそうです。大変でしたけれど、登れました。頂上で涙を流しながら、一緒に写真を撮ったんですがその時に巻いていたタオルに、「おばあちゃん おめでとう」と孫からのメッセージが書いてあってね。その時は、ガイドっていい仕事だと思いました。
一方でグランドジョラスには苦い思い出があります。どうしても登りたいというお客さんがいて、でも4回トライして駄目だった。北壁のウォーカーリッジまでやりましたけど、成功しなかった。それで最後の機会にとノーマルにチャレンジしたんです。しかし天候が崩れてきて、他の国のパーティも続々と引き返していく状況。なんとか登らせたいという思いで山頂まであと200mまで来て、頂上は見えていました。でも時間がもう無かった。帰りましょうと苦渋の決断をして、案の定帰路は土砂降りで真っ暗な中を戻ったんです。小屋につくとお客様は泣いている。説明はきちんとしましたが、納得いただけず彼女はシャモニーへ帰って行きました。
今同じ状況になっても、やはり戻る選択をします。そもそも、あのタイミングで行ったこと自体が間違いだった。自分の思い入れもあってもうちょっと行ける、という気持ちが働いてしまった。もっと早く撤退するべきだったんです。すべて自分の責任ですが、悔いの残る1日でした。登れなかったことにじゃなく、撤退が遅くなったことに対してです。この2つの登山は忘れられません。

山においては撤退するという判断が一番難しいところかと想像しますが、その判断力をどのように培い、後進のガイドに伝えているのですか。
目に見えるガイドラインを作ることです。例えば谷川岳なら、朝までに40cm降ったら入らず別のところに行くようにする。どんなに人が入っていても、いいパウダースノーであっても、決めた数字に達していたら入らない。その中で、ブランB、プランCを持っておくことで行動の幅を広げるんです。例えば20cm降ったなら、山には入るが一回でも危ないところがあったらそこで止めるとか、トバラースはしない、とかですね。こういうガイドラインをどう構築するかは、絶えず山を歩きながら基準を考えるんです。そしてそれを設定しながら進む。そうでないと、ただ危険だったからやめました、で終わってしまう。
自分もグランドジョラスで痛感しましたが、自分の心の葛藤とか思い入れが判断に作用してはいけないんです。どうしたってガイドにも確証バイアスが働いちゃうんですね。これが、きっちりとした自分のガイドラインを持つことの重要性です。
自然界では常に客観的な指標をもっていないといけない。
自然と喧嘩したり、パフォーマンスをぶつけようとするから想定外のことが起きるんです。自然をリスペクトしていれば、すいませんと誤って撤退できるのに、どうしても同等で対峙しようとしちゃう。挑戦とか名付けてね。アルパインクライマーのようなアスリートが挑戦するのはいいんですよ。いろいろなリスクマネジメントと安全管理をした上で挑むわけですから。一般の方が大自然に挑戦と言うと、それはもう一か八かになってしまう。だからガイドがしっかりと自分のガイドラインに沿って、判断をするべきなんです。
事故は必ず起こるという現実と山岳救助にかける思い
山岳救助に長らく携られていますが、そこにかける思いの強さはどこからくるのでしょうか。
事故っていうのはゼロにはできないんですよ。クライシスマネジメントをしても、一定量必ず発生する。これは受け止めなくちゃいけない事実です。「事故ゼロ運動」なんていうのはまやかしで、精神論で捉え始めると、起きた事故の検証が疎かになるんです。事故は絶対ある。それが10分の1か10000分の1かどうかが重要なのであって、この分母を増やすために起きた事故を検証する必要があるんです。それは誰が悪いかを追求するためではない。

「事故は必ず起こる」からこそいかにその確率を
少なくできるか生涯を懸け取り組んでいる。
この分母を増やすところが長岡さんのガイド活動、そして救助活動の中の大切な目標になっているんですね。
そうです。必ずありますから、事故は。これは確率です。だからいかにそのバイアスを取り払ったり、自分の心の葛藤だとか、クライミング能力や、技術や体力、そういった様々な要素を考えて自分のガイドラインを定められるか。事故が起きれば大勢の人に迷惑を掛けるし、自分のアルピニズムっていうものに対して疑問を抱くことになってしまうから、事故を起こさないようにしよう、と。
グレードではなく、楽しさを競おう
長岡さんはガイドからのメッセージとして、こう書かれています。「クライミングや登山について私の考えは、登るのはゆっくりと、でも終わってみればそこそこの時間で終了。クライミングはほかの人のことは意識せず、グレード等も競わずに、自分の楽しさと競ってください」と。
長年クライミングをしていて、根を詰めて登っていた人間は、みんな止めていっちゃいました。それはグレードで競っているからですね。他人と競ってるんです。ある程度までいくんですけども、負荷を掛けたことを体は覚えてますから、続かないんですよ。私も講師というか、人間として感じるのは、楽しいことと体が楽なこと、嬉しいことしか人間続かないし、覚えられないということです。
お客さんを焦らせたり頑張らせたり、速く行かせるっていうのは全部パワープレイなんですよ。これでできないこともないんですけれども、基本的にガイドというのはお客さんとのコミュニケーション。お客さんを気持ちのいい状態に持っていってあげることでパフォーマンスを上げ、疲れさせなければ結果的に速いんです。あとのロープワークとか登る技術はガイドがちゃんと伝えられればいいんです。

山に生きる者として、これから長岡さんが何かしたいこと、成し遂げたいこと、伝えたいことっていうのは何かありますか。
「ノウハウ」ではなくて「ノウホワイ」とよくお話しています。ノウハウは人から教わったことですが、それをなぜだろうといつも考えること、それがノウホワイ(know why)です。雨が降ってきたけれど、うまく逃げられた、濡れなくて良かった、で終わるのではなく、なぜ自分は雨を予測できなかったのかを考える。わかっていたらレインウェアを着て雨の中を楽しみながらゆっくり歩けたかもしれない。いつも「なぜ」を考える。それができると山登りに広がりが生まれてくると思います。
もちろん最初からそれは難しいから、山に行って何か「あれ?」と感じた時から始めてもらえれば。いつも自然と対話しながら、考えるイメージです。631とよく言うのですが、6は空や周りを見ること。3は一緒に行動するパートナーやお客さんを見て、自分の足元を見るのは1でいい。風の流れや、人の動きを見ながら登ると、なぜ今回はうまく登れたかがわかるんです。そうやって、自然を読めるようになりたいですね。やっぱり目標がないと楽しくないですから、自然と共に生きることはライフワークとして一生続けていくのだと思います。そうなるといいですね。
長岡 健一
KENICHI NAGAOKA
1954年生まれ。群馬県出身。幼少期より父の影響で山へ入り、20代で訪れたマッターホルンで啓示ともいえる国際ガイドと出会う。国際ガイドというプロフェッショナルの仕事に憧れ、47歳で独立。日本では数少ない国際ガイドとして活躍する傍ら、検定員を務め後進の育成に従事する。山岳救急の分野でも精力的な活動を行なっており、山での事故をいかに減らすか、リスクマネジメントの必要性を説いている。国内外の登山ガイドとして、近年はパラグライダーのガイド資格も取得。空にまでその興味関心は及んでいる。TNF ATHLETE PAGE
Instagram