Roger-Viollet/AFLO
6 Women
Who Paved the Path
山への道を切り拓いた女性たち。
1871年、
女性として初めてマッターホルンに登頂した
イギリス出身の登山家ルーシー・ウォーカーは
フランネルのスカートの下にズボンを隠して歩いた。
ズボンを履くことさえ許されなかった時代、
女性が山に登るなど、不埒の極みとされていた。
ウォーカーは登攀を始めてしばらくすると
ビクトリア様式の長いスカートを脱ぎ捨てたという。
それは、「女は女らしくあるべき」という
当時の社会的な規範を打ち破った瞬間だった。
それから約150年。
多くの女性たちが様々な困難を克服し、
山への道を切り拓いてきた。
あらゆる属性に関わらず、自由に山に登れること。
その歓びを分かち合い、讃え合えること。
今ある登山を当たり前のことにしてくれた、
6人の女性たちの軌跡。

アニー・スミス・ペック
1850-1935 / アメリカ

We should be free to do whatever we think we are qualified for
「私たちは、自分に適性があると思うことは何でも、自由にできるはずなのです」
STORY
1911年、アンデス山脈・コロプナ山。標高6,000mを超えるその山頂に、一枚の旗を掲げた女性がいた。アニー・スミス・ペック、61歳。風にはためくその旗には、「Votes for Women=女性に参政権を」の文字があった。
1850年、アメリカ・ロードアイランド州に生まれたペックは4人兄妹の末っ子。3人の兄たちに劣らぬ体力と、負けん気を持った少女だった。高校卒業後、兄たちと同じ大学への進学を希望したが、性別を理由に入学を拒否される。男女差別に抗議するペックに両親は非協力的だった。親元を離れて働き、ようやくミシガン大学への入学を許されたときには24歳になっていた。
修士号を取得したペックはインディアナ州のパデュー大学でラテン語を教え、1883年にはドイツに渡って研究を続けた。1885年、ドイツからギリシャへの旅の途中で目にしたマッターホルンの姿に心を奪われたペックは登山の猛訓練を始め、その10年後、二人のガイドを伴って、女性で3人目となるマッターホルン登頂を果たした。
ペックの功績は世界中に伝えられたが、返ってきたのは賞賛ではなく、バッシングだった。理由は「女性らしくない登山服を身につけていた」こと。腰まであるチュニックにニッカーボッカーズ、がっしりとしたブーツ。ペックの出で立ちに対して「ズボンを履いていた罪で逮捕されるべきか?」という議論が巻き起こったほどだった。
ペックはその後も同じスタイルのまま世界の高峰を登り続け、1908年にはペルーのワスカラン北峰(標高6,655m)の初登頂に成功する。すでに50歳を過ぎていたが、常に誰も成し遂げていないことに挑み、絶え間ない努力を続けた。
1902年、ペックは〈アメリカン・アルパイン・クラブ(アメリカ山岳会)〉の創設メンバーとなる。ヨーロッパの山岳会では女性の参加がほとんど認められていなかった時代に、多くの女性に門戸を開いた。また登山家であると同時に熱心な社会活動家でもあった彼女は、女性参政権運動にも力を注いだ。
「「幼い頃から男女平等を固く信じていた私は、どんなことでも大きな成果をあげれば、女性にとって有利になると思っていました。私たちは、自分に適性があると思うことは何でも、自由にできるはずなのです」
1911年、61歳のペックがコロプナ山の頂に掲げた「Votes for Women=女性に参政権を」の旗。それは多くの女性たちに男性主体の社会の中で声を上げ、行動を起こす勇気を与えた。
合衆国憲法修正第19条の成立によりアメリカの女性たちが参政権を獲得したのは、それから9年後、1920年8月26日のことだった。【参考文献】
Llithub.com〈Climbing Mountains for the Right to Vote〉May 13,2019
unladylike2020.com 〈Annie Smith Peck〉Illustration / Erika Kobayashi
Edit & Text / Yuriko Kobayashi
Supervision / Masami Onda
Special Thanks / Katie Ives(Editor in Chief at Alpinist Magazine)
ミリアム・オブライエン・アンダーヒル
1898-1976 / アメリカ

I did realize that if women were really to lead, that is, to take the entire responsibility for the climb, there couldn’t be any man at all in the party
「もし本当に女性がリードする、つまり登山の全責任を負うのであれば、パーティの中に男性はひとりもいないはずだ」
STORY
1898年、アメリカ・ニューイングランド州に生まれたミリアム・オブライエン・アンダーヒルは、新聞記者の編集者であり、政府高官でもあった父と、医師の母の元で育つ。幼い頃から独立したジェンダー感覚と、 “登る”欲求を持つ子どもだった。
1899年、母親は親戚に宛てた手紙にこうに書いている。
「娘は誕生日に私が買ってきた人形を投げ捨ててしまいました。エレン叔母さんが昨夜来て、この子にはグリースポール(油脂を塗ることで登りづらくした登り棒)か、木登りができる木を買ってあげるわと言っています」
16歳のときに母親と一緒にフランス・アルプスのシャモニーを訪れ、標高2,525mのル・ブレヴァンに登ったアンダーヒルは、そこから空を突き刺すようなモンブランの岩峰を見る。それは将来、彼女が人生をかけて挑むことになる山々だった。
大学で数学と物理学の学士号を、さらに心理学の修士号を取得したオブライエンは、1926年に本格的にロッククライミングを始める。その2年後には、のちに夫となる登山家のロバート・L・M・アンダーヒルとガイドとともにモンブランのエギュイユ・デュ・ディアブルからモン・ブラン・デュ・タキュルの縦走に成功。4,000mを超える5つの岩峰をつなげて登るという、世界で初めての偉業だった。
目覚ましい功績を挙げる傍ら、彼女の中には大きな疑問があった。なぜ女性はいつも男性の後ろについて登っているのか。 自伝『Give Me the Hills』の中でオブライエンは、こう記している。
「有能なリーダーを注意深く観察し、その判断を理解することが最大の学びになるとヘンリーは言った。しかし、女性はそれをしようとしない。どうせリーダーにはなれないとわかっているから、ただ後ろをついて歩いて景色を見ているのだ。だから仮にリーダーをやらせてもらっても、何もできないだろう。しかし、もし本当に女性がリードする、つまり登山の全責任を負うのであれば、パーティの中に男性はひとりもいないはずだ」
そして、こう決意する。
「私はガイドだけでなく、男性も同行しない登山に挑戦してみることにした」
1929年、オブライエンはその言葉通り、フランス人登山家のアリス・ダメムとともに、女性ふたりだけでアルプスで最も困難な登攀ルートのひとつとされていたモンブラン山塊のエギュイユ・デュ・グレポンに登頂する。その知らせを受けたフランスのアルピニスト、エティエンヌ・ブリュールは、悲しげにこう言ったという。
「グレポンは消えてしまった。岩はまだ残っているが、登山としてはもう存在しない。女性ふたりだけで登ったのだから、自尊心のある男は、もう登れないだろう」
3年後の1932年、オブライエンはアリス・ダメムとともに世界で初めて、女性だけでマッターホルンの登頂に成功する。『ナショナルジオグラフィック』誌は彼女らの偉業を「MANLESS ALPINE CLIMBING(男性なしのアルパイン・クライミング)」と表した記事で伝え、讃えた。
これ以降、多くの女性がオブライエンの後を追って社会通念による偏見や障害を打ち破り、「男性なし」で世界最難関のルートに挑んでいくこととなる。【参考文献】
『THE NATIONAL GEOGRAPHIC MAGAZINE』〈MANLESS ALPINE CLIMBING〉 August,1934
『Mountaineering Women : Stories by Early Climbers』David Mazel / Texas A&M University PressIllustration / Erika Kobayashi
Edit & Text / Yuriko Kobayashi
Supervision / Masami Onda
Special Thanks / Katie Ives(Editor in Chief at Alpinist Magazine)、Katie Sauter(American Alpine Club Library Director)
クラウド・コーガン
1919-1959 / フランス
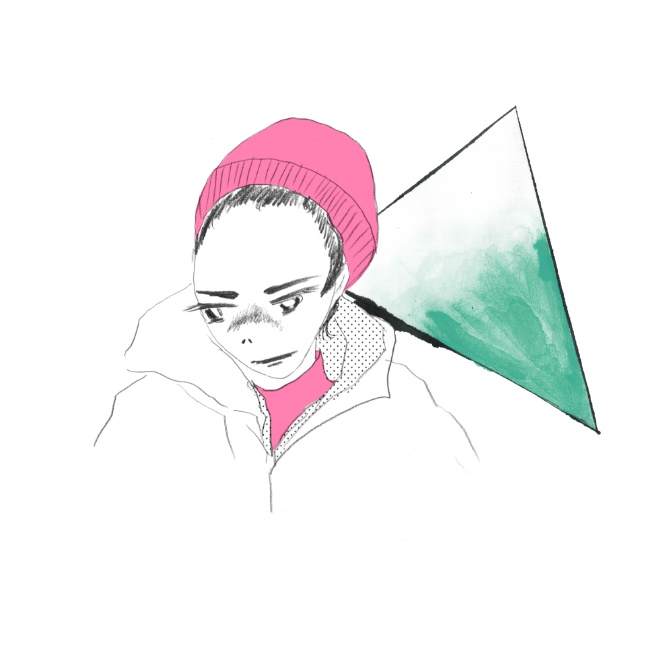
To pursue, always higher, toward the summit. Fate is thus made.
「頂上に向かって、常に高く、追い求めること。運命はこうして作られる」
STORY
1959年10月。ネパールとチベットの国境にある8,000m峰、チョ・オユーで、ひとりの女性が雪崩に飲まれて亡くなった。フランス人登山家、クラウド・コーガン。男性中心だった登山界にあって女性だけのヒマラヤ遠征隊を組み、登頂を目指している最中のことだった。
1919年、フランス・パリで生まれたコーガンは、貧しい生活を助けるために15歳で学校を辞め、お針子として働いた。第二次世界大戦が始まるとニースに移り住み、そこでのちの夫となるジョージ・コーガンに出会い、ロッククライミングを教わる。戦後、結婚したふたりは南仏で小さな衣料品工場を立ち上げ、コーガンは水着のデザインを担当。顧客にはクリスチャン・ディオールも名を連ねていたという。
フランスのアルパイングループに参加した夫妻は、1950年代初頭にアンデス遠征を行うなど、国際的な登山に挑戦する。1951年に夫のジョージを亡くし未亡人となったコーガンは、翌年再びアンデスに渡り、ベルナール・ピエール率いる遠征隊に参加。夫が夢見ていたペルー・サルカンタイ山の初登頂を果たした。
1953年、ピエール率いるヒマラヤ遠征隊に参加したコーガンは、カシミールのヌン山(7,135m)を目指す。途中、多くの仲間が雪崩に巻き込まれ負傷する中、コーガンは登山を続け、世界で初めてその頂を踏んだ。アメリカの新聞はこれを「すべての登山家の夢を実現したパリのドレスデザイナー」と報じた。当時の彼女の日記には、こんな言葉が残されている。
「頂上に向かって、常に高く、追い求めること。運命はこうして作られる」
ヌン山登頂の翌年、コーガンは世界で6番目に高い山、ヒマラヤのチョ・オユー(8,188m)登頂を目指すが、頂上まであと500mというところで悪条件に阻まれ、撤退を余儀なくされる。このときの気持ちを、「沸騰した無力な怒り」と表現したコーガンは、自分の努力不足を悔やみ、同時に「女性も男性登山家に負けないタフさがあることを証明したい」と強く思うようになる。
5年後の1959年、コーガンは自らヒマラヤ遠征隊を組織し、再びチョ・オユーを目指す。隊員はフランス、イギリス、スイス、ベルギー、ネパールから集まった12人の女性たち。世界で初めてとなる女性だけの国際ヒマラヤ遠征隊だった。
9月14日に標高5,640mのベースキャンプに到着した一行は順調に高度を上げ、9月末頃にはベースと山頂の間に4つのキャンプを設営した。登頂まであとわずかという10月2日、山麓にも積雪があるほどの大雪となった日に、大雪崩がキャンプを襲った。数日前、キャンプで不自然に倒れたグラスを見たシェルパたちが「悪い呪文だ」と口走った矢先のことだった。
コーガンを含む4人が滞在していたキャンプはすっかり雪崩に流され、遺体は見つからなかった。生還した隊員たちには、ジャーナリストたちからこんな言葉が投げかけられたという。
「女性が家からそんなに遠く、高く離れた場所に行って、何を探せるのか?」
その答えを持っていたかもしれない女性は、今もヒマラヤに眠っている。【参考文献】
adventurejournal.com〈Alpinist Claude Kogan〉May 29, 2013
alpinist.com 〈Sharp End: Off the Map〉November 6, 2015
philipperochot.com〈Voyage sans retour〉Illustration / Erika Kobayashi
Edit & Text / Yuriko Kobayashi
Supervision / Masami Onda
Special Thanks / Katie Ives(Editor in Chief at Alpinist Magazine)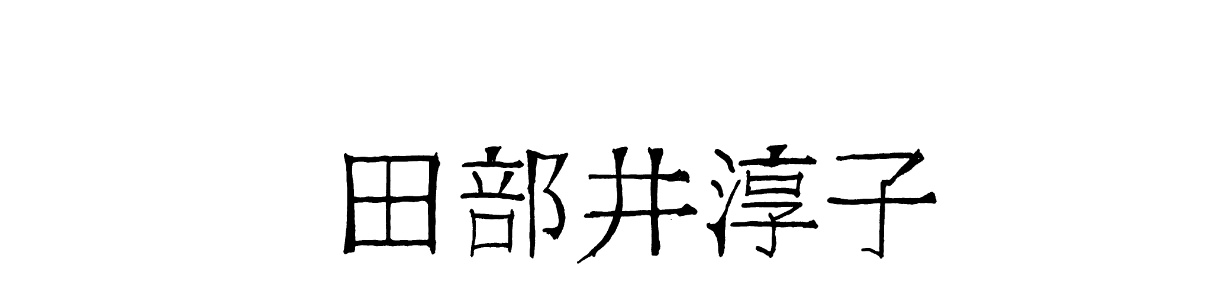
Junko Tabei
1939-2016 / 日本

普通の生活をし、ピアノを弾き、子供を育て、
そんな中から山に行く。ただ山が好きだから。
登りたいから行くだけなのだSTORY
クラウド・コーガンらがチョ・オユーの登頂を目指した10年後、日本でも女性だけのヒマラヤ遠征隊が結成される。その中心メンバーとなったのが、のちに女性初のエベレスト登頂を果たす田部井淳子だった。
福島県の小さな城下町、三春町に生まれた田部井は、10歳のときに学校の教員に連れられて那須連山の茶臼岳と朝日岳に登ったことをきっかけに山への興味を募らせる。中学から高校にかけては兄について安達太良山や磐梯山、吾妻山へ。体が小さく、こと体育では劣ると感じていた田部井にとって、「ゆっくりでも一歩ずつ登れば頂上に立てる」登山は、大きな自信をくれた。
“女子大生”という響きに憧れて東京の昭和女子大学へ進学した田部井は、時間の許す限り各地の山へ登るようになる。卒業後は学術雑誌の編集者として就職。同時に社会人山岳会に参加し、雪山やロッククライミングなど、本格的な登山の世界に入っていく。
基本的に男性パートナーと登攀をした田部井に、「どうせいつもひっぱりあげられているんだろう」という言葉が投げかけられることもあった。田部井は著書の中で、当時の気持ちをこう表現している。
「しょせん男とはそういうものかも知れない。守る人それは男で、守られる人が女なのだ」
27歳の頃、山岳会で知り合った田部井政伸と結婚。東京の六畳一間のアパートで新婚生活を始める。変わらず時間があれば山へ向かう田部井を、夫は快く送り出してくれた。「もし自分に何かあっても、夫がいれば大丈夫だ」という安心感が、田部井をより難しいルートへと導いた。
結婚から数年経ったある日、日本山岳会の女性らの呼びかけで、「女だけでネパール・ヒマラヤに行こう」という案が持ち上がる。すでに1949年には日本山岳会が東京支部に婦人部を設置し、1955 年には女性だけの山岳会〈エーデルワイスクラブ〉が誕生。男女平等の思想のもと、山の世界でもチャレンジ精神のある女性が歓迎される時代が到来していた。
1969年、田部井らは「女子登攀クラブ(LCC)」を創設。「アンナプルナ日本女子登山隊」を結成し、翌年の1970年5月19日、アンナプルナⅢ峰登頂に成功する。その後、長女の出産を経て、1975年には「エベレスト日本女子登山隊」の副隊長兼登攀隊長としてエベレストへ。キャンプが雪崩に襲われるなど数々のトラブルを克服し、同年5月16日、女性として世界で初めてエベレスト(8,848m)の頂に立った。
一躍ときの人となった田部井だが、周囲の熱狂をよそに、長らく「わたしはただの主婦です」と名乗り、エプロン姿で新聞の取材に応じることもあった。のちに田部井は著書『エベレスト・ママさん 山登り半生記』のあとがきに、こう記している。
「夫や子供のために捨身になるのもひとつの生き方であろうが、普通の生活を続けた上で、さらに捨身になって考えられるものを持つ。そんな生き方をしたい。それが山であれ、お琴であれ、ピアノであれ、自分自身のために没入するものを持つということ、これが自分の存在を意識させるものにほかならないからだ」
女性であること、妻であり、母であることによって、何かを諦めることはない。今ある状況の中で、自分はどう生きていきたいのか。それを考え、行動に移す勇気を、田部井はその姿を通して示した。
エベレスト登頂後、男児をもうけた田部井は、出産翌年の1979年にモンブランに登頂。1992年には女性初の七大陸最高峰を制覇する。世界の山々を歩き続ける傍ら、九州大学大学院修士課程に進み、エベレスト・ベースキャンプにおける登山隊による山岳汚染について研究。77歳で亡くなるまで常に没入するものを探し、熱意を傾け続けた人生だった。
昭和から平成へ、大きく羽ばたこうとする女性たちを先導するように、田部井は生涯力強く、目一杯楽しみながら、その道を歩んだ。【参考文献】
『エベレスト・ママさん 山登り半生記』 田部井淳子/著(山と溪谷社)
『タベイさん、頂上だよ』田部井淳子/著(山と溪谷社)Illustration / Erika Kobayashi
Edit & Text / Yuriko Kobayashi
Supervision / Masami Onda
Special Thanks / Katie Ives(Editor in Chief at Alpinist Magazine)、JUNKO TABEI Foundation
リン・ヒル
1961-/ アメリカ
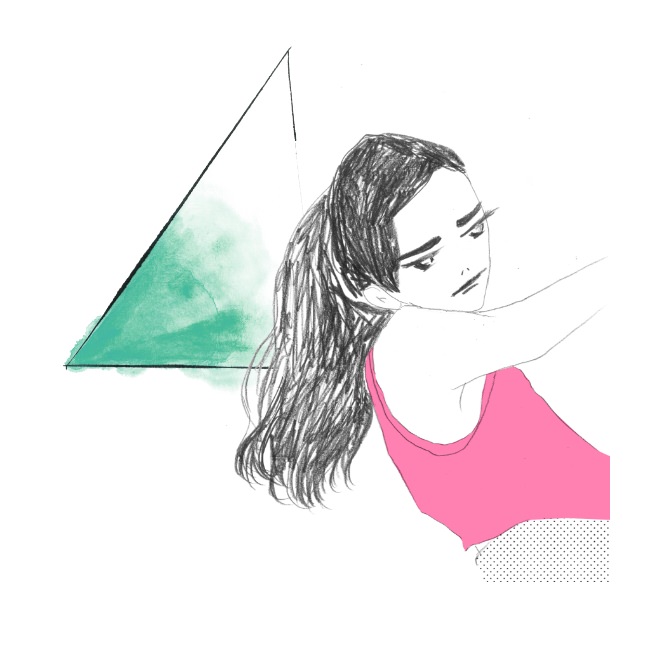
It goes, boys!
「ほら、できたでしょ、男の子たち!」
STORY
男性中心だった山の世界に風穴を開け続けてきた女性登山家たち。「女性初」「女性だけの」という枕詞は輝かしく、後に続く女性を支え、励ますものになったのは間違いないが、裏を返せばそれは、男性と女性を明らかに区別する言葉でもあった。それを鮮やかに打ち破り、性差を越えた“ひとりのクライマー”として歴史に名を刻んだ人がいた。
1961年、アメリカ・デトロイト州に生まれたリン・ヒルは14歳でクライミングを始める。その数週間後にはカリフォルニア・ジョシュアツリーの難ルートを登攀し、周囲を驚かせた。小柄で、体操の経験もあったヒルのクライミングムーブは柔軟性に富み、なおかつ創造的で、体力にものをいわせて登る男性のそれとは明らかに違っていた。
クライミングシーンに女性の姿がほとんどなかった時代。「どうせビギナーズラックだろう」という男性クライマーたちの囁きを耳にしながらも、ヒルは自分ならではのクライミングに自信と歓びを見出し、「岩の前ではみんな平等だ」という意識を持ち続けた。それはヒルが著書『クライミング・フリー』の中に記したこんな言葉によく表れている。
「クライミングの美は各人が自由に振り付けして岩に挑む点にある」
その4年後にはコロラド州の「オフィール・ブローク」というルートをフリークライミング(用具に頼らず、身体能力だけで登攀するクライミング方法)で完登。男性を含め、当時の世界最高に近い5.12cというグレードに成功する。その後はプロの競技クライマーとして世界大会を席巻するなど、世界のクライミングシーンでその存在をたしかなものにしていく。
1993年、競技クライミングから自然の岩を登る伝統的なクライミングに回帰したヒルは、ヨセミテ国立公園で歴史的なクライミングを成功させる。高さ約900m、花崗岩の一枚岩でできた大岩壁エル・キャピタンの中でも最も有名な「ザ・ノーズ」というルートを、世界で初めてフリークライミングで登ったのだ。
登頂後、彼女が言った言葉は今も多くのクライマーに語り継がれている。
「It goes, boys!(ほら、できたでしょ、男の子たち!)」
のちにヒルは、このクライミングが人生において最も重要な登攀であったと語っている。
「クライミングの世界で女性は過小評価され、落胆しているように見えていました。(中略)私は、パフォーマンスには単に男性として生まれたとか、女性として生まれたとか、そういう固定観念だけではない、もっと多くのことが関係しているということに気づいてもらいたかった。それぞれが様々なスキルや欲求を持った個人であり、それが世界を動かしているのだということ知ってもらうのが重要だったのです」
その言葉通り、ヒルによる「ザ・ノーズ」のフリークライミング登攀成功は、性差を越えて、個人としての技術や個性によってクライミングが語られるべきという考え方を生んだ。
人類史上初となる歴史的なクライミングを成功させた翌年、ヒルはさらに驚くべき偉業を成し遂げる。前年に4日間かけて完登した「ザ・ノーズ」を、今度は1日で登り切ったのだ。このワンデイフリークライミングにより、ヒルは“クライミングの神様”となる。そこにはもう“女性クライマー”という肩書きはなかった。
1995年、ヒルは〈ザ・ノース・フェイス〉のクライミングチームに加わり、世界中を旅しながら各地の岩を登った。その後、42歳で息子を出産するとビッグウォールからは距離を置き、“母親”という新しい冒険と挑戦を心から楽しんだ。その傍ら、講演活動やクライミングのガイドやコーチ、テクニックビデオの制作に打ち込んだ。
60歳を過ぎたヒルは今も自由に岩に登り、クライミングコミュニティの活性化や、女性クライマーたちを後押しする活動に力を注いでいる。【参考文献】
『クライミング・フリー』 リン・ヒル、グレッグ・チャイルド/著 小西敦子/訳(光文社文庫)
climbing.com〈“Do You Consider Yourself A Feminist ? ” A Conversation with Lynn Hill〉May 2020
emontana-magazine.com〈LYNN HILL〉Mar 9, 2022
jhnewsandguide.com〈”It goes boys”: Lynn Hill reflects on four decades of climbing as Mountain
Story keynote speaker〉Jan 14, 2020Illustration / Erika Kobayashi
Edit & Text / Yuriko Kobayashi
Supervision / Masami Onda
Special Thanks / Katie Ives
(Editor in Chief at Alpinist Magazine)
Kenichi Moriyama
カトリーヌ・デスティベル
1960-/ フランス
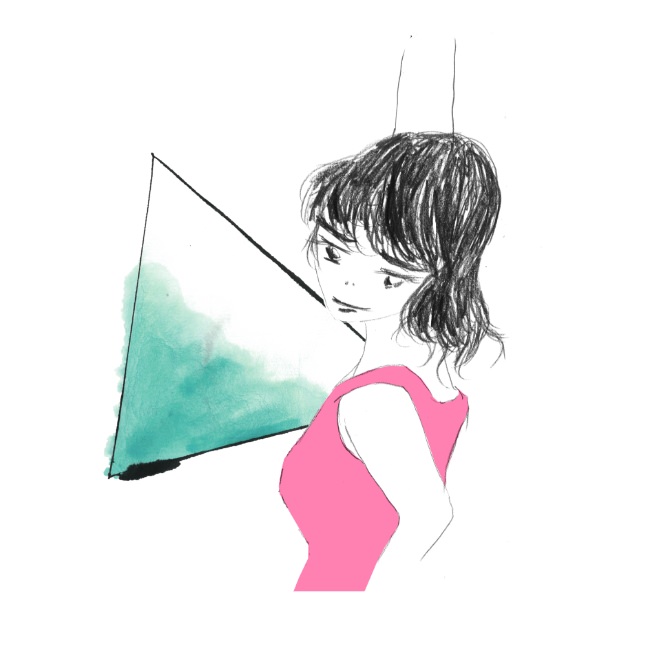
You had to think as a “mountaineer” – not as a “female mountaineer” or “male mountaineer” – in order to be just
「“女性登山家”でも“男性登山家”でもなく、“登山家”として考えなければ、正当な評価は得られないのです」
STORY
リン・ヒルがアメリカのビッグウォールに挑んでいた頃、カトリーヌ・デスティベルはヨーロッパの岩壁に情熱を燃やしていた。ヒルがエル・キャピタンの「ザ・ノーズ」をフリークライミングで完登する前年の1992年、デスティベルは女性として初めて、アイガー北壁の冬季単独登攀に成功。しかも、わずか17時間という、当時としては驚異的な記録だった。
デスティベルは1960年、フランス領アルジェリアのオランで生まれた。ロッククライマーだった両親は、5歳のデスティベルをパリ郊外のクライミングスポット、フォンテーヌブローに連れて行き、アクロバティックなムーブを必要とする岩登りを教えた。10代後半にはすでにアルプス山脈の高山にも足を踏み入れ、17歳でシャモニーにそびえる岩峰の非常に難しいルートを短時間で登るなど、その才能を開花させた。
その後、パリで理学療法士として働き、クライミングとは無縁の生活を送っていたデスティベルがクライミングの世界に戻ったのは、山岳映画への出演がきっかけだった。その中で当時のフランスで女性による登攀としては最高難度のルートを登ったデスティベルは、一躍フランススポーツ界の人気者になる。数社のスポンサーを得たデスティベルは、この頃からプロクライマーとしてのキャリアをスタートさせる。
彼女の名を世界に広めたのは1985年、イタリアで開催された国際クライミング競技会「スポルト・ロッチャ」での優勝だった。それを皮切りに名だたる競技会で成績を残したデスティベルは、コンペスターとして注目を浴びる。この頃、多くの競技会でしのぎを削ったライバルのひとりが、リン・ヒルだった。
当時、「フランス人の2人に1人がその名を知っている」というほど人気を博し、スポーツクライミングの人気を一気に高めることに貢献したデスティベルだったが、1990年にその世界から身を引く。次に彼女が情熱を注いだのが、アルピニズムの世界だった。
1992年に女性として初めてアイガー北壁の冬季単独登攀に成功。さらに翌年にはグランドジョラスのウォーカー稜、翌々年にはマッターホルン北壁のボナッティルートで冬季単独登攀を果たす。
デスティベルはアイガー北壁の冬季単独登攀にあたって、大きなチャレンジを試みていた。それはオンサイト(ルートの情報を事前に一切得ることなく、初見で登り切ること)で登るということ。大きな危険が伴う可能性のあるこのアプローチについて、のちのインタビューでこう語っている。
「私は議論の余地のない完璧な“初”を成し遂げたかったのです。(中略) “女性初”を達成したかったのではありません。トータル・プレミア(性別を越えた“初”)を実現したかったのです。アイガー北壁のオンサイトによる冬季単独登攀は、それまで誰も成し遂げていませんでしたから」
それまでに数多くの“女性初”タイトルを得ていたデスティベルは、自分が同レベルの男性クライマーより多くのスポンサーを得るなど、その性別によって注目されることに納得していなかった。だからこそ、自分自身がまず“女性初”という概念を捨てることにした。
「“女性登山家”でも“男性登山家”でもなく、“登山家”として考えなければ、正当な評価は得られない」
彼女は自分の登攀を通して、その思いを表現しようとした。
37歳で息子を出産したデスティベルは育児と教育に情熱を傾け、登山以外にマウンテンバイクやスキーなど、家族や友人と自然の中で過ごす時間を大切にし、そこに大きな喜びを見出した。現在は山岳専門の出版社を自ら立ち上げ、それまでとは違ったアプローチで登山やクライミングコミュニティに貢献している。
スポーツクライミングとアルパインクライミング、2つの世界で革新的な挑戦を続けたデスティベルは2020年、“登山界のアカデミー賞”とも言われる「ピオレドール賞」の生涯功労賞を受賞した。同賞では“女性初”となる快挙だったが、彼女の功績は間違いなく性別を越え、次の世代の多くのクライマーにインスピレーションを与え続けている。【参考文献】
transylvaniamountainfestival.ro〈INTERVIEW: CATHERINE DESTIVELLE
– THE BEAUTY AND JOY OF THE ASCENT〉2020
climbing.com〈Catherine Destivelle Earns Piolets d’Or Lifetime Achievement Award〉July 23, 2020Illustration / Erika Kobayashi
Edit & text / Yuriko Kobayashi
Supervision / Masami Onda
Special Thanks / Katie Ives(Editor in Chief at Alpinist Magazine)
Kenichi Moriyama






