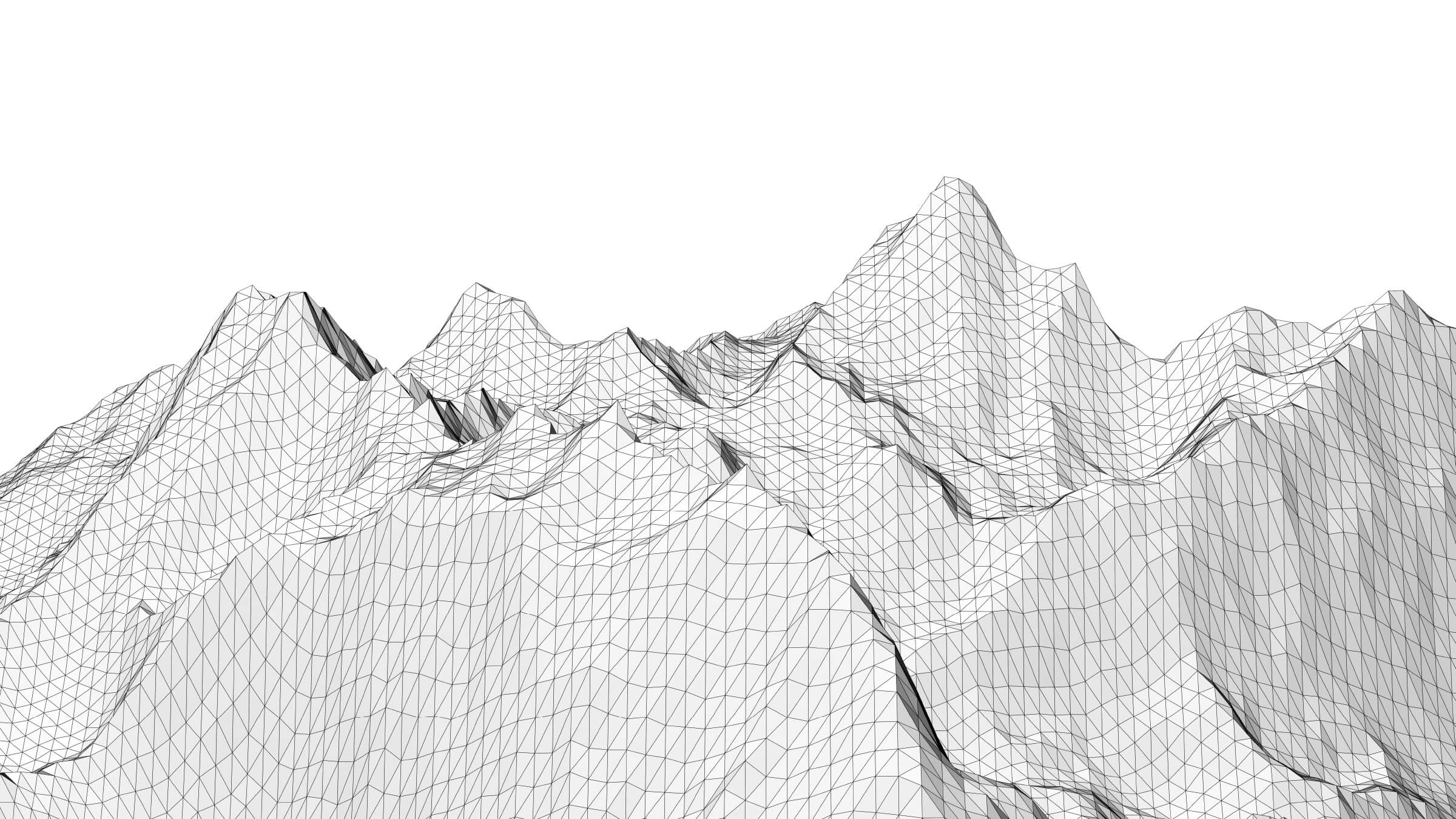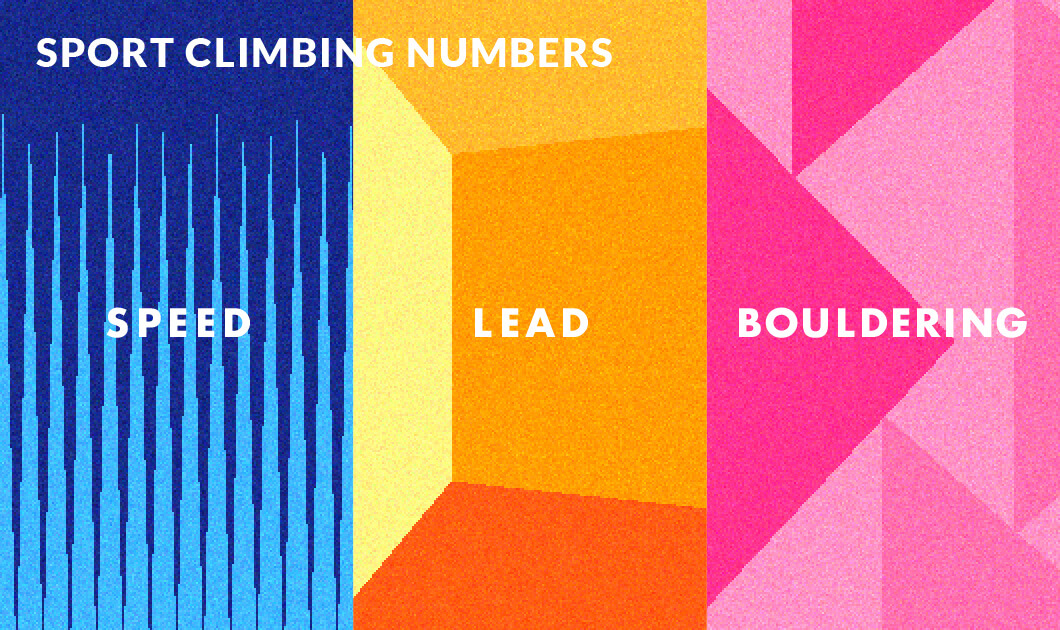クライミングは過去に何度か、価値観の大きな転換を重ねてきた。最初の転換点は、およそ150年前。それ以前、「岩登り」は、登山で山頂に達するためのひとつの技術にすぎなかった。しかしこの頃から、イギリスやドイツ、イタリアなどで同時多発的に「岩を登ること自体」に価値が見出されるようになり、それを専門的に追求する人も現れ始めた。これがクライミングの発祥ともされている。
次なる転換点は、およそ70年前。この頃にはピトンやロープなど道具の発展が飛躍的に進み、その力を借りて、登攀不可能視されていた岩壁も登られるようになっていた。ボルトが発明されて、まったく手がかりのない壁まで登ることまでが可能になった。しかしあるとき、クライマーたちはふと気づく。「道具の力に頼って登っても意味があるのだろうか?」。そしてクライマーは道具を捨て、できるだけシンプルに、ナチュラルな方法で登ることを志向し始めた。それは“Free”であること。この「フリー」は「自由」という意味ではない。“Free from artificial aid”――人工的な手段に頼らない。すなわち、身ひとつで登るという意味での「フリー」。現代にもつながるクライミングの根本思想がこれである。

3度目の転換点が40年前。もともとクライミングは「冒険」であった。ミスをすれば大怪我、あるいは死に至るリスクをはらむものだった。しかし道具や技術の発展により、危険性をできるだけ排除することが可能になり、「スポーツ」としての側面もクローズアップされていく。それまでの伝統的なクライミングと、スポーツとしてのクライミングの決定的な違いは、後者では頂上を必ずしも目指さなくなったことにある。高さ数十m、ときには5mの岩であっても「ルート」として認められ、価値が見出されるようになった。時を同じくして人工壁も登場する。人工的に作られたクライミングウォールが登場したのは1980年代。90年代に入ると、人工壁を利用したクライミングジムが全世界に作られるようになり、クライミング競技もすべてこの人工壁を利用して行われるようになった。これらの結果、ムーブの困難度が以前にも増して追求されるようになり、クライマーの技術は上昇の一途をたどった。

そして現在。もしかしたら私たちは今、4度目の転換点に立っているのかもしれない。150年の歴史をもつクライミングから、「スポーツクライミング」という新しいジャンルが誕生していく瞬間に。150年前に始まったクライミングをver.1.0とすれば、70年前にver.2.0、40年前にver.3.0と進化してきた。そして今、ver.4.0にアップデートされようとしている。90年代までは、人工壁は自然の岩の代用品にすぎなかった。クライマーの最終的な目標は、あくまで岩場のルートを登ることに置かれていた。しかし2000年代に入ると、最初から人工壁でクライミングを始め、岩場には行かない“人工壁ネイティブ”のクライマーが現われ始める。この5年ほどでその動きはさらに加速している。
クライミング人口は年々増え続け、テレビでクライミングの様子が放映されることも珍しくなくなった。かつては親に危険だからと止められる趣味の筆頭格だったクライミングも、今では、小学生が親に連れられてクライミングジムにやってくるようになった。時代は大きく変わろうとしている。クライミングの内容自体も大きく変わってきている。ルートの内容を自由に設定できる人工壁では、自然の岩ではありえないルートを設定することも可能だ。従来の発想にはなかったアクロバティックなテクニックが次々に開発され、クライミングは技術面でも大きく進化した。アスリートの進化のスピードは目を見張るものがあり、それは、3年前のテクニックでは現代のワールドカップでは太刀打ちできないほどだ。

こうして急速に進化してきたクライミングが、2021年をひとつの臨界点として、新たなステージに進もうとしている。旧来のクライミングの発想では想像もできなかったかたちに、今後スポーツクライミングは進化していく可能性がある。とはいえ、変わらないものもある。スポーツクライミングが脚光を浴びる一方で、岩場で行われるクライミングが古いものとして廃れたのかというと、むしろ逆である。岩場に出かけるクライマーは今でも増え続けている。自然の岩には、人工壁にはない開放感があり、挑戦の舞台となりうる冒険性がある。そこにあるのは競争の楽しみではなく、創造の楽しみ。それは150年間変わることがない。世界を閉塞感で覆ったパンデミック以降、クライミングのこうした側面を求める人々の志向は、今までになく高まっているようにさえ思える。新しい時代を迎え、旧来になかった分野に拡大を始めたスポーツクライミングと、150年間、進化を続けてきた岩場のクライミング。このふたつのベクトルをもって、これからのクライミングは進化していくことになるのだろう。