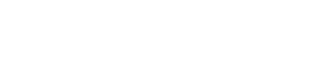Chapter 4 Vol.Three
SOUL BEAT ASIA
Hitsuke Nugumi
Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭
火付ぬ組
TEXT by HAJIME OISHI
PHOTOGRAPHS by KEIKO OISHI, JUNYA TAKATSU, KANJI FURUKAWA
PHOTOGRAPHS by KEIKO OISHI, JUNYA TAKATSU, KANJI FURUKAWA
愛知県豊田市で開催されてきた橋の下世界音楽祭の運営は、日本各地から集結する仲間たちによって支えられている。彼らはものづくりに対する共通の信念と遊び心を持ち、橋の下世界音楽祭の場でそれらを爆発させる。そうした橋の下から広がるネットワークは回を重ねるごとに拡張し、現在では海外へも広がりつつある。橋の下に集う各地の職人たちにリモートインタヴューを試みた。
橋の下世界音楽祭の運営チームには個性豊かな顔ぶれが揃っている。彼らは「火付ぬ組」という集団を構成していて、バックステージでは「ぬ組」の半纏を羽織った人々が出演者とともにくつろいでいる。そこではタトゥーを全身に入れている者は珍しくないし、日々肉体労働で鍛え抜かれた褐色の肌の男たちがいれば、民族衣装を着た音楽家、渋い佇まいの職人、モヒカン頭のパンクスもいる。今すぐにでも映画を撮影できそうな面構えばかりで、一件何万円で仕事を受けた見ず知らずの業者はそこにはいない。
通常の祭りの場合、運営団体を構成しているのは開催地の地域コミュニティーの人々である。神社の氏子や町内会・自治会、商店街、あるいはそれらが手を組んだ実行委員会形式の場合もあるが、少なくとも開催地および近隣に住む人々が運営を担っている。
橋の下世界音楽祭の場合もまた、地元豊田の人々が中心的な役割を担っている。ただし、運営チーム全体で見ると豊田の外からやってきたスタッフのほうが断然多く、それが特徴のひとつといえる。開催日が近くなると手に職を持った連中が各地から豊田へと集結し、数日間だけの幻の町を作り上げ、後片付けを終えるとそれぞれの地元へと颯爽と帰っていくのだ。
しかも、彼らは橋の下に金銭的な見返りを求めてやってくるわけではない。それどころか何日間もデイリーワークを休み、時には赤字覚悟で橋の下にやってくる。会社の経営者としてはちょっとクレイジーだし、フリーランスとしてはリスキーであるとも思う。
つまり、橋の下には彼らを惹きつける魔力みたいなものがあるのだ。祭り当日、運営スタッフの高揚した表情を目の当たりにすると、彼らが何のため橋の下にやってきたのか理解することができるはずだ。
 橋の下に作り上げられる数日間だけの「まぼろしの町」。そのイメージの源は、基本的に愛樹くんと根木くんが生み出している。それは2012年の1回目も、規模を大きく拡大した2018年も変わらない。
橋の下に作り上げられる数日間だけの「まぼろしの町」。そのイメージの源は、基本的に愛樹くんと根木くんが生み出している。それは2012年の1回目も、規模を大きく拡大した2018年も変わらない。
開催を重ねてきて大きく変わったのは、関わる人物が増え、愛樹くんと根木くんが知らないうちに町が作り上げられるようになったという点だ。ふたりもまた、そのプロセスを心から楽しんでいる。愛樹くんはこう話す。
「設計図がない感じだよね。10年やってるけど、いまだに最初は俺がマジックと鉛筆で描いたものから始まってる。下町ステージは米子のZERO ACTIONがやってるし、草原ステージは造景集団「某(なにがし)」やANTIBODIES COLLECTIVE。全体の配置とバランスだけは俺が考えてるけど、あとは勝手にやってる感じ。おお、こんな感じになったんだ!と驚いてるぐらいで(笑)」
通常の祭りの場合、運営団体を構成しているのは開催地の地域コミュニティーの人々である。神社の氏子や町内会・自治会、商店街、あるいはそれらが手を組んだ実行委員会形式の場合もあるが、少なくとも開催地および近隣に住む人々が運営を担っている。
橋の下世界音楽祭の場合もまた、地元豊田の人々が中心的な役割を担っている。ただし、運営チーム全体で見ると豊田の外からやってきたスタッフのほうが断然多く、それが特徴のひとつといえる。開催日が近くなると手に職を持った連中が各地から豊田へと集結し、数日間だけの幻の町を作り上げ、後片付けを終えるとそれぞれの地元へと颯爽と帰っていくのだ。
しかも、彼らは橋の下に金銭的な見返りを求めてやってくるわけではない。それどころか何日間もデイリーワークを休み、時には赤字覚悟で橋の下にやってくる。会社の経営者としてはちょっとクレイジーだし、フリーランスとしてはリスキーであるとも思う。
つまり、橋の下には彼らを惹きつける魔力みたいなものがあるのだ。祭り当日、運営スタッフの高揚した表情を目の当たりにすると、彼らが何のため橋の下にやってきたのか理解することができるはずだ。

PHOTO by KEIKO OISHI
開催を重ねてきて大きく変わったのは、関わる人物が増え、愛樹くんと根木くんが知らないうちに町が作り上げられるようになったという点だ。ふたりもまた、そのプロセスを心から楽しんでいる。愛樹くんはこう話す。
「設計図がない感じだよね。10年やってるけど、いまだに最初は俺がマジックと鉛筆で描いたものから始まってる。下町ステージは米子のZERO ACTIONがやってるし、草原ステージは造景集団「某(なにがし)」やANTIBODIES COLLECTIVE。全体の配置とバランスだけは俺が考えてるけど、あとは勝手にやってる感じ。おお、こんな感じになったんだ!と驚いてるぐらいで(笑)」

PHOTO by KEIKO OISHI
毎年テーマが設定される下町ステージは、拡張する橋の下世界音楽祭のひとつの象徴でもある。銭湯がモチーフになった年もあれば、大衆酒場の年もあった。そういえば、下町ステージの横に物干し台が設置され、そこにセッティングされたブースでDJをやったこともあった。いずれも経費をたっぷりかけた豪華なステージというよりも、廃材などを利用した手作りのステージである。「8時だョ!全員集合」的とでもいおうか、そこには作り手の遊び心が詰まっている。
そんな下町ステージの製作を担当しているのが、鳥取県米子市の建築会社ZERO ACTION ARCHITECTだ。
代表取締役の松永裕治さんは2008年から2011年まで米子で「DAISENMONDO」という野外フェスティヴァルをオーガナイズしていた過去があり、そのときにTURTLE ISLANDとその仲間たちと交流を深めた。2011年の東日本大震災では愛樹くんや橋の下初代現場監督のシゲヤスさんによるボランティア・チーム、ZERO ACTIONにも参加。そうした縁から橋の下世界音楽祭には2012年の1回目から携わっている。
裕治さんはZERO ACTION ARCHITECTが始まった経緯をこう語る。
「豊田でも建築関係の仕事をやっとったんだけど、そっちもあんまり調子よくなくて。地元の友達が先に米子に来とって、その子から『米子に来たらどう?』って声をかけてもらって。裕治くんやお兄ちゃんのケンちゃんとは震災のときから友達になっとったもんで、裕治くんに相談して米子に来ることになりました」
ZERO ACTION ARCHITECTについてシゲヤスさんは「型にはまっていない会社」と評する。なにせここで働くために豊田から米子へと移住してしまったぐらいで、裕治さんたちに寄せるシンパシーは強い。
「文字通りZEROからACTIONしていく会社っていう感じですよね。建築関係の会社だから、当然型というか、会社としての枠組みが普通はあるじゃないですか。そういうものにはまっていない。おもしろいところだと思いますね」
では、裕治さんやシゲヤスさんたちは、橋の下世界音楽祭の下町ステージをどのように作ってきたのだろうか。まずは裕治さんの証言。
「下町ステージも最初は規模が小さかったし、ベースの素材は竹と襖、障子、コンパネぐらいですよね。竹で骨組みを組んで、襖を貼るだけ。シゲヤスがいろんなところから廃材を持ってくるので、それを使っていました」
そんな下町ステージの製作を担当しているのが、鳥取県米子市の建築会社ZERO ACTION ARCHITECTだ。
代表取締役の松永裕治さんは2008年から2011年まで米子で「DAISENMONDO」という野外フェスティヴァルをオーガナイズしていた過去があり、そのときにTURTLE ISLANDとその仲間たちと交流を深めた。2011年の東日本大震災では愛樹くんや橋の下初代現場監督のシゲヤスさんによるボランティア・チーム、ZERO ACTIONにも参加。そうした縁から橋の下世界音楽祭には2012年の1回目から携わっている。
裕治さんはZERO ACTION ARCHITECTが始まった経緯をこう語る。
「豊田でも建築関係の仕事をやっとったんだけど、そっちもあんまり調子よくなくて。地元の友達が先に米子に来とって、その子から『米子に来たらどう?』って声をかけてもらって。裕治くんやお兄ちゃんのケンちゃんとは震災のときから友達になっとったもんで、裕治くんに相談して米子に来ることになりました」
ZERO ACTION ARCHITECTについてシゲヤスさんは「型にはまっていない会社」と評する。なにせここで働くために豊田から米子へと移住してしまったぐらいで、裕治さんたちに寄せるシンパシーは強い。
「文字通りZEROからACTIONしていく会社っていう感じですよね。建築関係の会社だから、当然型というか、会社としての枠組みが普通はあるじゃないですか。そういうものにはまっていない。おもしろいところだと思いますね」
では、裕治さんやシゲヤスさんたちは、橋の下世界音楽祭の下町ステージをどのように作ってきたのだろうか。まずは裕治さんの証言。
「下町ステージも最初は規模が小さかったし、ベースの素材は竹と襖、障子、コンパネぐらいですよね。竹で骨組みを組んで、襖を貼るだけ。シゲヤスがいろんなところから廃材を持ってくるので、それを使っていました」

PHOTO by KEIKO OISHI
シゲヤスさんがこう続ける。
「解体する家があったら、そこにあるものを持ってきたり。だから最初の年はほとんど買ってない。買ったのはコンパネぐらいじゃない? 足場も借りてきてたし、4年ぐらいはそんな感じだったよね。基本的に下町ステージは現場に入ってから何にする?って相談をして、そこからテーマを決めていく感じ」
その場でさまざまな人々のアイデアを取り入れながら、ひとつのステージを作り上げていく。そう書くと聞こえはいいが、時にはすでに開演しているにもかかわらずトンテンカンテンとステージを作っているケースもあるぐらいで、効率を考えるとありえないスタイルである。普段は納期のある仕事を請け負っている裕治さんは「普通の会社では考えられんですわね(笑)」と笑い、こう続ける。
「普通の会社だったら効率を考えなきゃいけないわけじゃないですか。でも、橋の下はどう考えても非効率的なやり方でやってるわけで。あと、社会的に規制されている部分があって、通常はそこで止まるんですよね。『ここはやったらいかん』みたいに。でも、橋の下は後から考えるタイプで、やってしまってから『駄目だったね』と(笑)。そういうのがやっぱり勉強になるし、地元に持って帰る材料になるんですよ。考え方自体も仕事に反映しますしね」
橋の下に広がる広大なスペースに、さまざまな地域からやってきた人たちが集い、繋がる。そこで生まれるエネルギーもまた橋の下の強みであり、おもしろさである。では、裕治さんは愛樹くんや根木くんたちのどのような部分に共感しているだろうか。
「根木ちゃんや愛樹くんはひとつの線を超えたところにいるんですよ。あとはどうなるかわからんけど、向こう側までいってみよう――彼らは出会ったときからそういう人たちですね。なんかやらかすよね? という。人間的にもパワーがある人たちですから」
橋の下にはいくつかのプロトタイプがあった。たとえば2011年に名古屋で開催された大規模な野外イヴェント「ズナマ歌踊祭」。そして、愛樹くんが2013年まで豊田で経営していたライヴスペース「斑屋」。斑屋のスタッフも務めていたシゲヤスさんはこう話す。
「斑屋も橋の下の原型だよね。今となっては全国からいろんな人たちが集まって手伝ってくれるけど、あれは愛樹くんがずっとひとりで作っとって。愛樹くんは『自分が酒を飲めてライヴをやれる場所を作りたかった』と言うけど、みんなが楽しめる場所を作りたくてコツコツやってましたね。どんな時もみんなが楽しくなることを考えてる優しい人なんですよ。ウッフッフッフ」
当初は少人数でやっていたものが、さまざまな人々の共感を得て広がっていく。橋の下も斑屋と同じプロセスを経て拡大していったといえる。裕治さんも巻き込まれたひとりだろうし、僕も間違いなくそのひとりだろう。 だが、10代のころから愛樹くんのことを知るシゲヤスさんはこう言う――「愛樹くんは自分が考えてることをやり続けてるだけだと思うけど」と。大きなうねりの中心にはいつも愛樹くんがいたのである。
「解体する家があったら、そこにあるものを持ってきたり。だから最初の年はほとんど買ってない。買ったのはコンパネぐらいじゃない? 足場も借りてきてたし、4年ぐらいはそんな感じだったよね。基本的に下町ステージは現場に入ってから何にする?って相談をして、そこからテーマを決めていく感じ」
その場でさまざまな人々のアイデアを取り入れながら、ひとつのステージを作り上げていく。そう書くと聞こえはいいが、時にはすでに開演しているにもかかわらずトンテンカンテンとステージを作っているケースもあるぐらいで、効率を考えるとありえないスタイルである。普段は納期のある仕事を請け負っている裕治さんは「普通の会社では考えられんですわね(笑)」と笑い、こう続ける。
「普通の会社だったら効率を考えなきゃいけないわけじゃないですか。でも、橋の下はどう考えても非効率的なやり方でやってるわけで。あと、社会的に規制されている部分があって、通常はそこで止まるんですよね。『ここはやったらいかん』みたいに。でも、橋の下は後から考えるタイプで、やってしまってから『駄目だったね』と(笑)。そういうのがやっぱり勉強になるし、地元に持って帰る材料になるんですよ。考え方自体も仕事に反映しますしね」
橋の下に広がる広大なスペースに、さまざまな地域からやってきた人たちが集い、繋がる。そこで生まれるエネルギーもまた橋の下の強みであり、おもしろさである。では、裕治さんは愛樹くんや根木くんたちのどのような部分に共感しているだろうか。
「根木ちゃんや愛樹くんはひとつの線を超えたところにいるんですよ。あとはどうなるかわからんけど、向こう側までいってみよう――彼らは出会ったときからそういう人たちですね。なんかやらかすよね? という。人間的にもパワーがある人たちですから」
橋の下にはいくつかのプロトタイプがあった。たとえば2011年に名古屋で開催された大規模な野外イヴェント「ズナマ歌踊祭」。そして、愛樹くんが2013年まで豊田で経営していたライヴスペース「斑屋」。斑屋のスタッフも務めていたシゲヤスさんはこう話す。
「斑屋も橋の下の原型だよね。今となっては全国からいろんな人たちが集まって手伝ってくれるけど、あれは愛樹くんがずっとひとりで作っとって。愛樹くんは『自分が酒を飲めてライヴをやれる場所を作りたかった』と言うけど、みんなが楽しめる場所を作りたくてコツコツやってましたね。どんな時もみんなが楽しくなることを考えてる優しい人なんですよ。ウッフッフッフ」
当初は少人数でやっていたものが、さまざまな人々の共感を得て広がっていく。橋の下も斑屋と同じプロセスを経て拡大していったといえる。裕治さんも巻き込まれたひとりだろうし、僕も間違いなくそのひとりだろう。 だが、10代のころから愛樹くんのことを知るシゲヤスさんはこう言う――「愛樹くんは自分が考えてることをやり続けてるだけだと思うけど」と。大きなうねりの中心にはいつも愛樹くんがいたのである。

PHOTO by JUNYA TAKATSU
橋の下から大きくはみ出した草原の一角に、竹で組んだ巨大な東屋がある。東屋というにはあまりに個性的なその造形物は、橋の下の象徴的なイメージのひとつともなっている。豊田市駅から東に向かい、豊田大橋の上から会場を見下ろすと、最初に巨大な東屋が見えてくる。その瞬間、ついに橋の下に戻ってきたぞ! という感動が込み上げてくるのだ。
草原ステージを担当しているのは、庭師を中心に構成される造景集団「某」だ。
2015年、橋の下の草原ステージに「木陰となる東屋的な場所を作ってくれないか」という依頼を受け、赤塚剛さんと見城周さんなど数人でスタート。現在は庭師だけでなく、装飾家やヒンメリ作家も加わり、さまざまなイヴェントやライヴで空間表現を行なっている。
剛さんは草原ステージの製作に携わる前の2014年、噂を聞きつけて橋の下世界音楽祭に足を踏み入れている。剛さんはこう話す。
「僕はもともとヒップホップをやっとって、その活動が一段落ついたときに橋の下に遊びに行ったんですよ。会場の作りを見て衝撃を受けました。出演者として出たいというよりも造園家の職人としてめちゃくちゃうずくものがあったんですよ。こんなに楽しそうなことをやってるんだという、琴線に触れるような感覚があった。俺も何かやりたい!と思いましたね」
職人としてうずくものがあった――剛さんのこの言葉は、橋の下に広がるクリエイティヴィティーを端的に表現するものでもあるだろう。剛さんはさらに続ける。
「職人としては普段の現場でそれぞれやってることだと思うんですよ。でも、それをひとつのイヴェントで、しかもすぐ壊さなきゃいけないにもかかわらず、あそこまで作り込んでいる。一夜城の儚さを知りながら、みんなが楽しそうにやってるんですよね。その翌年、何かやらないかと声がかかって。そりゃやるやる!となりますよね(笑)」
草原ステージを担当しているのは、庭師を中心に構成される造景集団「某」だ。
2015年、橋の下の草原ステージに「木陰となる東屋的な場所を作ってくれないか」という依頼を受け、赤塚剛さんと見城周さんなど数人でスタート。現在は庭師だけでなく、装飾家やヒンメリ作家も加わり、さまざまなイヴェントやライヴで空間表現を行なっている。
剛さんは草原ステージの製作に携わる前の2014年、噂を聞きつけて橋の下世界音楽祭に足を踏み入れている。剛さんはこう話す。
「僕はもともとヒップホップをやっとって、その活動が一段落ついたときに橋の下に遊びに行ったんですよ。会場の作りを見て衝撃を受けました。出演者として出たいというよりも造園家の職人としてめちゃくちゃうずくものがあったんですよ。こんなに楽しそうなことをやってるんだという、琴線に触れるような感覚があった。俺も何かやりたい!と思いましたね」
職人としてうずくものがあった――剛さんのこの言葉は、橋の下に広がるクリエイティヴィティーを端的に表現するものでもあるだろう。剛さんはさらに続ける。
「職人としては普段の現場でそれぞれやってることだと思うんですよ。でも、それをひとつのイヴェントで、しかもすぐ壊さなきゃいけないにもかかわらず、あそこまで作り込んでいる。一夜城の儚さを知りながら、みんなが楽しそうにやってるんですよね。その翌年、何かやらないかと声がかかって。そりゃやるやる!となりますよね(笑)」

PHOTO by JUNYA TAKATSU
一方の周さんは、2015年に初めて橋の下を訪れたときのことをこう回想する。
「発想をモノとしてちゃんと形にしているところに衝撃を受けました。庭を作っていると綺麗さや完璧なものを追い求めがちだけど、橋の下はそういうものじゃない。人生遊んでるなあ、という感じというか(笑)。
あと、僕は仕事で役所と付き合うこともあるので、河川敷でああいうことをやるということは、どういうところと打ち合わせをし、どこに許可を取っているか、ある程度見えてくるんですね。そこを突破してこういうことをやってるんだ、という驚きもあった」
2015年の1年目、剛さんと周さんは竹を使った造形物を作り上げる。使ってる素材はほとんどが矢作川の河川敷でとったもの。そこに庭師の技術やノウハウを用いて新たなステージを作り上げた。
その年の2日目、こんなことがあったという。周さんは言う。
「大人たちが酔っぱらって楽しんでいる横で、子供たちのスペースがちょっと少なく感じたんです。子供たちをロックするために僕らの知恵と技術でできることがあるんじゃないかと思って、2日目にブランコをつけたんですよ。そうしたら子供たちで大人気になって(笑)。その光景を見たときに、橋の下の世界で僕たちもやれることがあるんじゃないかと思えたんですよ」
周さんたちは準備と片付けを合わせると、毎回2週間もの時間を橋の下に費やしている。その期間は通常の仕事はできるわけもなく、かといって橋の下で莫大な収益を得るわけでもない。「それでも橋の下に参加するのはなぜなんでしょうか」――僕の質問に対し、周さんはこう答える。
「僕も剛くんも『あの世界を一緒に作りたい』という衝動で始まってるんですよ。普段の生活とは違う環境を求めて、みんなお金払ってでも海外旅行に行くじゃないですか。なぜそこにお金を払うのか、疑問はないわけですよ。海外旅行に行くような感じなんですよね、橋の下って。サグラダファミリアを見るためにはバルセロナに行くしかないけど、橋の下ではサグラダファミリアを作ることもできる。僕にとってはそういう感覚なんです」
周さんの言葉に触発されるかのように、剛さんがこう続ける。
「やってる最中とかやっとる前とか結構むかついたり、喧嘩になることもあるんだけど、あの祭りって余韻がすごいんですよ。普段はクソみたいな仕事もするんですけど(笑)、橋の下であの感覚を味わえるから1年間がんばることができる。お祭り好きの人たちも同じ感覚なのかなと思いますよね。
僕の地元である名古屋っていい大人が本気になるような大きな祭りがあんまりなくて、僕も小さいころからそういう祭りを渇望していたところもあって。それを隣町である豊田で見つけたっていう感覚があるんです」
「発想をモノとしてちゃんと形にしているところに衝撃を受けました。庭を作っていると綺麗さや完璧なものを追い求めがちだけど、橋の下はそういうものじゃない。人生遊んでるなあ、という感じというか(笑)。
あと、僕は仕事で役所と付き合うこともあるので、河川敷でああいうことをやるということは、どういうところと打ち合わせをし、どこに許可を取っているか、ある程度見えてくるんですね。そこを突破してこういうことをやってるんだ、という驚きもあった」
2015年の1年目、剛さんと周さんは竹を使った造形物を作り上げる。使ってる素材はほとんどが矢作川の河川敷でとったもの。そこに庭師の技術やノウハウを用いて新たなステージを作り上げた。
その年の2日目、こんなことがあったという。周さんは言う。
「大人たちが酔っぱらって楽しんでいる横で、子供たちのスペースがちょっと少なく感じたんです。子供たちをロックするために僕らの知恵と技術でできることがあるんじゃないかと思って、2日目にブランコをつけたんですよ。そうしたら子供たちで大人気になって(笑)。その光景を見たときに、橋の下の世界で僕たちもやれることがあるんじゃないかと思えたんですよ」
周さんたちは準備と片付けを合わせると、毎回2週間もの時間を橋の下に費やしている。その期間は通常の仕事はできるわけもなく、かといって橋の下で莫大な収益を得るわけでもない。「それでも橋の下に参加するのはなぜなんでしょうか」――僕の質問に対し、周さんはこう答える。
「僕も剛くんも『あの世界を一緒に作りたい』という衝動で始まってるんですよ。普段の生活とは違う環境を求めて、みんなお金払ってでも海外旅行に行くじゃないですか。なぜそこにお金を払うのか、疑問はないわけですよ。海外旅行に行くような感じなんですよね、橋の下って。サグラダファミリアを見るためにはバルセロナに行くしかないけど、橋の下ではサグラダファミリアを作ることもできる。僕にとってはそういう感覚なんです」
周さんの言葉に触発されるかのように、剛さんがこう続ける。
「やってる最中とかやっとる前とか結構むかついたり、喧嘩になることもあるんだけど、あの祭りって余韻がすごいんですよ。普段はクソみたいな仕事もするんですけど(笑)、橋の下であの感覚を味わえるから1年間がんばることができる。お祭り好きの人たちも同じ感覚なのかなと思いますよね。
僕の地元である名古屋っていい大人が本気になるような大きな祭りがあんまりなくて、僕も小さいころからそういう祭りを渇望していたところもあって。それを隣町である豊田で見つけたっていう感覚があるんです」

PHOTO by KEIKO OISHI
2016年、橋の下に巨大な櫓が初お目見えした。通称「ちどり櫓」。愛樹くんの依頼を受けて櫓を作り上げたのは、山治という屋号で活動する豊田市の大工、神尾治志さんだ。愛樹くんとは10代からの付き合いだという
「本当は宮大工になりたかったの。うちの母親の同級生が宮大工だったので弟子入りしたかったんだけど、断られちゃって。それがあるもんだから、今作るものでもどこかでお宮さんを意識しちゃう。やっぱり美しいものがいいよね」
治志さんは現在、宮大工の手法を応用しながら自宅を作っている。治志さんがすごいのは、家だけでなく、大工に使う道具まで自身で製作・加工しているという点だ。藁を編んで縄を作るための道具も自分に合うように作り直してしまうし、釘ひとつひとつもわざわざ加工してから使う。その結果、自宅を作り始めてから数年の歳月が経過しているものの、まだ完成には漕ぎ着けていない。
 2012年に初開催された橋の下世界音楽祭は、年を追うごとに規模を拡張。2018年にはピークに達した。さまざまなアーティストが出演し、多種多様な出店が並び、しかも入場料は投げ銭。橋の下世界音楽祭の精神や愛樹くんたちのヴィジョンなど露知らず、「ただで遊べるフェス」として会場にやってきた来場者も少なくなかった。その結果、ゴミは溢れかえり、喧嘩の場面も目撃した。2018年の橋の下での疲れ切った関係者たちの表情を僕は忘れることができない。
2012年に初開催された橋の下世界音楽祭は、年を追うごとに規模を拡張。2018年にはピークに達した。さまざまなアーティストが出演し、多種多様な出店が並び、しかも入場料は投げ銭。橋の下世界音楽祭の精神や愛樹くんたちのヴィジョンなど露知らず、「ただで遊べるフェス」として会場にやってきた来場者も少なくなかった。その結果、ゴミは溢れかえり、喧嘩の場面も目撃した。2018年の橋の下での疲れ切った関係者たちの表情を僕は忘れることができない。
案の定、2019年の開催は中止され、以降開催されることなく現在に至っている(2021年の「橋の下盆踊りンピック」など別の形では行われている)。愛樹くんはこう話す。
「料金を取れば来る人も絞れるじゃん。でも、間口を広げて『誰でも来てよ』とすると、すげえ大変で。話題になるほどおかしなのも来るしさ。フリーフェスの行き着くところが垣間見えた部分もあった。あの規模になったら下手をしたら人が死ぬからね。誰かが出鱈目な建物を建てて、それが崩れて人が死ぬことは全然ありえる。適当にやっているようで、みんな細かく見回ってたよね。この建て方は危ないでしょと注意したり。自由にできるぶん、責任も当然ある」
根木くんも続ける。
「2018年はピークを迎えた感じもあったよね。パンクしそうだった。俺たちも橋の下がどんどん大きくなることに違和感を感じていたし、『俺らがやりたいのはこういうものじゃないんだけどな』と思うこともあった」
「本当は宮大工になりたかったの。うちの母親の同級生が宮大工だったので弟子入りしたかったんだけど、断られちゃって。それがあるもんだから、今作るものでもどこかでお宮さんを意識しちゃう。やっぱり美しいものがいいよね」
治志さんは現在、宮大工の手法を応用しながら自宅を作っている。治志さんがすごいのは、家だけでなく、大工に使う道具まで自身で製作・加工しているという点だ。藁を編んで縄を作るための道具も自分に合うように作り直してしまうし、釘ひとつひとつもわざわざ加工してから使う。その結果、自宅を作り始めてから数年の歳月が経過しているものの、まだ完成には漕ぎ着けていない。

PHOTO by KANJI FURUKAWA
案の定、2019年の開催は中止され、以降開催されることなく現在に至っている(2021年の「橋の下盆踊りンピック」など別の形では行われている)。愛樹くんはこう話す。
「料金を取れば来る人も絞れるじゃん。でも、間口を広げて『誰でも来てよ』とすると、すげえ大変で。話題になるほどおかしなのも来るしさ。フリーフェスの行き着くところが垣間見えた部分もあった。あの規模になったら下手をしたら人が死ぬからね。誰かが出鱈目な建物を建てて、それが崩れて人が死ぬことは全然ありえる。適当にやっているようで、みんな細かく見回ってたよね。この建て方は危ないでしょと注意したり。自由にできるぶん、責任も当然ある」
根木くんも続ける。
「2018年はピークを迎えた感じもあったよね。パンクしそうだった。俺たちも橋の下がどんどん大きくなることに違和感を感じていたし、『俺らがやりたいのはこういうものじゃないんだけどな』と思うこともあった」

PHOTO by KANJI FURUKAWA
橋の下に治志さんの作った櫓が突如出現した年のことは忘れられない。中心のなかった橋の下に中心ができた――そんな感覚を持ったものだった。
櫓の上ではたびたび奇跡的な場面が作り出された。遠藤ミチロウの橋の下最後のパフォーマンスもあの櫓の上で行われたし、郡上おどりの大ベテラン音頭取りである後藤直弘が櫓の上に立ったシーンも僕の脳裏に刻み込まれている。TURTLE ISLANDの盆踊り編成、亀島楽隊もあの櫓の上がホームだ。ただの建造物ではなく、作り手の思いが込められたものだからこそ、治志さんの作った櫓はカオティックなエネルギー渦巻く橋の下の中心となった。
「気持ちが入っちゃうんだよね、どうしても。音楽をやってる人たちは言葉やメロディーで表現してるように、こっちはものづくりを通して表現しているから」
櫓の上ではたびたび奇跡的な場面が作り出された。遠藤ミチロウの橋の下最後のパフォーマンスもあの櫓の上で行われたし、郡上おどりの大ベテラン音頭取りである後藤直弘が櫓の上に立ったシーンも僕の脳裏に刻み込まれている。TURTLE ISLANDの盆踊り編成、亀島楽隊もあの櫓の上がホームだ。ただの建造物ではなく、作り手の思いが込められたものだからこそ、治志さんの作った櫓はカオティックなエネルギー渦巻く橋の下の中心となった。
「気持ちが入っちゃうんだよね、どうしても。音楽をやってる人たちは言葉やメロディーで表現してるように、こっちはものづくりを通して表現しているから」

PHOTO by KANJI FURUKAWA
治志さんは「僕がめざしているのは無骨の美ということ」と語る。「無骨」という言葉を辞書で引くと、「洗練されていないこと、無作法なこと」と書いてある。大量生産の建売住宅を(多少の皮肉を込めて)「洗練」と呼ぶのであれば、効率を度外視した治志さんのものづくりはあきらかに真逆であって、無骨である。
「建築は骨組みが一番格好いい。その上にいろんなものを貼ってきれいにしちゃうもんで、そんなもんいらん。今の建築だったら10年経ったらいろいろ変えなくちゃいけなくなる」
愛樹くんは治志さんに「100年使える櫓を作ってくれ」というオーダーをしたらしい。10年経ったら修理が必要になる建売住宅とはまったく逆の発想だ。
橋の下に集う職人たちは、治志さんのように無骨の美を追求している連中ばかりである。効率を度外視し、自由にものをつくる。市場経済からもっとも遠いものづくりの現場がここにあった。
「建築は骨組みが一番格好いい。その上にいろんなものを貼ってきれいにしちゃうもんで、そんなもんいらん。今の建築だったら10年経ったらいろいろ変えなくちゃいけなくなる」
愛樹くんは治志さんに「100年使える櫓を作ってくれ」というオーダーをしたらしい。10年経ったら修理が必要になる建売住宅とはまったく逆の発想だ。
橋の下に集う職人たちは、治志さんのように無骨の美を追求している連中ばかりである。効率を度外視し、自由にものをつくる。市場経済からもっとも遠いものづくりの現場がここにあった。

橋の下世界音楽祭・火付ぬ組
2012年9月、愛知県豊田市で始まった音楽祭。豊田大橋の下に広がる広大なスペースを会場としており、ジャンルを超えたパフォーマーが登場するほか、さまざまなワークショップも行われる。運営チームには個性豊かな顔ぶれが揃っており、彼らは「火付(ひつけ)ぬ組」という集団を構成している。これまでの主な出演者は、TURTLE ISLAND、ハンガイ、マージナル、切腹ピストルズ、OKI DUB AINU BAND、大城美佐子、折坂悠太、THA BLUE HERB、阿波踊り太閤連、T字路s、遠藤ミチロウなど。2021年7月は東京オリンピックに合わせて「橋の下盆踊りンピック」が開催。こちらも大きな話題となった。
-

FORESTER
Shigeaki Adachi
-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER
Kei Amano
-

BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER
Taiki Minakuchi
-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭 火付ぬ組
-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN
Yukihito Kanai
-

SAUNA BUILDER
nodaklaxonbebe