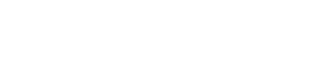Chapter 3 Vol.One
SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
Naoyuki Watanabe
渡辺尚幸
TEXT by SABU
PHOTOGRAPHS by KAZUMA ITO
PHOTOGRAPHS by KAZUMA ITO
241ファミリー、渡辺尚幸。
スノーシーズンの大半をスノーボーディングに費やし、オフシーズンには信州産の間伐材を自らの手で組み上げ、それを芯材としたスノーボードを製作する活動を現在も続けている。正真正銘のクリエイティビスト。そのバイタリティと溢れ出る創造力は、どこから湧いてくるのか? インディマガジン『未知の駅』発行人・さぶが、その謎に迫った。
スノーシーズンの大半をスノーボーディングに費やし、オフシーズンには信州産の間伐材を自らの手で組み上げ、それを芯材としたスノーボードを製作する活動を現在も続けている。正真正銘のクリエイティビスト。そのバイタリティと溢れ出る創造力は、どこから湧いてくるのか? インディマガジン『未知の駅』発行人・さぶが、その謎に迫った。
取材を通じて"何か"を受け取る
今から10年前。
『未知の駅』という名のZINE(自費出版本)を出版した。
2011年3月11日の東日本大震災と原発事故を機に、自分たちの暮らしのあり方を考え直してみよう、という趣旨の本だ。
テーマは「もう1つの暮らし方」。
これまで取材を通じて、いろいろな人たちと出会ってきた。
たとえば東京から熊本県南阿蘇村へ移住し、大手電力会社に頼らず電気や食べものを自給しながら暮らすパーマカルチャー農家さん。
確実に量産できるイースト菌ではなく、うまく発酵するかもわからない天然酵母でパン作りを行うパン屋さん。
鳥取の田舎町に移住してきて「土地なし・金なし・コネなし」の状況から、セルフビルドで小屋を建てて開業した本屋さん、などなど……。
2択あるとすれば〈あえて難しい方〉を選んでしまうモノズキな人たち、あるいは、そうならざるを得なかった人たち、と言ってみてもいいかもしれない。
生きていく上で、彼らが大事にしているものとは、いったいなんなのか。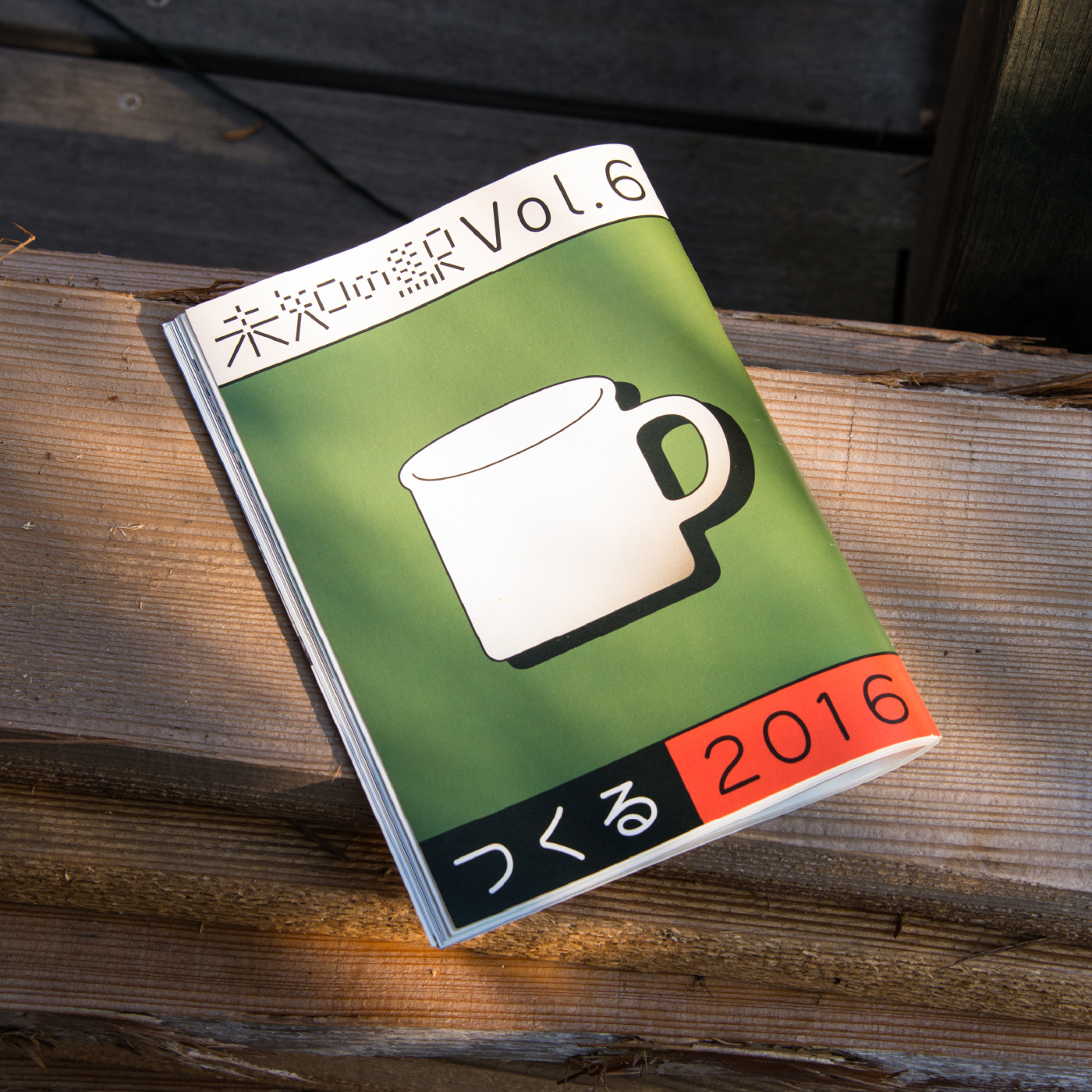 取材をしていると「不思議な現象」が起こることがある。
取材をしていると「不思議な現象」が起こることがある。
それは、最初は他人事のように見ていた物事が、だんだんそう見えなくなってくる、というものだ。
まるで「あなたのために用意しておいた話なんだよ」と言われているようである。
取材とは話を聞きたい人に会いに行く活動のことだが、その人物と会うことが実は前から決まっていたのではないか。
ふと、そんな錯覚をおぼえることがある。
そういう意味で言うと、自分がZINEの出版を始めたのも、この人に会うためだったのかもしれないと思わせる人物がいる。
まさに「もう1つの暮らし方」を、人生を賭けて体現してきたような、先生のような存在だ。
それが「ナベさん」こと、渡辺尚幸さんである。
今から10年前。
『未知の駅』という名のZINE(自費出版本)を出版した。
2011年3月11日の東日本大震災と原発事故を機に、自分たちの暮らしのあり方を考え直してみよう、という趣旨の本だ。
テーマは「もう1つの暮らし方」。
これまで取材を通じて、いろいろな人たちと出会ってきた。
たとえば東京から熊本県南阿蘇村へ移住し、大手電力会社に頼らず電気や食べものを自給しながら暮らすパーマカルチャー農家さん。
確実に量産できるイースト菌ではなく、うまく発酵するかもわからない天然酵母でパン作りを行うパン屋さん。
鳥取の田舎町に移住してきて「土地なし・金なし・コネなし」の状況から、セルフビルドで小屋を建てて開業した本屋さん、などなど……。
2択あるとすれば〈あえて難しい方〉を選んでしまうモノズキな人たち、あるいは、そうならざるを得なかった人たち、と言ってみてもいいかもしれない。
生きていく上で、彼らが大事にしているものとは、いったいなんなのか。
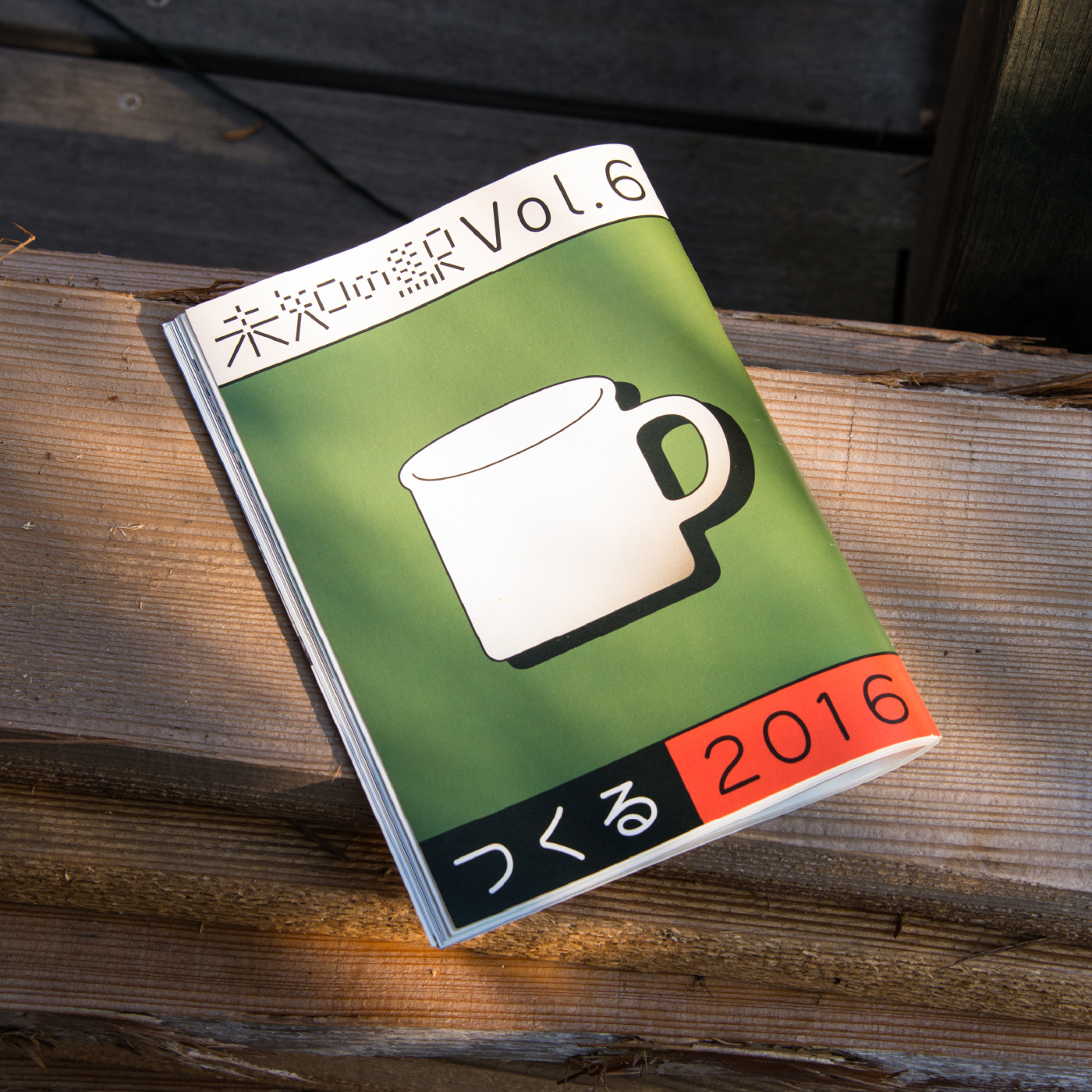
それは、最初は他人事のように見ていた物事が、だんだんそう見えなくなってくる、というものだ。
まるで「あなたのために用意しておいた話なんだよ」と言われているようである。
取材とは話を聞きたい人に会いに行く活動のことだが、その人物と会うことが実は前から決まっていたのではないか。
ふと、そんな錯覚をおぼえることがある。
そういう意味で言うと、自分がZINEの出版を始めたのも、この人に会うためだったのかもしれないと思わせる人物がいる。
まさに「もう1つの暮らし方」を、人生を賭けて体現してきたような、先生のような存在だ。
それが「ナベさん」こと、渡辺尚幸さんである。

どうも山が滑りにくい
「Green Lab.」(グリーンラボ)という、長野県を拠点とするスノーボード・プロジェクトの存在を知ったのは、2012年2月のことだった。
前述した『未知の駅』の創刊号に友人の山本敦久さんが寄稿してくれた「Critical Ridingーーヴァナキュラー横乗り文化論(長野編)」という記事を読んだのがキッカケである。
曰く、長野県の山間部(菅平高原・峰の原)を拠点に、夏場は農業や牧畜を営み、冬になると雪山の奥地や断崖絶壁の斜面に出かけて行ってスノーボードで遊ぶ、という暮らしをしている人たちがいるというのだ。
彼らが使うスノーボードは、長野県産のカラマツやヒノキの間伐材を使用したもので、自分たちの手によってつくり出されたハンドメイド品である。
間伐材を使って自分たちでスノーボードをつくるようになったのは、「どうも山が滑りにくい」という違和感を覚えたことがキッカケだった。
どういうことか。
山本さんの記事を一部、引用しよう。
「福島の原発事故を経て今では誰の目にも明らかになったことだが、意図的にエネルギー生産を原発に頼ってきた戦後の日本において林業は衰退の一途を辿っていた。戦後の植林政策は、戦時期にエネルギー源として使い果たした山林の木材を再供給するために膨大な規模で植林を進めた。しかし、やがて主要エネルギーのシフトや安価な輸入材等によって、コスト高となり、結局、間伐が立ち遅れ、手つかずとなり、荒廃した山林を生み出し続けた。こうした山林の荒廃状況をいち早く掴んだのがスノーボーダーたちであったという点は興味深い」(『未知の駅 Vol.1』, 「Critical Ridingーーヴァナキュラー横乗り文化論(長野編)」より抜粋)
スキー場のゲレンデよりも自然の山の斜面を滑ることを好む彼らにとって、植林された木々が伐採されないままで密集している環境は、スノーボードで滑降するのに適した状況とは言えず、そうした山が「滑りにくい」ということになる。
「Green Lab.」(グリーンラボ)という、長野県を拠点とするスノーボード・プロジェクトの存在を知ったのは、2012年2月のことだった。
前述した『未知の駅』の創刊号に友人の山本敦久さんが寄稿してくれた「Critical Ridingーーヴァナキュラー横乗り文化論(長野編)」という記事を読んだのがキッカケである。
曰く、長野県の山間部(菅平高原・峰の原)を拠点に、夏場は農業や牧畜を営み、冬になると雪山の奥地や断崖絶壁の斜面に出かけて行ってスノーボードで遊ぶ、という暮らしをしている人たちがいるというのだ。
彼らが使うスノーボードは、長野県産のカラマツやヒノキの間伐材を使用したもので、自分たちの手によってつくり出されたハンドメイド品である。
間伐材を使って自分たちでスノーボードをつくるようになったのは、「どうも山が滑りにくい」という違和感を覚えたことがキッカケだった。
どういうことか。
山本さんの記事を一部、引用しよう。
「福島の原発事故を経て今では誰の目にも明らかになったことだが、意図的にエネルギー生産を原発に頼ってきた戦後の日本において林業は衰退の一途を辿っていた。戦後の植林政策は、戦時期にエネルギー源として使い果たした山林の木材を再供給するために膨大な規模で植林を進めた。しかし、やがて主要エネルギーのシフトや安価な輸入材等によって、コスト高となり、結局、間伐が立ち遅れ、手つかずとなり、荒廃した山林を生み出し続けた。こうした山林の荒廃状況をいち早く掴んだのがスノーボーダーたちであったという点は興味深い」(『未知の駅 Vol.1』, 「Critical Ridingーーヴァナキュラー横乗り文化論(長野編)」より抜粋)
スキー場のゲレンデよりも自然の山の斜面を滑ることを好む彼らにとって、植林された木々が伐採されないままで密集している環境は、スノーボードで滑降するのに適した状況とは言えず、そうした山が「滑りにくい」ということになる。

国の植林政策によって自分たちの遊び場である山が荒廃している。
彼らはそのことを〈遊び〉を通じて気づいたのであった。
「だったら、自分たちの遊び場を守っていくために、何かやれることを考えてみてもいいんじゃないか」
そうして立ち上がったのが、中山二郎さん、中山一郎さん、そして「ナベさん」こと渡辺尚幸さんの3人だった。
プロジェクト名は「Green Lab.」と名付けられた。2004年のことである。
記事のインタビューの中で、ナベさんは、このように語っている。
「信州の山は全体の六割が針葉樹。成長の早いスギやカラマツなんだ。いま樹齢が40年から50年くらいか。植林したのはいいけど、日本の森林は利用価値が少ない木材ばかりになっちゃったわけ。植林され成長した針葉樹は、ほんとはいま使い時が来ているのに、使い道がない。だから間伐材を使ってスノーボードを作れないかって考えたわけさ」 Green Lab.では、スノーボードの要ともいえる「ウッドコア」(芯材)の製作を行っている。
Green Lab.では、スノーボードの要ともいえる「ウッドコア」(芯材)の製作を行っている。
簡単に言うと、乾燥させたカラマツやヒノキの間伐材を3cm×1.5cmの細長い角材に加工し、それらを繋ぎ合わせて、1枚の板(集成材)に仕上げる。
それが工場に届けられ、自分たちのデザインしたグラフィックがプレスされた状態で、スノーボードとなって返ってくる。
Green Lab.では年間約200本のスノーボードを生産している。
それらは活動に共感・賛同して購入してくれた人たちの手元へと届けられる。
人と自然とモノとが、スノーボードという〈遊び〉を通じて一本の軸で繋がる。
そのネットワークを彼らは「コア繋がり」と呼んでいる。
ナベさんは言う。
「この板を購入して実際にゲレンデで使うということが、エコロジーや持続可能性を考えてるっていう付加価値になる。そういうネットワークができる。グローバル企業みたいなブランドとは違うブランドになる。これってさあ、大量消費とか資本主義とは違った価値を打ち出せるんじゃないかな」
思っていたよりも奥の深い世界のように思えた。
彼らはそのことを〈遊び〉を通じて気づいたのであった。
「だったら、自分たちの遊び場を守っていくために、何かやれることを考えてみてもいいんじゃないか」
そうして立ち上がったのが、中山二郎さん、中山一郎さん、そして「ナベさん」こと渡辺尚幸さんの3人だった。
プロジェクト名は「Green Lab.」と名付けられた。2004年のことである。
記事のインタビューの中で、ナベさんは、このように語っている。
「信州の山は全体の六割が針葉樹。成長の早いスギやカラマツなんだ。いま樹齢が40年から50年くらいか。植林したのはいいけど、日本の森林は利用価値が少ない木材ばかりになっちゃったわけ。植林され成長した針葉樹は、ほんとはいま使い時が来ているのに、使い道がない。だから間伐材を使ってスノーボードを作れないかって考えたわけさ」

簡単に言うと、乾燥させたカラマツやヒノキの間伐材を3cm×1.5cmの細長い角材に加工し、それらを繋ぎ合わせて、1枚の板(集成材)に仕上げる。
それが工場に届けられ、自分たちのデザインしたグラフィックがプレスされた状態で、スノーボードとなって返ってくる。
Green Lab.では年間約200本のスノーボードを生産している。
それらは活動に共感・賛同して購入してくれた人たちの手元へと届けられる。
人と自然とモノとが、スノーボードという〈遊び〉を通じて一本の軸で繋がる。
そのネットワークを彼らは「コア繋がり」と呼んでいる。
ナベさんは言う。
「この板を購入して実際にゲレンデで使うということが、エコロジーや持続可能性を考えてるっていう付加価値になる。そういうネットワークができる。グローバル企業みたいなブランドとは違うブランドになる。これってさあ、大量消費とか資本主義とは違った価値を打ち出せるんじゃないかな」
思っていたよりも奥の深い世界のように思えた。

長野へ遊びに行く
記事を通じてこのプロジェクトを知った僕は、その後、年に1回のペースでGreen Lab.のメンバーたちに会いに、東京から長野へ遊びに行くようになった。
寄稿者である山本さんや何人かの身近な仲間たちと一緒に行くのが、いつものパターンだ。
といってもスノーボードができるわけでもなければ、山の断崖絶壁まで行くといった技術を僕たちが持ち合わせているわけではない。
〈遊び〉といっても、彼らがやっているのは「エクストリームスポーツ」と呼ばれる命がけの競技であり、いわば彼らはアスリートである。
迂闊に付いては行けない。
では何をしていたのかというと、彼らの畑で一緒に美味しい野菜を収穫したり、Green lab.メンバーの伊藤高さんの実家が経営する「ダボス牧場」で健康な牛を育てる様子を見学したり、中山二郎さんの母・一美さんの営むペンション「ふくなが」に泊まって、そうした食材からつくられる一美さんの美味しい料理をいただいたりして、みんなでワイワイと過ごしていた。
食卓にはレッドフリルレタスや「仙人ニンニク」といった聞いたこともない無農薬野菜、それに健康に育てられた牛の赤身のお肉や、羊のホゲット(ラムとマトンの間の珍しい肉)といった「内容の濃い」料理が並んだ。
「なるほど、"美味しい"ってこういうもののことを言うのか!」
消費者側にしてみれば「無農薬」や「オーガニック」といったワードは、なるほどたしかに魅力的に見える。
しかし農薬や除草剤、あるいはホルモン剤や抗生物質を使用しないということは、それだけ生産にかかる手間も時間もコストもかかるということを意味する。
病気や害虫が発生していないか、四六時中、気にし続けなければならないという心の負担もある。
資本主義の理屈から言えば、それは明らかに非合理的・非生産的である。
それでも、彼らがそんな選択をし続けるのは、なぜなのか。
その理由を日々あれこれ考えながら生活していたら、以前よりもちょっぴり自分の感覚が冴えているような"変化"に、ふと気づく場面が増えていった。
たとえば食材を買う時、外食する時、家で料理する時などである。
あらゆる選択肢の中から、何をどうするのがいいのか、自分の感覚に一度お伺いを立ててから決めるようになっていたのだ。
この時、長野で知った「ちゃんとした食べものの味」が、自分の中の1つの判断基準になっていた。
 ドはド、レはレと聞き分ける「絶対音感」が存在するように、旨いものは旨い、変なものは変と利き分ける「絶対味感」とも言えるような感覚もまた、ひょっとすると、体のどこかに眠っているのかもしれない。
ドはド、レはレと聞き分ける「絶対音感」が存在するように、旨いものは旨い、変なものは変と利き分ける「絶対味感」とも言えるような感覚もまた、ひょっとすると、体のどこかに眠っているのかもしれない。
何回か長野に通う内にわかってきたのは、彼らのエコロジーに対する意識が、何もスノーボードに限ったものではないということだった。
遊ぶことも、育てることも、食べることも、買うことも、捨てることも、呼吸することも、全て地続きに繋がっている。
「こういう生き方や考え方があったのか」
大学卒業後、「社会人」とは別の意味で人生の新しいステージに一歩足を踏み入れたような気がした。
Green Lab.の活動はまさにZINEのテーマである「もう1つの暮らし方」に対する、具体的かつ明快な1つの答え方であった。
で、いったい何者なんだ?!
肝心の「ナベさん」である。
当時は「長野に遊びに行く」というと、だいたい中山二郎さんに会いに行くことの方が多く、ナベさんはというと「謎の人物」という印象だった。
記事を通じてこのプロジェクトを知った僕は、その後、年に1回のペースでGreen Lab.のメンバーたちに会いに、東京から長野へ遊びに行くようになった。
寄稿者である山本さんや何人かの身近な仲間たちと一緒に行くのが、いつものパターンだ。
といってもスノーボードができるわけでもなければ、山の断崖絶壁まで行くといった技術を僕たちが持ち合わせているわけではない。
〈遊び〉といっても、彼らがやっているのは「エクストリームスポーツ」と呼ばれる命がけの競技であり、いわば彼らはアスリートである。
迂闊に付いては行けない。
では何をしていたのかというと、彼らの畑で一緒に美味しい野菜を収穫したり、Green lab.メンバーの伊藤高さんの実家が経営する「ダボス牧場」で健康な牛を育てる様子を見学したり、中山二郎さんの母・一美さんの営むペンション「ふくなが」に泊まって、そうした食材からつくられる一美さんの美味しい料理をいただいたりして、みんなでワイワイと過ごしていた。
食卓にはレッドフリルレタスや「仙人ニンニク」といった聞いたこともない無農薬野菜、それに健康に育てられた牛の赤身のお肉や、羊のホゲット(ラムとマトンの間の珍しい肉)といった「内容の濃い」料理が並んだ。
「なるほど、"美味しい"ってこういうもののことを言うのか!」
消費者側にしてみれば「無農薬」や「オーガニック」といったワードは、なるほどたしかに魅力的に見える。
しかし農薬や除草剤、あるいはホルモン剤や抗生物質を使用しないということは、それだけ生産にかかる手間も時間もコストもかかるということを意味する。
病気や害虫が発生していないか、四六時中、気にし続けなければならないという心の負担もある。
資本主義の理屈から言えば、それは明らかに非合理的・非生産的である。
それでも、彼らがそんな選択をし続けるのは、なぜなのか。
その理由を日々あれこれ考えながら生活していたら、以前よりもちょっぴり自分の感覚が冴えているような"変化"に、ふと気づく場面が増えていった。
たとえば食材を買う時、外食する時、家で料理する時などである。
あらゆる選択肢の中から、何をどうするのがいいのか、自分の感覚に一度お伺いを立ててから決めるようになっていたのだ。
この時、長野で知った「ちゃんとした食べものの味」が、自分の中の1つの判断基準になっていた。

何回か長野に通う内にわかってきたのは、彼らのエコロジーに対する意識が、何もスノーボードに限ったものではないということだった。
遊ぶことも、育てることも、食べることも、買うことも、捨てることも、呼吸することも、全て地続きに繋がっている。
「こういう生き方や考え方があったのか」
大学卒業後、「社会人」とは別の意味で人生の新しいステージに一歩足を踏み入れたような気がした。
Green Lab.の活動はまさにZINEのテーマである「もう1つの暮らし方」に対する、具体的かつ明快な1つの答え方であった。
で、いったい何者なんだ?!
肝心の「ナベさん」である。
当時は「長野に遊びに行く」というと、だいたい中山二郎さんに会いに行くことの方が多く、ナベさんはというと「謎の人物」という印象だった。

見た目は、痩せこけた頬に、白髪混じりのヒゲを生やして、年齢不詳。
メディアや表舞台にはほとんど出てこない。
イマドキの若者っぽい服装や喋り方をしていて、お気に入りのサングラスをいくつか持っている。
肩の力の抜けた穏やかな人柄で、チャーミングで、ちょっぴりファンキー。
こういうのも何だけれど、イメージとしては鳥山明の漫画『ドラゴンボール』に出てくる「亀仙人」に近い。
Green Lab.の発案者でありブレーンであるナベさんが、みんなから一目置かれる存在だということはなんとなく察していたのだが、その理由はよくわからなかった。
いったい、どんな人なんだろう。
気になる。
新潟県妙高市の実家を訪れる
時は過ぎ、2015年6月1日。
初夏の気持ちのいい、晴れの日。
僕はナベさんと2人、河原で昼間からビールを飲みながらバーベキューをしていた。
ナベさんがGreen Lab.と併行して「PRANA PUNKS」(プラーナ・パンクス)という姉妹ブランドを新たに立ち上げたのは2014年10月のことだった。
6号目の『未知の駅』で「つくる」という特集を組むことにした僕はちょうどいい機会だと思って、ずっと気になっていたナベさんの話を聞くべく、アポをとって、ひとりで取材しに来たのだった。
普段は長野市の自宅に住むナベさんだが、この時はナベさんの実家である新潟県妙高市新井町の一軒家にお邪魔させていただいた。
「ナベさん、久しぶりっす!」
「おい~っす! さぶちゃん、バーベキューでもやろうぜ~」
そう言って、ナベさんはガレージからバーベキューセットを引っ張り出してきて、用意しておいた肉を手際よく焼いて食べさせてくれたのだった。
メディアや表舞台にはほとんど出てこない。
イマドキの若者っぽい服装や喋り方をしていて、お気に入りのサングラスをいくつか持っている。
肩の力の抜けた穏やかな人柄で、チャーミングで、ちょっぴりファンキー。
こういうのも何だけれど、イメージとしては鳥山明の漫画『ドラゴンボール』に出てくる「亀仙人」に近い。
Green Lab.の発案者でありブレーンであるナベさんが、みんなから一目置かれる存在だということはなんとなく察していたのだが、その理由はよくわからなかった。
いったい、どんな人なんだろう。
気になる。
新潟県妙高市の実家を訪れる
時は過ぎ、2015年6月1日。
初夏の気持ちのいい、晴れの日。
僕はナベさんと2人、河原で昼間からビールを飲みながらバーベキューをしていた。
ナベさんがGreen Lab.と併行して「PRANA PUNKS」(プラーナ・パンクス)という姉妹ブランドを新たに立ち上げたのは2014年10月のことだった。
6号目の『未知の駅』で「つくる」という特集を組むことにした僕はちょうどいい機会だと思って、ずっと気になっていたナベさんの話を聞くべく、アポをとって、ひとりで取材しに来たのだった。
普段は長野市の自宅に住むナベさんだが、この時はナベさんの実家である新潟県妙高市新井町の一軒家にお邪魔させていただいた。
「ナベさん、久しぶりっす!」
「おい~っす! さぶちゃん、バーベキューでもやろうぜ~」
そう言って、ナベさんはガレージからバーベキューセットを引っ張り出してきて、用意しておいた肉を手際よく焼いて食べさせてくれたのだった。

ガレージには、木製の四角い箱型の打楽器「カホン」が5つも6つも置いてあり、家の中にはギターが少なくとも10本以上は置いてあった。
ナベさんはGreen Lab.のメンバーたちと一緒に「Fighting Farmers」というバンドをやっていて、アメリカツアーをしたこともあるそうだ。
なぜこんなにもたくさんのカホンやギターを持っているのだろう。
「スノーボードの人」というイメージが強かったので疑問に思った。
家の畳の大広間には立派な仏壇があり、その手前には額縁に入ったモノクロの写真が置いてあった。
そこには軍服を着た人の顔が写っていた。
小さい頃、九州の田舎のおばあちゃんの家でよく見た仏壇と似たような匂いがした。
実家というけれども、他に誰かが住んでいる気配はない。
どうやらナベさんがひとりでこの家と、近所にある田んぼを管理しているらしい。
詳しくは次回以降で後述するが、このあたりの謎が明らかにされるのは、ここからさらに6年後のことである。
ナベさんはGreen Lab.のメンバーたちと一緒に「Fighting Farmers」というバンドをやっていて、アメリカツアーをしたこともあるそうだ。
なぜこんなにもたくさんのカホンやギターを持っているのだろう。
「スノーボードの人」というイメージが強かったので疑問に思った。
家の畳の大広間には立派な仏壇があり、その手前には額縁に入ったモノクロの写真が置いてあった。
そこには軍服を着た人の顔が写っていた。
小さい頃、九州の田舎のおばあちゃんの家でよく見た仏壇と似たような匂いがした。
実家というけれども、他に誰かが住んでいる気配はない。
どうやらナベさんがひとりでこの家と、近所にある田んぼを管理しているらしい。
詳しくは次回以降で後述するが、このあたりの謎が明らかにされるのは、ここからさらに6年後のことである。

渡辺尚幸/スノーボードブランド〈PRANA PUNKS〉代表。デザイナー。アートディレクター。スノーボーダー(241所属)。
1958年、新潟県新井市生まれ。ロッククライマー、ラリードライバー、山岳ガイド、プロスノーボーダーなどの活動を経て、2004年、信州産の間伐材を芯材に使ったスノーボードのブランド〈Green Lab.〉を、中山一郎、中山二郎らと設立。グラフィックとディレクションを担当し、2015年、個人ブランド〈PRANA PUNKS SNOWBOARDING〉を設立。自らが作詞作曲を手がけるフォーク・ロックバンド「Fighting Farmers」ではヴォーカルとギターを担当。
-

FORESTER
Shigeaki Adachi
-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER
Kei Amano
-

BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER
Taiki Minakuchi
-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭 火付ぬ組
-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN
Yukihito Kanai
-

SAUNA BUILDER
nodaklaxonbebe