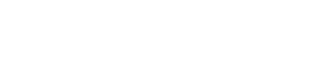Chapter 3 Vol.Four
SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
Naoyuki Watanabe
渡辺尚幸
TEXT by SABU
PHOTOGRAPHS by KAZUMA ITO, YOSHIRO HIGAI (Riding)
PHOTOGRAPHS by KAZUMA ITO, YOSHIRO HIGAI (Riding)
大量に生産して、大量に売ること。ものづくりに求められる条件は、それだけではない。効率が求められる時代だからこそ必要とされる真っ当なモノづくりとは?
手作りの価値にこだわり続けてきた男が明かす、クリエイティブの真髄。
木工作家になる
クライミングを続けるために月の半分はアルバイト、残りの半分をクライミングに費やす日々を送ってきたナベさんだったが、「そろそろ手に職をつけたほうがいい」「自分で稼げる人になろう」と思い、上田市から長野市へやって来る。
田んぼに囲まれた古民家を改装した、木工製作の工房を訪れたのは22歳の時である。
「こんにちは~、渡辺です。山登りやってまーす。ここで使ってもらえませんか?」
クライミングを続けるために月の半分はアルバイト、残りの半分をクライミングに費やす日々を送ってきたナベさんだったが、「そろそろ手に職をつけたほうがいい」「自分で稼げる人になろう」と思い、上田市から長野市へやって来る。
田んぼに囲まれた古民家を改装した、木工製作の工房を訪れたのは22歳の時である。
「こんにちは~、渡辺です。山登りやってまーす。ここで使ってもらえませんか?」

ナベさんが門を叩いたのは、カラマツで時計をつくっている「キコリ・デザイン研究所」だった。
当時、長野県の植林政策で植えられたカラマツはヤニや節が多い上、乾燥による割れや狂いも生じやすく、使い道といえば電信柱くらいのものであった。
そこで「キコリ」は、長野県内の林務課、工業試験場、信州大学などと連携しながら脱脂乾燥の技術を確立させ、カラマツの使い道をいろいろと模索していった。
当時の所長だった古川正礼さんは、千葉工業大学を卒業後、自動車メーカーの東洋工業(マツダの旧社名)の広島本社に勤務。
初代マツダ・キャロルのインストルメントパネル(運転席の正面に設置されているスピードメーターなどの計器類)のデザインを手掛けた工業デザイナーであり、JIDA(Japan Industrial Design Association/日本インダストリアルデザイナー協会)の正会員でもあった。
「当時の俺にしてみりゃ、うわ、すっげー!! そんなすげぇ仕事してるなんて、超かっけー!! って感じだった」
ナベさんはクライミングを続けながら、古川さんの下で工業デザインの基礎を学び、木工作家としての道を歩むようになる。
木は木であって!
徐々に仕事を覚えてきたナベさんは、ある時、鬼無里村の森林組合で使われなくなった広葉樹のブナに目をつける。
「これ、何かに使えないかな」と工房に持ち帰り、オモチャの作品をつくってみたところ、それが県内のとあるコンテストで賞を獲った。
当時、長野県の植林政策で植えられたカラマツはヤニや節が多い上、乾燥による割れや狂いも生じやすく、使い道といえば電信柱くらいのものであった。
そこで「キコリ」は、長野県内の林務課、工業試験場、信州大学などと連携しながら脱脂乾燥の技術を確立させ、カラマツの使い道をいろいろと模索していった。
当時の所長だった古川正礼さんは、千葉工業大学を卒業後、自動車メーカーの東洋工業(マツダの旧社名)の広島本社に勤務。
初代マツダ・キャロルのインストルメントパネル(運転席の正面に設置されているスピードメーターなどの計器類)のデザインを手掛けた工業デザイナーであり、JIDA(Japan Industrial Design Association/日本インダストリアルデザイナー協会)の正会員でもあった。
「当時の俺にしてみりゃ、うわ、すっげー!! そんなすげぇ仕事してるなんて、超かっけー!! って感じだった」
ナベさんはクライミングを続けながら、古川さんの下で工業デザインの基礎を学び、木工作家としての道を歩むようになる。
木は木であって!
徐々に仕事を覚えてきたナベさんは、ある時、鬼無里村の森林組合で使われなくなった広葉樹のブナに目をつける。
「これ、何かに使えないかな」と工房に持ち帰り、オモチャの作品をつくってみたところ、それが県内のとあるコンテストで賞を獲った。

日本大学芸術学部の、ある有名な先生からは、
「渡辺くんの作品のいいところは、普通、この木の節は使いにくいから取っちゃうんだけど、取らないでそのままデザインに溶け込ませたところ。そこが凄い」
と言って褒められた。
当時、山と溪谷社から出ていた雑誌『WOODY LIFE』には木工作家・渡辺尚幸としての作品が紹介されている。
「手に職をつけることができればいい」と考えていたので、作家として食えるようになってきたナベさんは入社後3年で退職。
しかし、その後も「キコリ」との関係性は続いていく。
ほとんどスタッフが入れ替わった今でも「こんちわー!」と言って工房に出入りして、PRANA PUNKSのスノーボードの来季試作品やカホンなど、いろいろなものをつくっている。
実は新井町の実家のガレージで見かけたあのカホンも、ナベさんがそこで自分の手で製作したものだったのだ。
たくさん置いてあった楽器の謎が少しずつ解けていった。
「キコリには、俺はずーっとお世話になってんの。最近はまた新しく、木を使ったテーブルとか椅子とかさ、そういう家具を作ってみたいと思ってる。そんなに高級なものじゃなくていいから。節があったり、皮があったり、ちょっと歪んだりしてるけど、そういう"木を感じられるスツール"みたいな(笑)。木は木であって! って感じ。ギターもつくってみたいんだけどね」
話を聴いていくうちに、僕の中の「スノーボードの人」という印象は、もう一歩引いた「木の人」に変わっていった。
ナベさん自身は「俺は山屋さんだから」と言っていた。 グルのような存在だった
グルのような存在だった
最初のうちは木工作家として食えていたが、それだけでは厳しいと感じたナベさんはその後、デザイン事務所で広告ディレクターのアシスタントとして働き始める。
長野のブティックを紹介する情報マガジン、観光土産のキャラクター、出版社で使う釣りや旅などのアウトドア系のイラスト、さらに当時はテレフォンカード全盛の時代でテレフォンカードのデザインなども手掛けていった。
事務所は長野市善光寺南西にある妻科神社の近所で、古い土蔵をリノベーションした趣のある建物だった。
事務所の主は、原山尚久さん。
原山さんは、栗菓子の「小布施堂」、おやきの「いろは堂」、七味唐辛子の「八幡屋礒五郎」、ワインの「サンクゼール」に鉄道事業者の「長野電鉄」といった、誰でも知っているような有名企業の顧問デザイナーとしてブランディングを手掛けていった、凄腕のアートディレクターであり、またアーティストでもあった。
地元ではかなり有名な人で、ナベさんも原山さんのことは昔から知っていたという。
ナベさんは20代前半の頃、長野市内にあった「仏陀」という伝説のライブハウスに出入りしていて、その時に原山さんとよく顔を合わせていた。
ちなみにその当時、舞台に立って歌っていたのが、ナベさんの音楽活動に多大な影響を与え、後に一緒に全国でライブ活動をして回ることとなるフォークシンガー「ナミさん」こと、南正人さんである。
「俺にとっては先輩、というよりも先生。もはやグル(聖者)のような存在。最初はライブの後なんか怖くて声かけられないのよ、2人ともすごい形相だから(笑)。原山さんは坊主に金縁眼鏡。ナミさんは髪を長く伸ばしてて。俺たちの中ではもう超有名で、超凄い人だった。原山さんのデザインに対する考え方なんか本当に全部その通りだなって思ったし、ナミさんのライブの時のエネルギー、駆動力なんかは凄まじかったね」
この2人との出会いから、ナベさんは生き方を教わっていった。
「渡辺くんの作品のいいところは、普通、この木の節は使いにくいから取っちゃうんだけど、取らないでそのままデザインに溶け込ませたところ。そこが凄い」
と言って褒められた。
当時、山と溪谷社から出ていた雑誌『WOODY LIFE』には木工作家・渡辺尚幸としての作品が紹介されている。
「手に職をつけることができればいい」と考えていたので、作家として食えるようになってきたナベさんは入社後3年で退職。
しかし、その後も「キコリ」との関係性は続いていく。
ほとんどスタッフが入れ替わった今でも「こんちわー!」と言って工房に出入りして、PRANA PUNKSのスノーボードの来季試作品やカホンなど、いろいろなものをつくっている。
実は新井町の実家のガレージで見かけたあのカホンも、ナベさんがそこで自分の手で製作したものだったのだ。
たくさん置いてあった楽器の謎が少しずつ解けていった。
「キコリには、俺はずーっとお世話になってんの。最近はまた新しく、木を使ったテーブルとか椅子とかさ、そういう家具を作ってみたいと思ってる。そんなに高級なものじゃなくていいから。節があったり、皮があったり、ちょっと歪んだりしてるけど、そういう"木を感じられるスツール"みたいな(笑)。木は木であって! って感じ。ギターもつくってみたいんだけどね」
話を聴いていくうちに、僕の中の「スノーボードの人」という印象は、もう一歩引いた「木の人」に変わっていった。
ナベさん自身は「俺は山屋さんだから」と言っていた。

最初のうちは木工作家として食えていたが、それだけでは厳しいと感じたナベさんはその後、デザイン事務所で広告ディレクターのアシスタントとして働き始める。
長野のブティックを紹介する情報マガジン、観光土産のキャラクター、出版社で使う釣りや旅などのアウトドア系のイラスト、さらに当時はテレフォンカード全盛の時代でテレフォンカードのデザインなども手掛けていった。
事務所は長野市善光寺南西にある妻科神社の近所で、古い土蔵をリノベーションした趣のある建物だった。
事務所の主は、原山尚久さん。
原山さんは、栗菓子の「小布施堂」、おやきの「いろは堂」、七味唐辛子の「八幡屋礒五郎」、ワインの「サンクゼール」に鉄道事業者の「長野電鉄」といった、誰でも知っているような有名企業の顧問デザイナーとしてブランディングを手掛けていった、凄腕のアートディレクターであり、またアーティストでもあった。
地元ではかなり有名な人で、ナベさんも原山さんのことは昔から知っていたという。
ナベさんは20代前半の頃、長野市内にあった「仏陀」という伝説のライブハウスに出入りしていて、その時に原山さんとよく顔を合わせていた。
ちなみにその当時、舞台に立って歌っていたのが、ナベさんの音楽活動に多大な影響を与え、後に一緒に全国でライブ活動をして回ることとなるフォークシンガー「ナミさん」こと、南正人さんである。
「俺にとっては先輩、というよりも先生。もはやグル(聖者)のような存在。最初はライブの後なんか怖くて声かけられないのよ、2人ともすごい形相だから(笑)。原山さんは坊主に金縁眼鏡。ナミさんは髪を長く伸ばしてて。俺たちの中ではもう超有名で、超凄い人だった。原山さんのデザインに対する考え方なんか本当に全部その通りだなって思ったし、ナミさんのライブの時のエネルギー、駆動力なんかは凄まじかったね」
この2人との出会いから、ナベさんは生き方を教わっていった。

モノづくりは寄り添うこと
面白いことに、原山さんは「ほとんど仕事をしない人だった」という。
正確に言えば仕事をしないわけではないのだが、どちらかというと経営者たちの相談話をよく聞いていた。
つまり、みんなの相談役である。
それも「うちの息子がこうでこうで、先生どうしたらいいんですかね」といった身の上話のように、仕事と直接的には関係のない話ばかりだった。
困っている人の面倒を見ること、お世話をすること。
人の声に耳を傾けること、寄り添うこと。
温度感のあるやりとりがあること。
それらが原山さんの大切にしていたことだった。
ナベさんは原山さんの姿を見ながら、つくる側と客の関係性や「寄り添うモノづくり」というテーマを見出していった。
そんな折、長野県小布施町にある栗菓子の老舗店「小布施堂」の当時の副社長・市村良三さん(後の小布施町の町長)から「ナベちゃん、スノーボードつくってみない?」という声がかかる。
当時、県内で最も面積の小さな小布施町は過疎化の一途を辿っており、市村さんは、このままだと10年後には高齢者の観光客しかやって来ない町になってしまう、と危惧していた。
短期間で得られる目先の利益に飛びつくのではなくて、もっと時間をかけ、10年後の未来を見据えた長期的なまちづくりを行っていかなければならない。
そして、そこには若い子たちも絶対に必要である、と考えた。
そうしてナベさんが「将来にコンタクトできるための板」としてつくったのが、現在の小布施堂の店内の壁に飾ってある赤と黒の、葛飾北斎の絵が描かれたスノーボードである。
1996~2000年くらいまで、5年ほどつくっていたという。
小布施町はその後、個人宅の庭を一般開放する「おぶせオープンガーデン」、スケートボードやスラックラインのパーク(練習場)、古い公園を再利用したスケートボード施設、全国から35歳以下の若者を集め地域の未来を話し合う2泊3日の「小布施若者会議」など、ユニークな試みを次々と展開していく。
今や小布施町は年間120万人の観光客が訪れる「栗と北斎の町」である。
戦後復興、高度経済成長を経た日本の地域が、これからどんな姿であるべきか。
そんな問いを自らに掲げた小さな町の答えが、古い景観と若い感性が同居する現在の小布施町の有り様だった。
「モノづくりにおいて、自分はアートディレクターだって言うのが一番適切なんだろうなと思った。デザイナーだとパッケージの"ここの部分だけ"しかつくれないけど、資材や流通なんかを全部結ぶとなると、それはアートディレクターの仕事になるんだよ」
ナベさんは流通も含めたプロダクトの「行く末」に可能性を見出すようになる。
こうしたナベさんの気づきと人生経験が下地となって、Green Lab.やPRANA PUNKSといったスノーボード・プロジェクトが立ち上がっていくこととなる。
面白いことに、原山さんは「ほとんど仕事をしない人だった」という。
正確に言えば仕事をしないわけではないのだが、どちらかというと経営者たちの相談話をよく聞いていた。
つまり、みんなの相談役である。
それも「うちの息子がこうでこうで、先生どうしたらいいんですかね」といった身の上話のように、仕事と直接的には関係のない話ばかりだった。
困っている人の面倒を見ること、お世話をすること。
人の声に耳を傾けること、寄り添うこと。
温度感のあるやりとりがあること。
それらが原山さんの大切にしていたことだった。
ナベさんは原山さんの姿を見ながら、つくる側と客の関係性や「寄り添うモノづくり」というテーマを見出していった。
そんな折、長野県小布施町にある栗菓子の老舗店「小布施堂」の当時の副社長・市村良三さん(後の小布施町の町長)から「ナベちゃん、スノーボードつくってみない?」という声がかかる。
当時、県内で最も面積の小さな小布施町は過疎化の一途を辿っており、市村さんは、このままだと10年後には高齢者の観光客しかやって来ない町になってしまう、と危惧していた。
短期間で得られる目先の利益に飛びつくのではなくて、もっと時間をかけ、10年後の未来を見据えた長期的なまちづくりを行っていかなければならない。
そして、そこには若い子たちも絶対に必要である、と考えた。
そうしてナベさんが「将来にコンタクトできるための板」としてつくったのが、現在の小布施堂の店内の壁に飾ってある赤と黒の、葛飾北斎の絵が描かれたスノーボードである。
1996~2000年くらいまで、5年ほどつくっていたという。
小布施町はその後、個人宅の庭を一般開放する「おぶせオープンガーデン」、スケートボードやスラックラインのパーク(練習場)、古い公園を再利用したスケートボード施設、全国から35歳以下の若者を集め地域の未来を話し合う2泊3日の「小布施若者会議」など、ユニークな試みを次々と展開していく。
今や小布施町は年間120万人の観光客が訪れる「栗と北斎の町」である。
戦後復興、高度経済成長を経た日本の地域が、これからどんな姿であるべきか。
そんな問いを自らに掲げた小さな町の答えが、古い景観と若い感性が同居する現在の小布施町の有り様だった。
「モノづくりにおいて、自分はアートディレクターだって言うのが一番適切なんだろうなと思った。デザイナーだとパッケージの"ここの部分だけ"しかつくれないけど、資材や流通なんかを全部結ぶとなると、それはアートディレクターの仕事になるんだよ」
ナベさんは流通も含めたプロダクトの「行く末」に可能性を見出すようになる。
こうしたナベさんの気づきと人生経験が下地となって、Green Lab.やPRANA PUNKSといったスノーボード・プロジェクトが立ち上がっていくこととなる。

ビッグウォールからパリ・ダカールへ
最初はまさか自分がスノーボードをつくることになるとは思わなかったナベさんだが、やってみて「スノーボードが一番伝えやすい」と感じたという。
というのもクライミングや登山には、どうしても「上を目指す」空気や精神性のようなものがあって、ナベさんは「難しい方へ、難しい方へ」というグレード至上主義のような、ドライな空気をなんとなく感じていたのだ。
「高グレードの山を登ることが凄い、っていう世界はちょっと嫌だったんだよね。そんなに難しいことじゃないんだよ~! もっと楽しもうよって(笑)。その点、スノーボードには"楽しむための"っていう大前提があるんだ。それが大きかった。だって、毎回、風向きも雪質も違って一期一会だから。ミスもへったくれもないんだよ。みんなで楽しめるかどうか、それだけ」
ちなみに「垂直が行けるなら水平も行けるんじゃねぇかな」と考えたナベさんは、いったんクライミングや登山から離れ、マウンテンバイクやラリーにも挑戦している。
新しい競技でもコツを掴むのが上手く、習得は早かった。
30代の時には全日本マウンテンバイク選手権大会(ダウンヒル部門)で入賞。
今のようにサスペンションもない時代に、タンクトップ&短パンという姿で急な坂を下った。
「軸の違いだけだから、横もまた冒険かって思って。これギャグみたいな話だけど、真剣にパリ・ダカールラリーに出ようとしてたからね(笑)」
「パリ・ダカール・ラリー」は、フランスのパリからセネガルのダカールまで砂漠を抜けて車で走る過酷な耐久レースである。
JAF(日本自動車連盟)の国内競技のBライセンスがないと出れないことを知り、そのライセンスをとるために地域のモータースポーツクラブに入会。賞味4年間、特訓を積んだ。
3年目にはスポンサーもついて、DCCS(ダイハツ・カー・クラブオブ・スポーツ)主催の「第19回DCCSウィンターラリー クラスB」(1988年2月)の決勝に出場。「No.39」のゼッケンをつけたナベさんは、トヨタ車で完走。
60台が出場して、結果は15位だった。
結局、「パリ・ダカール・ラリー」の夢は叶わなかった。
ナベさんは「行きたかったなぁ、パリ」と悔しそうに声を漏らしていたが、このラリーのエピソードを語る時はひときわ目を輝かせて、興奮気味だったのが印象的だった。
よっぽど行きたかったに違いない。
あいつの気にもなってみろよ
何より驚かされるのはナベさんの「垂直から水平に」という奇想天外の発想力、それを実際にやってのける実行力、そして驚く早さで競技の技術を習得していく身体能力である。
しかも、それらを支えているのは「楽しいから」「ワクワクするから」といった、内から沸き起こる快楽的なモチベーションである。
最初はまさか自分がスノーボードをつくることになるとは思わなかったナベさんだが、やってみて「スノーボードが一番伝えやすい」と感じたという。
というのもクライミングや登山には、どうしても「上を目指す」空気や精神性のようなものがあって、ナベさんは「難しい方へ、難しい方へ」というグレード至上主義のような、ドライな空気をなんとなく感じていたのだ。
「高グレードの山を登ることが凄い、っていう世界はちょっと嫌だったんだよね。そんなに難しいことじゃないんだよ~! もっと楽しもうよって(笑)。その点、スノーボードには"楽しむための"っていう大前提があるんだ。それが大きかった。だって、毎回、風向きも雪質も違って一期一会だから。ミスもへったくれもないんだよ。みんなで楽しめるかどうか、それだけ」
ちなみに「垂直が行けるなら水平も行けるんじゃねぇかな」と考えたナベさんは、いったんクライミングや登山から離れ、マウンテンバイクやラリーにも挑戦している。
新しい競技でもコツを掴むのが上手く、習得は早かった。
30代の時には全日本マウンテンバイク選手権大会(ダウンヒル部門)で入賞。
今のようにサスペンションもない時代に、タンクトップ&短パンという姿で急な坂を下った。
「軸の違いだけだから、横もまた冒険かって思って。これギャグみたいな話だけど、真剣にパリ・ダカールラリーに出ようとしてたからね(笑)」
「パリ・ダカール・ラリー」は、フランスのパリからセネガルのダカールまで砂漠を抜けて車で走る過酷な耐久レースである。
JAF(日本自動車連盟)の国内競技のBライセンスがないと出れないことを知り、そのライセンスをとるために地域のモータースポーツクラブに入会。賞味4年間、特訓を積んだ。
3年目にはスポンサーもついて、DCCS(ダイハツ・カー・クラブオブ・スポーツ)主催の「第19回DCCSウィンターラリー クラスB」(1988年2月)の決勝に出場。「No.39」のゼッケンをつけたナベさんは、トヨタ車で完走。
60台が出場して、結果は15位だった。
結局、「パリ・ダカール・ラリー」の夢は叶わなかった。
ナベさんは「行きたかったなぁ、パリ」と悔しそうに声を漏らしていたが、このラリーのエピソードを語る時はひときわ目を輝かせて、興奮気味だったのが印象的だった。
よっぽど行きたかったに違いない。
あいつの気にもなってみろよ
何より驚かされるのはナベさんの「垂直から水平に」という奇想天外の発想力、それを実際にやってのける実行力、そして驚く早さで競技の技術を習得していく身体能力である。
しかも、それらを支えているのは「楽しいから」「ワクワクするから」といった、内から沸き起こる快楽的なモチベーションである。

ナベさんは地球上を縦横無尽に駆け回り、人生を余すことなくフルに楽しみきろうとする自由な冒険家、旅人だ。
「俺たちさ、こんな時代で、生きてたかだか100年じゃん。まともに動ける時間が60年から80年くらいだったとしたら、せめてその間はまわりの友達と気持ちよく飲んだの騒いだの、そうすりゃいいだけの話なんだよ。厄介な騒ぎとか恐怖心とか、そういうので俺の時間を埋めないでちょ~!(笑)。いろいろダメな政治にならないでちょ! 人を縛るための法律もそんなにつくんないでちょ! 勝手に自分たちで、自分たちの都合で、都合のいい解釈しないでちょ! って感じ」
競争原理、勝敗志向、ヒエラルヒー、規律といったものは、不安や恐怖を煽りやすい。
それが極度のストレスになってそちらに意識を奪われると、今度は自分は何がしたかったのかとか、何のために生きているのかといった人生の方向性や「根っこ」の部分がだんだんわからなくなってくる。これが狂いや戸惑いとなり、ついには身動きがとれなくなってしまう。
ナベさんは「恐怖心に駆り立てられていく内に、どんどん弱っちい人間になっていく」「根っこや基準を見失って、"自分で選択する"ということができなくなってしまう」と言う。
「結局、その子の気持ちになってみろっていうことだと思った。"お前、あいつの気にもなってみろよ"って言うじゃん。逆に言うと、今の社会ってそうではない状況で。その人に寄り添えてもいない。どっちかと言えば市場経済で、"こっちに来るなよ、こっちに来るなよ"っていう社会。そんな社会で本当に求められるモノづくりは、どこまでその人の思いに寄り添えるのか、でしかないと俺は思ってるのよ」
ナベさんが「楽しもうよ!」と繰り返し言うのは、何が自分の生きがいなのか、生の感触を常に確認し続けたいからなのだろう。だから命がけのエクストリームスポーツにも果敢に挑戦していく。
PRANA PUNKSのロゴマークには見開いた目のイラストが描かれていた。
目を覚ませ、と言わんばかりである。 真っ当なものづくり
真っ当なものづくり
取材中、ナベさんは「真っ当なモノづくり」「真っ当な生き方」といったように、「真っ当」という言葉をよく使っていた。
「これは俺の造語なんだけど、"真っ当な人"って書いて、"真人(まっとう)"って読んでるの」
世の中、どこからが「真っ当」で、どこからが「真っ当」でなくなるのか。
ナベさんの言う「真人」とは、その境界線を自分の基準や感性で見極めることができる人のことを指しているように見える。
ふと、階段に立て掛けてあるウッドコアが目に入った。
ナベさんが今年つくっている、来季出荷分のウッドコアだ。
「ちょっと見せてもらってもいいですか」
近寄ってそのウッドコアをよく見てみた。
使われている角材の1本1本の模様や色が違っていた。
「これ、どういうことですか?」と聞くと、ナベさんは木曽ヒノキだけでなくカラマツやキハダなど数種類の木の角材を組み合わせて1枚のウッドコアをつくっていることを教えてくれた。それもウッドコアごとに1枚ずつ、その素材や配置も異なっているのだ。
ナベさんは注文者リストの全員の名前を見ながら「これは誰々さん用で、これは誰々さん用」といったように、ひとりひとりの顔を思い浮かべながら、できる限りその人に合ったウッドコアをカスタマイズしていたのだ。
驚いた。
まるでオーダメイドのスーツである。
ここまで細かい調整は大量生産体制だとなかなか難しいが、「目の届く小さな範囲で、小さな規模の生産、流通を」ということであれば、手仕事や職人技といったクリエイティブな余地を十分に残すことができるのだろう。
全ては偶然なんかじゃない!
来季発表されるPRANA PUNKSのスノーボードの試作品も置いてあった。
そこにはナベさんがデザインした「シャコちゃん」こと縄文遮光器土偶のイラストが載っていた。
取材の終盤になってきてようやく理解したのだが、Green Lab.にしてもPRANA PUNKSにしても、ナベさんは最初から一貫して「縄文」というテーマでスノーボードづくりを行ってきたのだ。
「俺たちさ、こんな時代で、生きてたかだか100年じゃん。まともに動ける時間が60年から80年くらいだったとしたら、せめてその間はまわりの友達と気持ちよく飲んだの騒いだの、そうすりゃいいだけの話なんだよ。厄介な騒ぎとか恐怖心とか、そういうので俺の時間を埋めないでちょ~!(笑)。いろいろダメな政治にならないでちょ! 人を縛るための法律もそんなにつくんないでちょ! 勝手に自分たちで、自分たちの都合で、都合のいい解釈しないでちょ! って感じ」
競争原理、勝敗志向、ヒエラルヒー、規律といったものは、不安や恐怖を煽りやすい。
それが極度のストレスになってそちらに意識を奪われると、今度は自分は何がしたかったのかとか、何のために生きているのかといった人生の方向性や「根っこ」の部分がだんだんわからなくなってくる。これが狂いや戸惑いとなり、ついには身動きがとれなくなってしまう。
ナベさんは「恐怖心に駆り立てられていく内に、どんどん弱っちい人間になっていく」「根っこや基準を見失って、"自分で選択する"ということができなくなってしまう」と言う。
「結局、その子の気持ちになってみろっていうことだと思った。"お前、あいつの気にもなってみろよ"って言うじゃん。逆に言うと、今の社会ってそうではない状況で。その人に寄り添えてもいない。どっちかと言えば市場経済で、"こっちに来るなよ、こっちに来るなよ"っていう社会。そんな社会で本当に求められるモノづくりは、どこまでその人の思いに寄り添えるのか、でしかないと俺は思ってるのよ」
ナベさんが「楽しもうよ!」と繰り返し言うのは、何が自分の生きがいなのか、生の感触を常に確認し続けたいからなのだろう。だから命がけのエクストリームスポーツにも果敢に挑戦していく。
PRANA PUNKSのロゴマークには見開いた目のイラストが描かれていた。
目を覚ませ、と言わんばかりである。

取材中、ナベさんは「真っ当なモノづくり」「真っ当な生き方」といったように、「真っ当」という言葉をよく使っていた。
「これは俺の造語なんだけど、"真っ当な人"って書いて、"真人(まっとう)"って読んでるの」
世の中、どこからが「真っ当」で、どこからが「真っ当」でなくなるのか。
ナベさんの言う「真人」とは、その境界線を自分の基準や感性で見極めることができる人のことを指しているように見える。
ふと、階段に立て掛けてあるウッドコアが目に入った。
ナベさんが今年つくっている、来季出荷分のウッドコアだ。
「ちょっと見せてもらってもいいですか」
近寄ってそのウッドコアをよく見てみた。
使われている角材の1本1本の模様や色が違っていた。
「これ、どういうことですか?」と聞くと、ナベさんは木曽ヒノキだけでなくカラマツやキハダなど数種類の木の角材を組み合わせて1枚のウッドコアをつくっていることを教えてくれた。それもウッドコアごとに1枚ずつ、その素材や配置も異なっているのだ。
ナベさんは注文者リストの全員の名前を見ながら「これは誰々さん用で、これは誰々さん用」といったように、ひとりひとりの顔を思い浮かべながら、できる限りその人に合ったウッドコアをカスタマイズしていたのだ。
驚いた。
まるでオーダメイドのスーツである。
ここまで細かい調整は大量生産体制だとなかなか難しいが、「目の届く小さな範囲で、小さな規模の生産、流通を」ということであれば、手仕事や職人技といったクリエイティブな余地を十分に残すことができるのだろう。
全ては偶然なんかじゃない!
来季発表されるPRANA PUNKSのスノーボードの試作品も置いてあった。
そこにはナベさんがデザインした「シャコちゃん」こと縄文遮光器土偶のイラストが載っていた。
取材の終盤になってきてようやく理解したのだが、Green Lab.にしてもPRANA PUNKSにしても、ナベさんは最初から一貫して「縄文」というテーマでスノーボードづくりを行ってきたのだ。

なぜ縄文なのか。
「もう謎すぎてわかんね(笑)。でも見てる限り、聞いてる限り、ものすごく素直に、とてつもなく長い歴史をひたすら平和に、寄り添い合いながら暮らしていたらしいんだよ」
終戦後、焼け野原から復興、高度経済成長を経て、価値観や風景が様変わりしていく激動の時代からナベさんが見つけ出した「寄り添う」というテーマは、実は縄文時代からずっと変わらない、人類普遍の根源的なテーマだったのかもしれない。
理想郷のような世界を生きた縄文人たちに呼応するように、ナベさんはウッドコアに載せるグラフィックを独特のタッチで描き出していく。
取材の最後、ナベさんはこのように語ってくれた。
「俺の大好きなナミさんが去年、亡くなったんだけど、生前、俺にずっと言ってたんだよ。『ナベちゃん、縁じゃないから。偶然じゃないからね』って。みんな偶然知り合って何かがあるっていうんじゃなくて、そんなの前から決まってて、決められたところにいて、そのタイミングが来るってだけ。そういう運命なんだよ。サブがこうやって取材しにここへ来るのもそう。なんかあるんだよ。ナミさんが『俺たちは草の根で繋がっているから、その力を信じよう』って言ってたけど、俺は本当に全くその通りだと思った。信じるって言葉よりも、草の根に『信じてまっせ』を言われたほうがよっぽど強いと思う」
「偶然じゃない」。
その言葉はナミさんからナベさんへ、そしてナベさんから自分へと手渡された。
自分もまた誰かに手渡していくのだろう。
こうしてナベさんの取材は終わった。
まさか10年以上の付き合いになるとは最初は思ってもみなかったが、ナベさんの言う通り、この出会いもまた偶然ではなかったのだろう。翻って、この記事とここまで読んでくれた読者の方々との出会いもまた、偶然ではないはずだ。
取材後、東京に帰った僕は、どんな風に世界が見えるようになったか、数日、数週間と時間をかけながらワクワクとその後の変化を噛みしめるように確かめた。不思議とミラクルな出来事が立て続けに起こったが、その話はまた別の機会に譲ろう。
「もう謎すぎてわかんね(笑)。でも見てる限り、聞いてる限り、ものすごく素直に、とてつもなく長い歴史をひたすら平和に、寄り添い合いながら暮らしていたらしいんだよ」
終戦後、焼け野原から復興、高度経済成長を経て、価値観や風景が様変わりしていく激動の時代からナベさんが見つけ出した「寄り添う」というテーマは、実は縄文時代からずっと変わらない、人類普遍の根源的なテーマだったのかもしれない。
理想郷のような世界を生きた縄文人たちに呼応するように、ナベさんはウッドコアに載せるグラフィックを独特のタッチで描き出していく。
取材の最後、ナベさんはこのように語ってくれた。
「俺の大好きなナミさんが去年、亡くなったんだけど、生前、俺にずっと言ってたんだよ。『ナベちゃん、縁じゃないから。偶然じゃないからね』って。みんな偶然知り合って何かがあるっていうんじゃなくて、そんなの前から決まってて、決められたところにいて、そのタイミングが来るってだけ。そういう運命なんだよ。サブがこうやって取材しにここへ来るのもそう。なんかあるんだよ。ナミさんが『俺たちは草の根で繋がっているから、その力を信じよう』って言ってたけど、俺は本当に全くその通りだと思った。信じるって言葉よりも、草の根に『信じてまっせ』を言われたほうがよっぽど強いと思う」
「偶然じゃない」。
その言葉はナミさんからナベさんへ、そしてナベさんから自分へと手渡された。
自分もまた誰かに手渡していくのだろう。
こうしてナベさんの取材は終わった。
まさか10年以上の付き合いになるとは最初は思ってもみなかったが、ナベさんの言う通り、この出会いもまた偶然ではなかったのだろう。翻って、この記事とここまで読んでくれた読者の方々との出会いもまた、偶然ではないはずだ。
取材後、東京に帰った僕は、どんな風に世界が見えるようになったか、数日、数週間と時間をかけながらワクワクとその後の変化を噛みしめるように確かめた。不思議とミラクルな出来事が立て続けに起こったが、その話はまた別の機会に譲ろう。

取材をしていると「不思議な現象」が起こることがある。
それは、最初は他人事のように見ていた物事が、だんだんそう見えなくなってくる、というものだ。
まるで「あなたのために用意しておいた話なんだよ」と言われているようである。
取材とは話を聞きたい人に会いに行く活動のことだが、その人物と会うことが実は前から決まっていたのではないか。
ふと、そんな錯覚をおぼえることがある。
来季はどんなスノーボードがみんなの手元に届くだろうか。
ナベさんの思いを乗せた木曽ヒノキのスノーボードは今日もまた、どこかのスキー場や断崖絶壁で真っ白な雪の上を、体をしならせながら気持ちよく滑っているに違いない。
旅はまだまだ続く。(了)
それは、最初は他人事のように見ていた物事が、だんだんそう見えなくなってくる、というものだ。
まるで「あなたのために用意しておいた話なんだよ」と言われているようである。
取材とは話を聞きたい人に会いに行く活動のことだが、その人物と会うことが実は前から決まっていたのではないか。
ふと、そんな錯覚をおぼえることがある。
来季はどんなスノーボードがみんなの手元に届くだろうか。
ナベさんの思いを乗せた木曽ヒノキのスノーボードは今日もまた、どこかのスキー場や断崖絶壁で真っ白な雪の上を、体をしならせながら気持ちよく滑っているに違いない。
旅はまだまだ続く。(了)

渡辺尚幸/スノーボードブランド〈PRANA PUNKS〉代表。デザイナー。アートディレクター。スノーボーダー(241所属)。
1958年、新潟県新井市生まれ。ロッククライマー、ラリードライバー、山岳ガイド、プロスノーボーダーなどの活動を経て、2004年、信州産の間伐材を芯材に使ったスノーボードのブランド〈Green Lab.〉を、中山一郎、中山二郎らと設立。グラフィックとディレクションを担当し、2015年、個人ブランド〈PRANA PUNKS SNOWBOARDING〉を設立。自らが作詞作曲を手がけるフォーク・ロックバンド「Fighting Farmers」ではヴォーカルとギターを担当。
-

FORESTER
Shigeaki Adachi
-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER
Kei Amano
-

BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER
Taiki Minakuchi
-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭 火付ぬ組
-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN
Yukihito Kanai
-

SAUNA BUILDER
nodaklaxonbebe