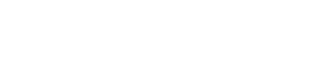Chapter 3 Vol.Two
SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
Naoyuki Watanabe
渡辺尚幸
TEXT by SABU
PHOTOGRAPHS by KAZUMA ITO
PHOTOGRAPHS by KAZUMA ITO
ものづくりに求められるのは、本質を見極める目と、どの角度から見るか。
そうして生み出される独自の価値観こそが、クリエイティブの要諦だと渡辺は語る。
資本や組織に依らず、地道に創造活動を続けてきた者だけが得ることのできる哲学は、いかにして育まれたのか。
そうして生み出される独自の価値観こそが、クリエイティブの要諦だと渡辺は語る。
資本や組織に依らず、地道に創造活動を続けてきた者だけが得ることのできる哲学は、いかにして育まれたのか。
呼吸するスノーボード
新潟での取材は「素材のポテンシャル」をキーワードに話が進んだ。
ナベさん曰く、PRANA PUNKSでは信州南木曽の「木曽ヒノキ」を使ったウッドコアでスノーボードをつくっているという。
なぜ「木曽ヒノキ」という素材にこだわったのかと聞くと、ナベさんは「木曽ヒノキは、よく"しなる"からなんだよ」と教えてくれた。
新潟での取材は「素材のポテンシャル」をキーワードに話が進んだ。
ナベさん曰く、PRANA PUNKSでは信州南木曽の「木曽ヒノキ」を使ったウッドコアでスノーボードをつくっているという。
なぜ「木曽ヒノキ」という素材にこだわったのかと聞くと、ナベさんは「木曽ヒノキは、よく"しなる"からなんだよ」と教えてくれた。

ナベさんの話には「しなり」「鳴り」「乗り味」といった、趣味性を表現する言葉がよく出てくるのが特徴である。
「スノーボードにとって重要なのは"しなり"だから、当然しなる木を使った方がいいに決まってる。木曽ヒノキってのは、法隆寺や伊勢神宮にも使われている高級木材なんだよ。地震列島である日本で1300年も衝撃に耐えているのは、木曽ヒノキがよくしなるからなのさ。俺たちはそのことに10年以上も前から注目してたんだ。たぶん木曽ヒノキでスノーボードをつくったのは俺たちが初めてだと思う」
世の中にはカーボン製のスノーボードも多く存在するが、ナベさんにとってカーボンは「ダメな素材をなんとか使えるようにするための"補強材"」でしかない。
木曽ヒノキはもとから素材が良いので、カーボンで補強せずとも、乗り心地の良いスノーボードを実現できるのだ。
「だから、うちは木のまんま。"木が呼吸するスノーボード"ってわけ」
PRANA PUNKSのスノーボードはスノーボーダーたちの間でも「軽くて、しなやかで、柔らかい」、「薄いのに踏み込んだ瞬間の"返り"が速い」と言われ、評判が高い。
「技術力って、いいモノを探してくる力のことだと思うんだ。たとえば寿司屋の職人って、もちろん寿司を握る技術も大事なんだけれど、それ以上にネタが良いのか悪いのか、そこを見極める"目"をもっているかどうかが大事だと思う。いい寿司屋っていうのは、本当にうまいものを見つけてきて食わしてくれる寿司屋のことだと俺は思ってるんだ」 ナベさんの鋭い視点や的確な喩えにも驚いたが、何より印象的だったのは、どの主張も長年にわたり積み重ねた経験に基づいていて、理にかなっているということだった。
ナベさんの鋭い視点や的確な喩えにも驚いたが、何より印象的だったのは、どの主張も長年にわたり積み重ねた経験に基づいていて、理にかなっているということだった。
要は、PRANA PUNKSでナベさんがやっているのは、素材のもつ「癖」や「個性」をできる限り一般化・標準化"せずに"、むしろそれらを「キワ」まで突き詰めたらどうなるのか確かめてみよう、というかなり実験的なものづくりだったのだ。
硬い木なら、硬い木らしく。
歪んだ木なら、歪んだ木らしく。
「だってさ、自然がつくったものってもっとポテンシャルあるはずじゃん! って俺は思ってるんだけどね」
「使いにくいから」「利用価値がないから」といってゴミ扱いしていくのは、そういう風にしか見られない「目」や「解釈」が存在するからなのだ。
薬草も使い方がわからなければただの雑草であるように、効能・効果や性質を知らないということや、そこまで好奇心が沸かないと言って見限る瞬間が、人間の想像力の終着点となっている。
「スノーボードにとって重要なのは"しなり"だから、当然しなる木を使った方がいいに決まってる。木曽ヒノキってのは、法隆寺や伊勢神宮にも使われている高級木材なんだよ。地震列島である日本で1300年も衝撃に耐えているのは、木曽ヒノキがよくしなるからなのさ。俺たちはそのことに10年以上も前から注目してたんだ。たぶん木曽ヒノキでスノーボードをつくったのは俺たちが初めてだと思う」
世の中にはカーボン製のスノーボードも多く存在するが、ナベさんにとってカーボンは「ダメな素材をなんとか使えるようにするための"補強材"」でしかない。
木曽ヒノキはもとから素材が良いので、カーボンで補強せずとも、乗り心地の良いスノーボードを実現できるのだ。
「だから、うちは木のまんま。"木が呼吸するスノーボード"ってわけ」
PRANA PUNKSのスノーボードはスノーボーダーたちの間でも「軽くて、しなやかで、柔らかい」、「薄いのに踏み込んだ瞬間の"返り"が速い」と言われ、評判が高い。
「技術力って、いいモノを探してくる力のことだと思うんだ。たとえば寿司屋の職人って、もちろん寿司を握る技術も大事なんだけれど、それ以上にネタが良いのか悪いのか、そこを見極める"目"をもっているかどうかが大事だと思う。いい寿司屋っていうのは、本当にうまいものを見つけてきて食わしてくれる寿司屋のことだと俺は思ってるんだ」

要は、PRANA PUNKSでナベさんがやっているのは、素材のもつ「癖」や「個性」をできる限り一般化・標準化"せずに"、むしろそれらを「キワ」まで突き詰めたらどうなるのか確かめてみよう、というかなり実験的なものづくりだったのだ。
硬い木なら、硬い木らしく。
歪んだ木なら、歪んだ木らしく。
「だってさ、自然がつくったものってもっとポテンシャルあるはずじゃん! って俺は思ってるんだけどね」
「使いにくいから」「利用価値がないから」といってゴミ扱いしていくのは、そういう風にしか見られない「目」や「解釈」が存在するからなのだ。
薬草も使い方がわからなければただの雑草であるように、効能・効果や性質を知らないということや、そこまで好奇心が沸かないと言って見限る瞬間が、人間の想像力の終着点となっている。

ナベさんは、自然保護に理解のある南木曽木材工業から正規ではない(商材ではない)木曽ヒノキを提供してもらっている。普通なら捨てられてしまう端材である。
「でもさ、産地がすごくいい産地なら、ゴミもまたゴミとは呼べないわけ。ただ使われてない木を使っているわけじゃなくて、本当にいい木を使ってるんだからね」
木という資源を「お金になるかならないか」という基準で判断する前に、まず「木を木として」認めることが大事だとナベさんは言う。
「でもそれは"キワ"だからね。好き嫌いがあって当然。決して万人受けするモノにはならないっていうのは、当たり前の話なんだよね。でも、それでいいじゃんって思ってる」
サンスクリット語で「気」「呼吸」「生命力」を意味する「PRANA」(プラーナ)という言葉には、その素材がもつポテンシャルに対するリスペクトの念が込められている。
「自然がつくり出す森羅万象の事柄は、あまりにも強いインパクトがあるなっていうことだね。ただそれだけ。それほど極めて美しいし、極めてコアだしっていう部分かなって思ってて。何より凄い驚きだよね、自然のつくり出すあの現象が驚異以外の何ものでもなくて、というか驚きも越しちゃってて」
スノーボードの話を聴いているはずなのに、僕にはどうもそれがスノーボードだけの話には聴こえなかった。
ただトゲがあるだけじゃん
ナベさんは技術者や研究者のようでありながら、詩人や編集者のようでもある。
言葉の力を上手くものづくりに取り入れているのだ。
注目したいのが、PRANAに続く「PUNKS」(パンクス)という言葉である。
「でもさ、産地がすごくいい産地なら、ゴミもまたゴミとは呼べないわけ。ただ使われてない木を使っているわけじゃなくて、本当にいい木を使ってるんだからね」
木という資源を「お金になるかならないか」という基準で判断する前に、まず「木を木として」認めることが大事だとナベさんは言う。
「でもそれは"キワ"だからね。好き嫌いがあって当然。決して万人受けするモノにはならないっていうのは、当たり前の話なんだよね。でも、それでいいじゃんって思ってる」
サンスクリット語で「気」「呼吸」「生命力」を意味する「PRANA」(プラーナ)という言葉には、その素材がもつポテンシャルに対するリスペクトの念が込められている。
「自然がつくり出す森羅万象の事柄は、あまりにも強いインパクトがあるなっていうことだね。ただそれだけ。それほど極めて美しいし、極めてコアだしっていう部分かなって思ってて。何より凄い驚きだよね、自然のつくり出すあの現象が驚異以外の何ものでもなくて、というか驚きも越しちゃってて」
スノーボードの話を聴いているはずなのに、僕にはどうもそれがスノーボードだけの話には聴こえなかった。
ただトゲがあるだけじゃん
ナベさんは技術者や研究者のようでありながら、詩人や編集者のようでもある。
言葉の力を上手くものづくりに取り入れているのだ。
注目したいのが、PRANAに続く「PUNKS」(パンクス)という言葉である。

なぜ「パンクス」なのか。
まず確認しておきたいが、そもそも「パンク」とは、本来的には「反体制」や「アナーキズム」(無政府主義)を指す、社会にとってはタブー(禁句)のような言葉であるということだ。
ナベさんは「あまり表面に出ちゃいけない言葉」だと言う。
英語のパンク(punk)には「不良」「チンピラ」「青二才」「役立たず」といった意味もある。
こうして見ると、悪役・曲者のような言葉である。
しかしそんな言葉をあえてブランド名につけることで、ナベさんはスキー場にある面白い光景をつくり出してしまう。
「スノーボードの世界でパンクっていう言葉を使って表現したら『おぉ』って反応してくれる人たちがかなりいたのも事実でさ。スキー場でアナウンスされるのがなんて心地いいんだろうって思ったんだよ。『本日はバートン、リブテック、プラーナ"パンクス"の試乗会が行われています』なんて、何度も何度も"パンク"を連呼してくれるわけ(笑)」
嬉しそうに語るナベさんにつられて、思わず吹き出してしまった。 さながら言葉遊びをするお笑いコントのようであるが、その実、ナベさんはスノーボードと同時に「パンク」という言葉(価値観、思想、生き様)も、"さり気なく"流通させていたのだった。
さながら言葉遊びをするお笑いコントのようであるが、その実、ナベさんはスノーボードと同時に「パンク」という言葉(価値観、思想、生き様)も、"さり気なく"流通させていたのだった。
盲点というか、実に意外な切り口。
非常にソフトかつエレガントな"載せ方"だ。
「俺ら、トゲがあって刺せるけどさ、あえて刺すつもりなんか全くないじゃん。"ただトゲがあるだけだぜ"って。それだけじゃん、わかるでしょ?(笑)」
示唆的な表現である。
「ただトゲがあるだけ」。
ナベさんは問題の本質が、トゲの「尖っている」という性質そのものにあるのではなく、その「尖り」の向かう矛先にある、ということを暗に教えてくれている。
言うなれば、ナベさんがPRANA PUNKSで試みたのは、「パンク」という〈精神性〉と「木曽ヒノキ」という〈物質性〉を組み合わせる、ということだったのかもしれない。
互いに全く関わりのないように思えるモノ同士の組み合わせでも、意外に「これはこれでアリだね」と不思議に成立させてしまう。
そこがナベさんの巧みな編集能力、言葉のセンス、クリエイティブの力なのだ。
重要なのは構図
ものづくりにおいて重要なのは〈構図〉である。
「あなたがつくらない限りつくれないのが〈構図〉。だってあるんだもん、そこにずっと、風景が。あなたが見える中において。でもその〈構図〉を切り取る作業っていうのは、自分のやることだから。そういうことの上にあのプラーナって言葉が生まれてくるのさ。自然がつくり出す凄さ。夕焼けの色なんて三原則の色では絶対に出ないじゃん。微妙な湿度だとか、いろんなものが加味されてくるんだもん。人間はそれを追おうとしているに過ぎない。超えることはない。やつらのほうが百花繚乱で凄いよねっていう。結局、なんかそこに至るような気がするな」
ナベさんがただ単に商品をつくって市場に流す「ビジネス」をしているわけではないということは、ここまでの話でも明らかである。利益重視というより、影響重視。
もっと現実のミクロな局面にまで踏み込んで、人間の意識や暮らしにどんな刺激や変化を与えるのかといった社会的、政治的、環境的な影響、つまりプロダクトの「行く末」に対して、人間工学的な観点から戦略的に向き合っているのだ。
まず確認しておきたいが、そもそも「パンク」とは、本来的には「反体制」や「アナーキズム」(無政府主義)を指す、社会にとってはタブー(禁句)のような言葉であるということだ。
ナベさんは「あまり表面に出ちゃいけない言葉」だと言う。
英語のパンク(punk)には「不良」「チンピラ」「青二才」「役立たず」といった意味もある。
こうして見ると、悪役・曲者のような言葉である。
しかしそんな言葉をあえてブランド名につけることで、ナベさんはスキー場にある面白い光景をつくり出してしまう。
「スノーボードの世界でパンクっていう言葉を使って表現したら『おぉ』って反応してくれる人たちがかなりいたのも事実でさ。スキー場でアナウンスされるのがなんて心地いいんだろうって思ったんだよ。『本日はバートン、リブテック、プラーナ"パンクス"の試乗会が行われています』なんて、何度も何度も"パンク"を連呼してくれるわけ(笑)」
嬉しそうに語るナベさんにつられて、思わず吹き出してしまった。

盲点というか、実に意外な切り口。
非常にソフトかつエレガントな"載せ方"だ。
「俺ら、トゲがあって刺せるけどさ、あえて刺すつもりなんか全くないじゃん。"ただトゲがあるだけだぜ"って。それだけじゃん、わかるでしょ?(笑)」
示唆的な表現である。
「ただトゲがあるだけ」。
ナベさんは問題の本質が、トゲの「尖っている」という性質そのものにあるのではなく、その「尖り」の向かう矛先にある、ということを暗に教えてくれている。
言うなれば、ナベさんがPRANA PUNKSで試みたのは、「パンク」という〈精神性〉と「木曽ヒノキ」という〈物質性〉を組み合わせる、ということだったのかもしれない。
互いに全く関わりのないように思えるモノ同士の組み合わせでも、意外に「これはこれでアリだね」と不思議に成立させてしまう。
そこがナベさんの巧みな編集能力、言葉のセンス、クリエイティブの力なのだ。
重要なのは構図
ものづくりにおいて重要なのは〈構図〉である。
「あなたがつくらない限りつくれないのが〈構図〉。だってあるんだもん、そこにずっと、風景が。あなたが見える中において。でもその〈構図〉を切り取る作業っていうのは、自分のやることだから。そういうことの上にあのプラーナって言葉が生まれてくるのさ。自然がつくり出す凄さ。夕焼けの色なんて三原則の色では絶対に出ないじゃん。微妙な湿度だとか、いろんなものが加味されてくるんだもん。人間はそれを追おうとしているに過ぎない。超えることはない。やつらのほうが百花繚乱で凄いよねっていう。結局、なんかそこに至るような気がするな」
ナベさんがただ単に商品をつくって市場に流す「ビジネス」をしているわけではないということは、ここまでの話でも明らかである。利益重視というより、影響重視。
もっと現実のミクロな局面にまで踏み込んで、人間の意識や暮らしにどんな刺激や変化を与えるのかといった社会的、政治的、環境的な影響、つまりプロダクトの「行く末」に対して、人間工学的な観点から戦略的に向き合っているのだ。

「スノーボード・ビジネス」ではなく「スノーボード・プロジェクト」という言い方をするのも頷ける。
このあたりは話がやや専門的というか、ある意味"オタクな"領域なので、自分でもきちんと理解できていたかは正直怪しいけれど、少なくとも、ブランディングという世界を全く心得ていなかった自分にとって、こうしたナベさんの細やかな気の配り方や現実との向き合い方は、ノートにメモしておきたくなるほどタメになる情報のように思われた。
渡辺先生によるブランド戦略論の講義を聴いているようである。
楽しさのバイブスで広げていきたい
ナベさんはクリエイティブにモノを考える時、いつも「対極の概念」を意識すると言う。
たとえば精神と物質、抽象と具体、過去と未来、繊細さと大胆さ、陰と陽といったように2つの異なる面をくっつけて、表裏一体となるような、両義的なモノの考え方をするのだ。
「片側だけだったら終わりなんだよ。つまらないことなんだよ。俺はいつも"2 way"って言ってるんだけど、対極がいてようやく面白くなってくるのさ」
それにしてもどうしてナベさんはいささか「遠回し」とも思えるような伝え方に、こんなにもこだわるのだろうか。
やっていることがトリッキー過ぎると、「何のことやら?」と逆にスルーされてしまうのではないか。
しかしナベさんは「皆まで言うな」と言わんばかりに、あくまで「それとなく、さり気なく、ほのめかす」程度に留めている。
「俺も努力してギリギリのところで見えるようにしてるからさ、どっかで気づいてもらえたらいいなって思ってる。恐怖心を植え付けられて"ゴミを拾わなくちゃ"とかっていうんじゃなくてさ。逆なんだよ。森の木なんかを使って楽しんで、良くなっていった方がいいじゃん。そっちのバイブスを広げていった方がいいじゃんって思ってるんだよ。そうしたらきっと今よりももっと進んだところで物事がよく見えるようになるじゃん」
「社会の問題を解決しなければならない!」と叫ぶのか、それとも「こんなに気持ちいいことってないよね!」と叫ぶのか。それによって向き合い方も心のもちようも随分と変わってくる。どちらの方が「ゴキゲン」かは言うまでもないだろう。
このあたりは話がやや専門的というか、ある意味"オタクな"領域なので、自分でもきちんと理解できていたかは正直怪しいけれど、少なくとも、ブランディングという世界を全く心得ていなかった自分にとって、こうしたナベさんの細やかな気の配り方や現実との向き合い方は、ノートにメモしておきたくなるほどタメになる情報のように思われた。
渡辺先生によるブランド戦略論の講義を聴いているようである。
楽しさのバイブスで広げていきたい
ナベさんはクリエイティブにモノを考える時、いつも「対極の概念」を意識すると言う。
たとえば精神と物質、抽象と具体、過去と未来、繊細さと大胆さ、陰と陽といったように2つの異なる面をくっつけて、表裏一体となるような、両義的なモノの考え方をするのだ。
「片側だけだったら終わりなんだよ。つまらないことなんだよ。俺はいつも"2 way"って言ってるんだけど、対極がいてようやく面白くなってくるのさ」
それにしてもどうしてナベさんはいささか「遠回し」とも思えるような伝え方に、こんなにもこだわるのだろうか。
やっていることがトリッキー過ぎると、「何のことやら?」と逆にスルーされてしまうのではないか。
しかしナベさんは「皆まで言うな」と言わんばかりに、あくまで「それとなく、さり気なく、ほのめかす」程度に留めている。
「俺も努力してギリギリのところで見えるようにしてるからさ、どっかで気づいてもらえたらいいなって思ってる。恐怖心を植え付けられて"ゴミを拾わなくちゃ"とかっていうんじゃなくてさ。逆なんだよ。森の木なんかを使って楽しんで、良くなっていった方がいいじゃん。そっちのバイブスを広げていった方がいいじゃんって思ってるんだよ。そうしたらきっと今よりももっと進んだところで物事がよく見えるようになるじゃん」
「社会の問題を解決しなければならない!」と叫ぶのか、それとも「こんなに気持ちいいことってないよね!」と叫ぶのか。それによって向き合い方も心のもちようも随分と変わってくる。どちらの方が「ゴキゲン」かは言うまでもないだろう。

ナベさんはスノーボードを通じた自然保護活動が、ビクビクした恐怖心によってではなく、ワクワクする楽しさによって広がっていってほしいと言う。
少しずつナベさんのやりたいことが見えてきたような気がした。
取材は日が暮れるまで続き、この日、僕はナベさんの家に泊まらせてもらった。
そしてグイグイと話に引き込まれていった僕は、いつの間にか「ナベさんLOVE!!」な熱烈なファンのひとりとなっていた。
ピースフルで、優しくて、思慮深くて、ユーモアがあって、カッコいい。
周りの人たちがナベさんに注目する理由がよくわかった。
それにしてもこの人は、これまでどんな人生を歩んできたのだろう?
今度はナベさんの経歴が気になった。
ナベさんの生い立ち
JR長野駅から車で約15分。
長野市の東に位置する地附山の中腹の閑静な住宅街に一軒の、年季の入ったアメリカ風のログハウスが建っている。
駐車場には大きなハイエースが1台。玄関先のウッドデッキには大量の角材やウッドチップの入った袋が置いてある。
ほんのりと木の匂いがする。
少しずつナベさんのやりたいことが見えてきたような気がした。
取材は日が暮れるまで続き、この日、僕はナベさんの家に泊まらせてもらった。
そしてグイグイと話に引き込まれていった僕は、いつの間にか「ナベさんLOVE!!」な熱烈なファンのひとりとなっていた。
ピースフルで、優しくて、思慮深くて、ユーモアがあって、カッコいい。
周りの人たちがナベさんに注目する理由がよくわかった。
それにしてもこの人は、これまでどんな人生を歩んできたのだろう?
今度はナベさんの経歴が気になった。
ナベさんの生い立ち
JR長野駅から車で約15分。
長野市の東に位置する地附山の中腹の閑静な住宅街に一軒の、年季の入ったアメリカ風のログハウスが建っている。
駐車場には大きなハイエースが1台。玄関先のウッドデッキには大量の角材やウッドチップの入った袋が置いてある。
ほんのりと木の匂いがする。

ピンポン、と家のベルを鳴らすと奥の方から「あいあ~い」と抜けた調子の声が返ってきた。
足音が近づいてきて、玄関の木の扉が開く。
「おう、さぶちゃん、久しぶり! 調子どう? 入りな~」
家の中に入るとまず目に飛び込むのが、やはりギターである。少なくとも5~6本は置いてあって、ヤマハ、ギブソン、マーチン、S.Yairiなどメーカーはさまざまだ。
PRANA PUNKSの来季試作品やウッドコアもずらりと並んでいる。
ナベさんが温かいコーヒーを淹れてくれた。
2021年10月19日。前回の取材から、はや6年。
最初にGreen Lab.の記事を読んだ時から数えると、なんともう10年の月日が経っていた。
「今日もよろしくお願いします!」
「まあまあ、そう焦らずに」
ぷ~っとタバコの煙をくゆらせ、一息ついた後、ナベさんはとうとうと喋り始めた。
ナベさんというひとりの人間を形成した、その壮絶な人生ヒストリーの世界に、僕はいよいよ足を踏み入れた。 戦後、激動の時代に生まれる
戦後、激動の時代に生まれる
時は遡ること1945年、終戦。
戦争に負け、焼け野原となった日本では至るところで孤児、傷病兵、未亡人たちが路頭に迷っていた。
大勢の若者たちが戦争で亡くなり、働き手は不足していた。
そんな時代の混迷期、行く宛のなかった高橋弘(ひろし)さんという長野県川中島出身の20代の男性が、どういうわけか新潟県新井町にある「渡辺タカさん」という小作人の家に流れ着いて、養子に入る。
その後、長野県諏訪の貧しい家庭に生まれた鷲野美津子さんという同じく20代の女性が、近所に住んでいた友人の紹介で、弘さんの世話をするような形で渡辺家に養子として入ってくる。
縁もゆかりもない土地で2人は出会い、結婚して、「渡辺」という全く知らない人の家の性となる。
そこで4人の子ども(2人の息子と2人の娘)を生み、育てた。
次男が生まれたのは、1958(昭和33)年1月6日のことである。
それが渡辺尚幸さんだった。
両親ともに養子というのは現代ではあまり馴染みないが、ナベさん曰く「当時としては普通にあったこと」だという。
渡辺タカさんは当時50代。
戦争で旦那と一人息子を失くした未亡人だったが、ひとりで家や田んぼの管理をすることはできず、働き手となる養子をとったのだった。 家は貧しくて「まるでゲットーのようだった」という。
家は貧しくて「まるでゲットーのようだった」という。
貧しい時代、子どもはすなわち労働力だった。
みんなで寄り添いながら、全てを賄っていかなければ生活が成り立たない時代だった。
戦争はみんなの人生をシェイクした
父・弘さんは、17、18歳の時に戦争に駆り出され、予科練の特攻隊に入った兵隊だった。
死を覚悟した父は「精神的に毎日がお祭り騒ぎで楽しかった」という話をナベさんに聞かせていた。
仲間たちと酒を飲み、飯を食い、今生の別れを何度も経験する……。
そんな毎日が続いたという。
しかし、いつになったら戦地へ飛び立つのか、と思っているうちに玉音放送が鳴り、日本は終戦を迎える。
生き延びた父は、その後、兵士たちを励ます慰問団という組織に入り、ハーモニカを吹いたりギターを弾いたりしながら、戦地を歩いて回ったそうだ。
新井の実家にある昔の写真には、ヴァイオリンや太鼓など楽器をもった人たちと並んでギターを抱えた父の姿が写っている。
ナベさんが生まれてからは、新井にある大日本セルロイドという軍需関係の会社の社員として、化学工場で働いた。
ナベさんが小学校低学年の頃、タカさんは他界。
自分のおばあちゃんだと思っていた人が血の繋がりがないことを、そこで初めて知ることになるが、あまりショックではなかったという。
「それが戦争というものだったからね。戦争って、すっごいみんなの人生をシェイクしたんだよ」
その後、2人の妹たちは嫁いでいき、父親は他界。母親は認知症で介護施設に入所している。
兄は52歳で癌が発症し、闘病生活の末、60歳で亡くなる。
こうして渡辺家に残された人間は、ナベさんただ一人となった。
「渡辺家っていうのはさ、本当に星が降ってくるように俺が生まれて、そこでいろいろあって。で、俺の代で終わっちゃうんだよ」
足音が近づいてきて、玄関の木の扉が開く。
「おう、さぶちゃん、久しぶり! 調子どう? 入りな~」
家の中に入るとまず目に飛び込むのが、やはりギターである。少なくとも5~6本は置いてあって、ヤマハ、ギブソン、マーチン、S.Yairiなどメーカーはさまざまだ。
PRANA PUNKSの来季試作品やウッドコアもずらりと並んでいる。
ナベさんが温かいコーヒーを淹れてくれた。
2021年10月19日。前回の取材から、はや6年。
最初にGreen Lab.の記事を読んだ時から数えると、なんともう10年の月日が経っていた。
「今日もよろしくお願いします!」
「まあまあ、そう焦らずに」
ぷ~っとタバコの煙をくゆらせ、一息ついた後、ナベさんはとうとうと喋り始めた。
ナベさんというひとりの人間を形成した、その壮絶な人生ヒストリーの世界に、僕はいよいよ足を踏み入れた。

時は遡ること1945年、終戦。
戦争に負け、焼け野原となった日本では至るところで孤児、傷病兵、未亡人たちが路頭に迷っていた。
大勢の若者たちが戦争で亡くなり、働き手は不足していた。
そんな時代の混迷期、行く宛のなかった高橋弘(ひろし)さんという長野県川中島出身の20代の男性が、どういうわけか新潟県新井町にある「渡辺タカさん」という小作人の家に流れ着いて、養子に入る。
その後、長野県諏訪の貧しい家庭に生まれた鷲野美津子さんという同じく20代の女性が、近所に住んでいた友人の紹介で、弘さんの世話をするような形で渡辺家に養子として入ってくる。
縁もゆかりもない土地で2人は出会い、結婚して、「渡辺」という全く知らない人の家の性となる。
そこで4人の子ども(2人の息子と2人の娘)を生み、育てた。
次男が生まれたのは、1958(昭和33)年1月6日のことである。
それが渡辺尚幸さんだった。
両親ともに養子というのは現代ではあまり馴染みないが、ナベさん曰く「当時としては普通にあったこと」だという。
渡辺タカさんは当時50代。
戦争で旦那と一人息子を失くした未亡人だったが、ひとりで家や田んぼの管理をすることはできず、働き手となる養子をとったのだった。

貧しい時代、子どもはすなわち労働力だった。
みんなで寄り添いながら、全てを賄っていかなければ生活が成り立たない時代だった。
戦争はみんなの人生をシェイクした
父・弘さんは、17、18歳の時に戦争に駆り出され、予科練の特攻隊に入った兵隊だった。
死を覚悟した父は「精神的に毎日がお祭り騒ぎで楽しかった」という話をナベさんに聞かせていた。
仲間たちと酒を飲み、飯を食い、今生の別れを何度も経験する……。
そんな毎日が続いたという。
しかし、いつになったら戦地へ飛び立つのか、と思っているうちに玉音放送が鳴り、日本は終戦を迎える。
生き延びた父は、その後、兵士たちを励ます慰問団という組織に入り、ハーモニカを吹いたりギターを弾いたりしながら、戦地を歩いて回ったそうだ。
新井の実家にある昔の写真には、ヴァイオリンや太鼓など楽器をもった人たちと並んでギターを抱えた父の姿が写っている。
ナベさんが生まれてからは、新井にある大日本セルロイドという軍需関係の会社の社員として、化学工場で働いた。
ナベさんが小学校低学年の頃、タカさんは他界。
自分のおばあちゃんだと思っていた人が血の繋がりがないことを、そこで初めて知ることになるが、あまりショックではなかったという。
「それが戦争というものだったからね。戦争って、すっごいみんなの人生をシェイクしたんだよ」
その後、2人の妹たちは嫁いでいき、父親は他界。母親は認知症で介護施設に入所している。
兄は52歳で癌が発症し、闘病生活の末、60歳で亡くなる。
こうして渡辺家に残された人間は、ナベさんただ一人となった。
「渡辺家っていうのはさ、本当に星が降ってくるように俺が生まれて、そこでいろいろあって。で、俺の代で終わっちゃうんだよ」

ナベさんは現在63歳。
両親が新井にやってきて過ごした時間より長い時間をそこで過ごしていることになる。
5反にも及ぶ田んぼの苗植え、稲刈り、草刈りはナベさんの子どもの頃からの役割で、どんな時でも律儀に管理し続けてきた。
それが60年間続いた。田んぼをいよいよ手放したのは、つい3年前のことである。
何の因縁か、こうした不思議な運命の下に生まれ育ったナベさんであった。
両親が新井にやってきて過ごした時間より長い時間をそこで過ごしていることになる。
5反にも及ぶ田んぼの苗植え、稲刈り、草刈りはナベさんの子どもの頃からの役割で、どんな時でも律儀に管理し続けてきた。
それが60年間続いた。田んぼをいよいよ手放したのは、つい3年前のことである。
何の因縁か、こうした不思議な運命の下に生まれ育ったナベさんであった。

渡辺尚幸/スノーボードブランド〈PRANA PUNKS〉代表。デザイナー。アートディレクター。スノーボーダー(241所属)。
1958年、新潟県新井市生まれ。ロッククライマー、ラリードライバー、山岳ガイド、プロスノーボーダーなどの活動を経て、2004年、信州産の間伐材を芯材に使ったスノーボードのブランド〈Green Lab.〉を、中山一郎、中山二郎らと設立。グラフィックとディレクションを担当し、2015年、個人ブランド〈PRANA PUNKS SNOWBOARDING〉を設立。自らが作詞作曲を手がけるフォーク・ロックバンド「Fighting Farmers」ではヴォーカルとギターを担当。
-

FORESTER
Shigeaki Adachi
-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER
Kei Amano
-

BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER
Taiki Minakuchi
-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭 火付ぬ組
-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN
Yukihito Kanai
-

SAUNA BUILDER
nodaklaxonbebe