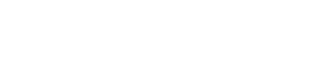Chapter 6 Vol.One
BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
Daisuke Soutome
五月女大介
栃木県芳賀郡茂木町を拠点とするひとりの竹細工職人が注目を集めている。五月女大介、1980年生まれ。かつてDJとして精力的な活動を続けていた彼は、茂木町の里山で妻と暮らしながら、これからの生き方について思考し、実践している。人と自然の関係を結び直そうというその壮大なヴィジョンに文筆家の大石始が迫る。
栃木県南東部に位置する茂木町をめざし、東京から常磐自動車道を北上する。友部ICを降りるとそれまで踏ん張っていた黒雲からしとしとと小雨が降り始め、茂木町に到着するころには本降りになっていた。宇都宮まで車で1時間ほどということもあって茂木町は宇都宮への通勤圏内に入るが、低山と田んぼが交互に広がるその長閑な光景は、ビルが立ち並ぶ宇都宮の中心部とはまったく別物だ。
茂木町に入り、さらに数分。里山の麓に佇む五月女大介くんと尚子さんの自宅に到着した。車を庭に停め、サイドブレーキを引くと、エンジン音に気づいた大介くんがやってきた。
「大石さん、おひさしぶりです」
作務衣姿の大介くんと握手を交わす。彼とこうやって会うのは10年ぶりぐらいだろうか。柔らかな笑顔は以前と何ひとつ変わっていない。続けて彼のパートナーである尚子さんも紹介していただく。尚子さんとは初対面だが、不思議と初めて会う感じがしない。
茂木町に入り、さらに数分。里山の麓に佇む五月女大介くんと尚子さんの自宅に到着した。車を庭に停め、サイドブレーキを引くと、エンジン音に気づいた大介くんがやってきた。
「大石さん、おひさしぶりです」
作務衣姿の大介くんと握手を交わす。彼とこうやって会うのは10年ぶりぐらいだろうか。柔らかな笑顔は以前と何ひとつ変わっていない。続けて彼のパートナーである尚子さんも紹介していただく。尚子さんとは初対面だが、不思議と初めて会う感じがしない。

竹細工職人である大介くんは、自宅兼工房「かごめらぼ」を拠点に創作活動を続けている。屋号は「伍竹庵」。彼の性格が現れた丁寧な作りのざるや籠の熱心なファンは多く、県外からも多くの人々がここにやってくる。
僕が大介くんと初めて会ったのは15年ほど前のことだ。そのときの彼は竹細工職人ではなく、JAHTOMEという名のDJとして都内を中心に活動していた。CHAMPION BASSというDJクルーの一員としても活動していた彼がプレイしていたのはジャングルやダブといった重低音が売り物の音楽。物静かな現在の彼からは当時の姿を想像することもできないだろう。
僕が大介くんと初めて会ったのは15年ほど前のことだ。そのときの彼は竹細工職人ではなく、JAHTOMEという名のDJとして都内を中心に活動していた。CHAMPION BASSというDJクルーの一員としても活動していた彼がプレイしていたのはジャングルやダブといった重低音が売り物の音楽。物静かな現在の彼からは当時の姿を想像することもできないだろう。

そのころ彼のことを「大介くん」と呼ぶ仲間はほとんどいなかったし、実際、僕も彼を「JAHTOMEくん」と呼んでいた。だが、現在、茂木町で彼のことをそう呼ぶ人はいない。ここでの彼は「都内のアンダーグラウンドクラブで重低音を鳴り響かせていたDJのJAHTOMEくん」ではなく、「竹細工職人の大介くん」として知られているのだ(なので、この記事では彼のことを「JAHTOMEくん」ではなく「大介くん」と書く)。
大介くんがいつも顔を合わせていた東京の夜の世界から突然姿を消したのは、東日本大震災から1年ほど後のことだった。地元の栃木に戻り、畑仕事に精を出しているらしいという風の噂を聞いたが、クラブで会う友人たちのなかでも彼は一際シリアスで繊細なところがあったので、突然の方向転換に驚くことはなかった。東日本大震災のあと、多くの友人たちが東京を離れていったし、きっと大介くんも思うところあって帰郷したのだろう。直接顔を合わせてそのことについて話を聞く機会はなかったけれど、彼の心情がなんとなく理解できる気がした。
だが、畑をやっていたはずの大介くんはいつの間にか竹細工の職人となり、茂木町の里山へと移住。近年ではメディアに取り上げられる機会も多く、SNSにはたびたび大介くんの活動を紹介する記事やテレビ番組の情報が流れてきた。 東京の生活に疲れ、田舎でのんびりとした暮らしを送る元DJの竹細工職人――。大介くんのことをある種のステレオタイプと共に語ることもできるだろう。だが、ネット経由で伝わってくる発言からすると、彼が東京から離れた理由は「東京の生活に疲れた」というだけではなさそうなのだ。SNSを通して知る彼の活動からは、今後の人生を送るうえでの何か壮大なヴィジョンのようなものが見え隠れした。僕の目には、かつて都内のアンダーグラウンドクラブでDJとして活動しながら自由な生き方を求めていた大介くんが、都心から離れた茂木町の地で――少しずつ、具体的なやり方で――何かを変えようとしているように映ったのだ。
東京の生活に疲れ、田舎でのんびりとした暮らしを送る元DJの竹細工職人――。大介くんのことをある種のステレオタイプと共に語ることもできるだろう。だが、ネット経由で伝わってくる発言からすると、彼が東京から離れた理由は「東京の生活に疲れた」というだけではなさそうなのだ。SNSを通して知る彼の活動からは、今後の人生を送るうえでの何か壮大なヴィジョンのようなものが見え隠れした。僕の目には、かつて都内のアンダーグラウンドクラブでDJとして活動しながら自由な生き方を求めていた大介くんが、都心から離れた茂木町の地で――少しずつ、具体的なやり方で――何かを変えようとしているように映ったのだ。
聞きたいことは山ほどあった。現在の活動の背景にどんな思いがあるのか。彼のヴィジョンとはどのようなものなのか。そもそもなぜ彼は突如東京から消えたのか。10年間の空白を埋めるため、僕は彼が住む茂木町にやってきたのだった。
大介くんがいつも顔を合わせていた東京の夜の世界から突然姿を消したのは、東日本大震災から1年ほど後のことだった。地元の栃木に戻り、畑仕事に精を出しているらしいという風の噂を聞いたが、クラブで会う友人たちのなかでも彼は一際シリアスで繊細なところがあったので、突然の方向転換に驚くことはなかった。東日本大震災のあと、多くの友人たちが東京を離れていったし、きっと大介くんも思うところあって帰郷したのだろう。直接顔を合わせてそのことについて話を聞く機会はなかったけれど、彼の心情がなんとなく理解できる気がした。
だが、畑をやっていたはずの大介くんはいつの間にか竹細工の職人となり、茂木町の里山へと移住。近年ではメディアに取り上げられる機会も多く、SNSにはたびたび大介くんの活動を紹介する記事やテレビ番組の情報が流れてきた。

聞きたいことは山ほどあった。現在の活動の背景にどんな思いがあるのか。彼のヴィジョンとはどのようなものなのか。そもそもなぜ彼は突如東京から消えたのか。10年間の空白を埋めるため、僕は彼が住む茂木町にやってきたのだった。

「かごめらぼ」の大広間には小さな音でアコースティックギターのインストが流れていた。窓の外では大粒の雨が木々に降り注ぎ、サワサワと音を立てている。暖かいギターの音色が雨音と混ざり合い、優しい音環境を作り出している。彼の部屋にもはやDJ用のミキサーはないけれど、BGMのセレクションには大介くんの趣味の良さが現れていた。竹細工の作業スペースとなっている床の間の一角では猫のキラちゃんが気持ちよさそうに寝転んでいて、ときどきニャーと伸びをしては、ふたたび眠りに落ちてゆく。

話はまず、大介くんの生い立ちを聞くところから始まった。
大介くんの生まれは栃木県東部にあたる那須烏山市。1歳までそこで過ごし、その後は両親が購入した宇都宮郊外の家で高校生まで育った。いわば生粋の栃木っ子だ。
五月女家は代々栃木の家系らしく、父方の先祖の墓は那須烏山にある。大介くんによると「祖父は農業をやりながら川船で鮎や鰻をとりながら生活していました。農家であり、漁師であり、冬は竹を編んでいた」らしい。幼少時代に目の当たりにした自然と共に生きる祖父の姿は、のちに大介くんのめざすものとなっていく。
彼が高校時代まで過ごした宇都宮の地は周囲に雑木林が点在し、少し足を伸ばせば水田が広がるという自然豊かな場所だった。大介くんの父親はサラリーマンだったが、定年後は農業に精を出した。
DJを初めたのは90年代、20歳前後のことだった。東京の美大で空間演出デザインを学んでいたが、「卒業後、就活もしないでクラブという違う空間にはまってしまった(笑)」。僕が彼と出会ったのはそれから数年後、DJとして精力的な活動を展開していた時期にあたる。
僕にはひとつ気になる点があった。川船で鮎や鰻をとりながら生活する祖父の姿を幼少時代から目の当たりにし、農業にも近いところで育った大介くんは、煙が渦巻く都会の地下クラブに何を求めていたのだろうか。僕にはそのふたつの世界の間にはあまりにも大きなギャップがあるように思えたが、そのギャップは大介くんのなかの迷いとも繋がっていた。
「十代のころは栃木が嫌いだったんですよ。中途半端に田舎で、全然面白くない町だと。中学生ぐらいから東京で遊んでいたし、刺激を求めて都会に出たようなもんで。自分と同じように音楽を通して自己表現している人たちや、そういうカルチャーの中に身を置きたかったんです。
ただ、迷いは少しありましたね。東京にいるとすごく消費が早くて、お金を稼ぐのでいっぱいいっぱいで。地に足をつけて生きている感じがあまりなかった。東京での暮らしがずっと続くとも思っていなかったし、いつかは変わらなきゃと思っていたんですよ」
五月女家は代々栃木の家系らしく、父方の先祖の墓は那須烏山にある。大介くんによると「祖父は農業をやりながら川船で鮎や鰻をとりながら生活していました。農家であり、漁師であり、冬は竹を編んでいた」らしい。幼少時代に目の当たりにした自然と共に生きる祖父の姿は、のちに大介くんのめざすものとなっていく。
彼が高校時代まで過ごした宇都宮の地は周囲に雑木林が点在し、少し足を伸ばせば水田が広がるという自然豊かな場所だった。大介くんの父親はサラリーマンだったが、定年後は農業に精を出した。
DJを初めたのは90年代、20歳前後のことだった。東京の美大で空間演出デザインを学んでいたが、「卒業後、就活もしないでクラブという違う空間にはまってしまった(笑)」。僕が彼と出会ったのはそれから数年後、DJとして精力的な活動を展開していた時期にあたる。
僕にはひとつ気になる点があった。川船で鮎や鰻をとりながら生活する祖父の姿を幼少時代から目の当たりにし、農業にも近いところで育った大介くんは、煙が渦巻く都会の地下クラブに何を求めていたのだろうか。僕にはそのふたつの世界の間にはあまりにも大きなギャップがあるように思えたが、そのギャップは大介くんのなかの迷いとも繋がっていた。
「十代のころは栃木が嫌いだったんですよ。中途半端に田舎で、全然面白くない町だと。中学生ぐらいから東京で遊んでいたし、刺激を求めて都会に出たようなもんで。自分と同じように音楽を通して自己表現している人たちや、そういうカルチャーの中に身を置きたかったんです。
ただ、迷いは少しありましたね。東京にいるとすごく消費が早くて、お金を稼ぐのでいっぱいいっぱいで。地に足をつけて生きている感じがあまりなかった。東京での暮らしがずっと続くとも思っていなかったし、いつかは変わらなきゃと思っていたんですよ」

2011年3月、東日本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所事故は大介くんにとっての転期となった。
東日本大震災の起きた日、僕は南米のコロンビアにいた。約2か月間、コロンビア各地を周り、帰国したのは4月初旬。その直後、東京の行きつけの酒場で大介くんと交わした会話をはっきりと覚えている。帰国してからしばらく浦島太郎状態だった僕は、マスクを着用していた大介くんに遭遇。そしてこんな会話をする。
「JAHTOMEくん、久しぶり。マスクなんか付けてどうしたの? 風邪?」
「……放射能対策ですよ」
大介くんは東日本大震災と原発事故のことに真摯に向き合い、その後の人生をどう歩もうか思案している最中だった。コロンビア帰りで浮かれた僕との温度差ははっきりとしていて、彼の目から見ると当時の僕はひどく滑稽に映ったことだろう。今の大介くんにそのことを伝えると「そんなこと、ありましたっけ(笑)」と笑うが、あのときの彼はいくらか呆れているように見えたものだった。
「そのころ(杉並区の)善福寺に住んでたんですけど、近くの青梅街道をたくさんの人たちが歩いて帰っているのを見たり、震災の次の日、スーパーやホームセンターに行列ができているのを見たりして、これはもう続かないと思いました。それで名古屋の友達の家に避難しました。とりあえず1週間だけでも西に行こうと」
震災から1年後、大介くんは宇都宮郊外の実家に戻ることを決意する。「今後自分はどのように生きていくのか」という課題を背負ったまま、東京の部屋を引き払ってしまうのだ。そうしたなかでテーマとして浮かび上がってきたのが農業だった。
「震災の次の日にスーパーの行列を見たわけですけど、食べ物は土があればできるし、とりあえず土があるところに移住しようと。それで土地勘のある宇都宮に戻りました。震災前に農業をやろうと考えたこともなかったんですけどね」
幼少時代から自然と共に生きる祖父の姿を見てきた大介くんにとって、農業とは決して憧れでもなければ理想でもない。切実な問題から浮かび上がってきた「生きるための手段」だった。
「当時はとにかくお金が全然なかったし、むしろ借金があったぐらいだったんで、資本ゼロでできる仕事を考えなきゃいけなかったんです。農業を生業としようというより、自分の健康のため、家族や友達の健康のために、小さくてもいいから作ろうと。
あとは、東京に10年以上いて、自然のセンス・オブ・ワンダーみたいなものを忘れちゃってたんですよね。小さなものでもいいから自然に触れる時間が欲しかったんです。それが自分の魂の癒しになるんじゃないかって。だからね……ちょっと病んでたんだと思います(笑)」 2012年4月9日、大介くんは日々の農作業を綴る「不耕起栽培記」と題したブログをスタートさせる。不耕起栽培とは水田や田畑を耕さないまま農作物を栽培する農法で、彼は実家の隣のスペースを耕し、この不耕起栽培で農作物を収穫しようと試みる。農薬や肥料を使った通常の農法ではなく、この栽培方法を選んだのはなぜだったのだろうか。
2012年4月9日、大介くんは日々の農作業を綴る「不耕起栽培記」と題したブログをスタートさせる。不耕起栽培とは水田や田畑を耕さないまま農作物を栽培する農法で、彼は実家の隣のスペースを耕し、この不耕起栽培で農作物を収穫しようと試みる。農薬や肥料を使った通常の農法ではなく、この栽培方法を選んだのはなぜだったのだろうか。
「いろいろありますけど、結局土を痛めたくなかったわけですよ。農薬を使えば虫もいなくなって、土の中の多様性が失われていく。農業を仕事にしようと思ったらそういうやり方にしなきゃいけなかったでしょうけど、自分の楽しみというか、目的がセンス・オブ・ワンダーに触れることだったんで、だったら不耕起栽培でやろうと」
東日本大震災の起きた日、僕は南米のコロンビアにいた。約2か月間、コロンビア各地を周り、帰国したのは4月初旬。その直後、東京の行きつけの酒場で大介くんと交わした会話をはっきりと覚えている。帰国してからしばらく浦島太郎状態だった僕は、マスクを着用していた大介くんに遭遇。そしてこんな会話をする。
「JAHTOMEくん、久しぶり。マスクなんか付けてどうしたの? 風邪?」
「……放射能対策ですよ」
大介くんは東日本大震災と原発事故のことに真摯に向き合い、その後の人生をどう歩もうか思案している最中だった。コロンビア帰りで浮かれた僕との温度差ははっきりとしていて、彼の目から見ると当時の僕はひどく滑稽に映ったことだろう。今の大介くんにそのことを伝えると「そんなこと、ありましたっけ(笑)」と笑うが、あのときの彼はいくらか呆れているように見えたものだった。
「そのころ(杉並区の)善福寺に住んでたんですけど、近くの青梅街道をたくさんの人たちが歩いて帰っているのを見たり、震災の次の日、スーパーやホームセンターに行列ができているのを見たりして、これはもう続かないと思いました。それで名古屋の友達の家に避難しました。とりあえず1週間だけでも西に行こうと」
震災から1年後、大介くんは宇都宮郊外の実家に戻ることを決意する。「今後自分はどのように生きていくのか」という課題を背負ったまま、東京の部屋を引き払ってしまうのだ。そうしたなかでテーマとして浮かび上がってきたのが農業だった。
「震災の次の日にスーパーの行列を見たわけですけど、食べ物は土があればできるし、とりあえず土があるところに移住しようと。それで土地勘のある宇都宮に戻りました。震災前に農業をやろうと考えたこともなかったんですけどね」
幼少時代から自然と共に生きる祖父の姿を見てきた大介くんにとって、農業とは決して憧れでもなければ理想でもない。切実な問題から浮かび上がってきた「生きるための手段」だった。
「当時はとにかくお金が全然なかったし、むしろ借金があったぐらいだったんで、資本ゼロでできる仕事を考えなきゃいけなかったんです。農業を生業としようというより、自分の健康のため、家族や友達の健康のために、小さくてもいいから作ろうと。
あとは、東京に10年以上いて、自然のセンス・オブ・ワンダーみたいなものを忘れちゃってたんですよね。小さなものでもいいから自然に触れる時間が欲しかったんです。それが自分の魂の癒しになるんじゃないかって。だからね……ちょっと病んでたんだと思います(笑)」

「いろいろありますけど、結局土を痛めたくなかったわけですよ。農薬を使えば虫もいなくなって、土の中の多様性が失われていく。農業を仕事にしようと思ったらそういうやり方にしなきゃいけなかったでしょうけど、自分の楽しみというか、目的がセンス・オブ・ワンダーに触れることだったんで、だったら不耕起栽培でやろうと」

農薬も肥料も使わないということは、農作物の成長を思うようにコントロールできないということも意味する。そもそも大介くんが最初に不耕起栽培を試みた実家横のスペースは、もともとただの空き地。そんな場所で経験のない不耕起栽培に挑むというのはなかなか大変だったのではないだろうか?
「いやー、もう楽しくてしょうがなかった(笑)。実家に帰ってきたときあまりに金がなかったんで、週5日、看板屋さんで働いてたんですよ。だから、朝と夕方しか畑仕事ができなかったんです。それでもすごくよくできたし、十分満足でした」 2012年8月28日、大介くんはそれまでDJとしての出演情報などを告知していた音楽ブログでこんなことを書いている。
とにかく本気で、今、このときに「農」を学びたいと思った。農家になりたい訳ではない。なぜ「今」なのかと言えばそれがこれからの生き方の1つの基軸になると直感しているからです。
これからの生き方の基軸――この段階で大介くんにとっての農業とは、生きる糧としての農作物を生産するだけでなく、震災後の世界で生きていくためのヴィジョンとも結びついていた。
「地球全体で見たら都市が占める面積ってわずかなものだし、人間の歴史で考えてみても、自然と一緒に生きてきた時間のほうが遥かに長いわけじゃないですか。その中で食べ物を作ったり、道具を作ったりしてきたわけで、自分ももう1回地球人としてちゃんと生きていきたいなと思ったんです」
自然と共に生きる地球人としての暮らし。その意義を声高に訴えるのではなく、まずは自分が実践してみる。大介くんは何よりも実践の人であった。 「社会を変えたいと思ってデモに行ったこともありましたけど、なんか虚無感だけが残ったんですよ。だから、まずは自分で手を動かさないと駄目だなと思っていました。そう思えたのは祖父が手を動かしているのを見ていたからかもしれませんね。小学生の僕の目には、自然と共に生きる祖父の暮らしがすごく豊かに映ったんです。すごく楽しくて幸せだなと。それを自分の人生の中で作りたいなと思ったんです」
「社会を変えたいと思ってデモに行ったこともありましたけど、なんか虚無感だけが残ったんですよ。だから、まずは自分で手を動かさないと駄目だなと思っていました。そう思えたのは祖父が手を動かしているのを見ていたからかもしれませんね。小学生の僕の目には、自然と共に生きる祖父の暮らしがすごく豊かに映ったんです。すごく楽しくて幸せだなと。それを自分の人生の中で作りたいなと思ったんです」
窓の外ではあいかわらず雨がしとしとと降り続けていた。僕の生活では常に鳴り響いている車のエンジン音がまったく聴こえないことに気づいた。その代わりに時たま野鳥が涼しげな鳴き声を響かせている。
大介くんは尚子さんが入れてくれたお茶に口をつけ、こう呟いた。
「だからね、祖父のような生活を送ることで自由が欲しかったのかもしれない。社会の枠に収まるのがずっといやで、変に抗ったり、就活しなかったりしてきたわけですけど」
自由というのは実に難しい。自由を求めて閉鎖的な村社会を飛び出してみたところで、都市のコミュニティーにおいても小さな村社会が構築されていることを知り、愕然とすることもあるだろう。現代社会においては自由と不自由の境界線はひどく曖昧で、僕もときたま自分がどちら側にいるのかわからなくなることがある。
「いやー、もう楽しくてしょうがなかった(笑)。実家に帰ってきたときあまりに金がなかったんで、週5日、看板屋さんで働いてたんですよ。だから、朝と夕方しか畑仕事ができなかったんです。それでもすごくよくできたし、十分満足でした」 2012年8月28日、大介くんはそれまでDJとしての出演情報などを告知していた音楽ブログでこんなことを書いている。
とにかく本気で、今、このときに「農」を学びたいと思った。農家になりたい訳ではない。なぜ「今」なのかと言えばそれがこれからの生き方の1つの基軸になると直感しているからです。
これからの生き方の基軸――この段階で大介くんにとっての農業とは、生きる糧としての農作物を生産するだけでなく、震災後の世界で生きていくためのヴィジョンとも結びついていた。
「地球全体で見たら都市が占める面積ってわずかなものだし、人間の歴史で考えてみても、自然と一緒に生きてきた時間のほうが遥かに長いわけじゃないですか。その中で食べ物を作ったり、道具を作ったりしてきたわけで、自分ももう1回地球人としてちゃんと生きていきたいなと思ったんです」
自然と共に生きる地球人としての暮らし。その意義を声高に訴えるのではなく、まずは自分が実践してみる。大介くんは何よりも実践の人であった。

窓の外ではあいかわらず雨がしとしとと降り続けていた。僕の生活では常に鳴り響いている車のエンジン音がまったく聴こえないことに気づいた。その代わりに時たま野鳥が涼しげな鳴き声を響かせている。
大介くんは尚子さんが入れてくれたお茶に口をつけ、こう呟いた。
「だからね、祖父のような生活を送ることで自由が欲しかったのかもしれない。社会の枠に収まるのがずっといやで、変に抗ったり、就活しなかったりしてきたわけですけど」
自由というのは実に難しい。自由を求めて閉鎖的な村社会を飛び出してみたところで、都市のコミュニティーにおいても小さな村社会が構築されていることを知り、愕然とすることもあるだろう。現代社会においては自由と不自由の境界線はひどく曖昧で、僕もときたま自分がどちら側にいるのかわからなくなることがある。

大介くんにとっては、自分自身で食べるものを畑や川から得る祖父の暮らしこそが自由を体現するものだった。そこにおける「自由」とは貨幣経済に牛耳られた社会から離れることで得られる自由であり、経済的に自立するということでもあった。大介くんは自問自答を繰り返しながら、都内のアンダーグラウンドなクラブにはなかった「自由」を追い求めていったのだ。
大介くんが故郷に戻ったのが2012年3月。農業と看板屋のダブルワークを続けるなかで、彼はもうひとつの表現手段を見つけることになる。それが祖父が漁の合間にやっていた竹細工だったのだ。
大介くんが故郷に戻ったのが2012年3月。農業と看板屋のダブルワークを続けるなかで、彼はもうひとつの表現手段を見つけることになる。それが祖父が漁の合間にやっていた竹細工だったのだ。

五月女 大介/竹細工職人。竹細工工房〈伍竹庵〉庵主。
1980年、栃木県生まれ。武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒。東京で音楽関係の仕事に従事した後、2011年の東日本大震災をきっかけに栃木へUターン。半農半Xを志す過程で竹細工に出会い、伝統工芸士・八木澤正に師事。3年間の内弟子修行の後、八溝山脈の麓・茂木町に工房を構え、伍竹庵として独立。同年、妻・尚子と結婚。制作と並行して、自然に根ざした暮らしと仕事の在り方や手仕事をワークショップやコミュニティ活動を通じて発信している。
-

FORESTER
Shigeaki Adachi
-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER
Kei Amano
-

BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER
Taiki Minakuchi
-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭 火付ぬ組
-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN
Yukihito Kanai
-

SAUNA BUILDER
nodaklaxonbebe