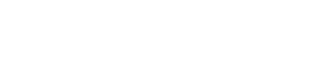Chapter 6 Vol.Three
BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
Daisuke Soutome
五月女大介
竹細工職人として独立するにあたって、五月女大介は栃木県芳賀郡茂木町の里山へ移住。みずからの手で古民家を改修し、理想の拠点づくりに精を出す。妻という仲間も増え、里山の麓で新たなヴィジョンをひとつひとつ実践していく。竹細工というフィールドを飛び超え、「水の杜(もり)」再生へと挑むその活動に迫る。
2016年、五月女大介くんは竹細工職人として独り立ちするにあたって、工房となる場所を探していた。条件のひとつが「竹林が近くにあること」。それだけ聞くとそこそこハードルが高いようにも感じてしまうけれど、大介くんは空き家バンクで物件を探し始めて一軒目で竹林まで歩いて10秒という現在の住まいと出会う。まさに運命の出会いというか、山の神のお導きというか。竹細工職人としてはこれ以上の場所はそうそうないだろう。
僕が茂木町にやってきたのはこの取材のときが初めてだったが、里山と水田が続く風光明媚な風景に一瞬で魅せられてしまった。大介くんたちの話によると、近年はそうした環境に魅せられた茂木町への移住者も増えているのだという。しかもものづくりに関わる人や自然栽培農家が集まっているのだとか。大介くんはこう話す。
「茂木町は宇都宮や笠間まで車で40分ぐらいで行けるし、海もそう遠くないですからね。僕らみたいなものづくりに携わる人たちもいるし、勤め人にとっても不便じゃない。子育てもできる。環境がいいんですよ。移住希望者は栃木でもかなり多いみたいです」
尚子さんも「ここに移住してくるのは里山に憧れがある人たちが多いですよね」と話す。ここに住み始めて6年以上が経つ五月女夫妻もまた、今もなおこの環境に惚れ込んでいるようだ。大介くんがこう続ける。
「初めてここに来たとき、電線が見えないことに感動したんですよ。今までは自然より人が多い環境で暮らしてきたんですけど、ここは自然が圧倒的で、そのなかで住まわせてもらってるという感覚なんですよ。それがいいなと思って。季節の移り変わりがすごく感じられますしね」 大介くんはそう話すと、窓の外に視線を向けた。季節は5月初旬、新緑が青々と広がっている。暑い夏がやってくると、里山はさらにギラギラと生命の輝きを増す。鮮やかな紅葉の秋、雪が散らつく冬。その美しさもきっと格別のものだろう。
大介くんはそう話すと、窓の外に視線を向けた。季節は5月初旬、新緑が青々と広がっている。暑い夏がやってくると、里山はさらにギラギラと生命の輝きを増す。鮮やかな紅葉の秋、雪が散らつく冬。その美しさもきっと格別のものだろう。
「茂木は森林の面積が65パーセントとか70パーセントぐらいで、日本の国土とほぼ一緒だそうなんですね。町としてもそのポテンシャルを活かしてほしいと思いますけどね」
47都道府県の魅力度ランキングで栃木と茨城は最下位争いをしているらしいが、まったくひどい話である。どこの何を見てそんな勝手なランキングづけをしているのだろうか。少なくとも同じようなチェーン店が立ち並ぶ中途半端な都市部などよりは、色彩鮮やかな茂木町のほうがよほど魅力的に思える。
先述したように、大介くんが茂木町に移住したのは2016年のことである。ただし、すぐに現在の住環境が整えられたわけではなかった。その3年前まではひとりの老婆が住んでいたらしく、彼女の死後は空き家になっていたという。そのため、家の中は痛み放題。大介くんは現在の形になるまで大規模なリフォームを完全DIYで施すことになる。尚子さんがやってくるまではたったひとりで古民家をこつこつ改築していたというから、なんとも大介くんらしい。
僕が茂木町にやってきたのはこの取材のときが初めてだったが、里山と水田が続く風光明媚な風景に一瞬で魅せられてしまった。大介くんたちの話によると、近年はそうした環境に魅せられた茂木町への移住者も増えているのだという。しかもものづくりに関わる人や自然栽培農家が集まっているのだとか。大介くんはこう話す。
「茂木町は宇都宮や笠間まで車で40分ぐらいで行けるし、海もそう遠くないですからね。僕らみたいなものづくりに携わる人たちもいるし、勤め人にとっても不便じゃない。子育てもできる。環境がいいんですよ。移住希望者は栃木でもかなり多いみたいです」
尚子さんも「ここに移住してくるのは里山に憧れがある人たちが多いですよね」と話す。ここに住み始めて6年以上が経つ五月女夫妻もまた、今もなおこの環境に惚れ込んでいるようだ。大介くんがこう続ける。
「初めてここに来たとき、電線が見えないことに感動したんですよ。今までは自然より人が多い環境で暮らしてきたんですけど、ここは自然が圧倒的で、そのなかで住まわせてもらってるという感覚なんですよ。それがいいなと思って。季節の移り変わりがすごく感じられますしね」

「茂木は森林の面積が65パーセントとか70パーセントぐらいで、日本の国土とほぼ一緒だそうなんですね。町としてもそのポテンシャルを活かしてほしいと思いますけどね」
47都道府県の魅力度ランキングで栃木と茨城は最下位争いをしているらしいが、まったくひどい話である。どこの何を見てそんな勝手なランキングづけをしているのだろうか。少なくとも同じようなチェーン店が立ち並ぶ中途半端な都市部などよりは、色彩鮮やかな茂木町のほうがよほど魅力的に思える。
先述したように、大介くんが茂木町に移住したのは2016年のことである。ただし、すぐに現在の住環境が整えられたわけではなかった。その3年前まではひとりの老婆が住んでいたらしく、彼女の死後は空き家になっていたという。そのため、家の中は痛み放題。大介くんは現在の形になるまで大規模なリフォームを完全DIYで施すことになる。尚子さんがやってくるまではたったひとりで古民家をこつこつ改築していたというから、なんとも大介くんらしい。

これからの時代、どのように生きていくべきか。そうした壮大なヴィジョンを持って栃木へとUターンした大介くんにとって、里山の古民家は自身のヴィジョンを実現する場所でもあった。
そのため、最初からガスも冷蔵庫もなし。電気は通っているものの、あくまでも最小限のものだ。米を炊くかまどは、益子で使われていた登り窯の耐火レンガを譲り受け、ひとつひとつモルタルで積み上げて漆喰で仕上げた。日々の調理をするシンクも大介くんの自作である。ふと上を見上げると、お湯を沸かすために起こしていた火が煙となって天井のほうへと吸い上げられている。大介くんはこう話す。
「煙突が屋根裏を通ってるんで、暖気が上に貯まるんですよ。それをシーリングファンでかき混ぜると家中全部温まるんです。夏は逆にファンを上向きにしています。向こう側に小さな窓をつけていて、暖気が横風で抜けるようにしているんですよ」 ちなみにシーリングファンはヤフオクで購入。そうやってネットのいいところは利用しているわけで、現代的でハイブリッドなライフスタイルを実践しているのだ。
ちなみにシーリングファンはヤフオクで購入。そうやってネットのいいところは利用しているわけで、現代的でハイブリッドなライフスタイルを実践しているのだ。
驚いたのは水道や下水道のシステム。もともとこの家に住んでいた老婆は下水道を利用していたが、大介くんたちは下水道とは別に新たな水の流れを自分たちで構築してしまったというのだ。そのシステムを大介くんに解説してもらおう。
「水道水は普通の浄水も引いてるんですけど、プラス、雨水を貯めて野菜の水やりや洗い物で使っています。下水は繋いでいなくて、庭の大きな木の根本に自分がすっぽり入るぐらいの大穴を掘って、そこに枝と炭と落ち葉を組んでそこに流しています。近くにカエデの木などが生えているので、その根や微生物が分解してくれるんですよ。いずれ浄水のかわりに山の水を引けたらと思っています」
そのため、最初からガスも冷蔵庫もなし。電気は通っているものの、あくまでも最小限のものだ。米を炊くかまどは、益子で使われていた登り窯の耐火レンガを譲り受け、ひとつひとつモルタルで積み上げて漆喰で仕上げた。日々の調理をするシンクも大介くんの自作である。ふと上を見上げると、お湯を沸かすために起こしていた火が煙となって天井のほうへと吸い上げられている。大介くんはこう話す。
「煙突が屋根裏を通ってるんで、暖気が上に貯まるんですよ。それをシーリングファンでかき混ぜると家中全部温まるんです。夏は逆にファンを上向きにしています。向こう側に小さな窓をつけていて、暖気が横風で抜けるようにしているんですよ」

驚いたのは水道や下水道のシステム。もともとこの家に住んでいた老婆は下水道を利用していたが、大介くんたちは下水道とは別に新たな水の流れを自分たちで構築してしまったというのだ。そのシステムを大介くんに解説してもらおう。
「水道水は普通の浄水も引いてるんですけど、プラス、雨水を貯めて野菜の水やりや洗い物で使っています。下水は繋いでいなくて、庭の大きな木の根本に自分がすっぽり入るぐらいの大穴を掘って、そこに枝と炭と落ち葉を組んでそこに流しています。近くにカエデの木などが生えているので、その根や微生物が分解してくれるんですよ。いずれ浄水のかわりに山の水を引けたらと思っています」

私たちは水のことをさほど意識せずに生活を送っている。蛇口をひねればすぐに水が出るし、キッチンやトイレから流れ出る汚水がどこに向かっているか、使うたびに考えるという人はいないだろう。だが、大介くんたちは水のことを強く意識し、そこに今後のヴィジョンを重ね合わせている。後述するように、水のことを考えるということは自分たちの住む土地の環境を考えるということであり、自然との共存について考えるということでもあるのだ。
そうした意識とは、大介くんだけのものでもない。尚子さんも長年そうした生き方について模索し、実践の機会を窺っていた。尚子さんはこう話す。
「大介くんとは目指す生き方が一緒だったんです。私自身、ずっと世界のエコビレッジやトランジションタウンの活動を通して、地に足のついた暮らし方を学んではいたんですけど、自分自身の実践っていうのはまだまだ。憧れてたんですね。バリ島で竹ガムランの研究をしていたときも目の前にニワトリや豚が走り回ってるような環境で暮らしていたんですけど、研究のためというよりはこの暮らしのための学びだったのかなと思って(笑)」
そうした意識とは、大介くんだけのものでもない。尚子さんも長年そうした生き方について模索し、実践の機会を窺っていた。尚子さんはこう話す。
「大介くんとは目指す生き方が一緒だったんです。私自身、ずっと世界のエコビレッジやトランジションタウンの活動を通して、地に足のついた暮らし方を学んではいたんですけど、自分自身の実践っていうのはまだまだ。憧れてたんですね。バリ島で竹ガムランの研究をしていたときも目の前にニワトリや豚が走り回ってるような環境で暮らしていたんですけど、研究のためというよりはこの暮らしのための学びだったのかなと思って(笑)」

ただし、ふたりの実践とは決して気楽なものではない。お茶を一杯飲むためにはわざわざ時間をかけて火を起こさないといけないし、冷えたビールやキンキンのアイスが詰まった冷蔵庫があるわけでもない。極めてストイックなものともいえるだろう。
「最初は大変なんじゃないかと思ってましたけど、やればなんとかなる(笑)。こういうことをずっとやりたかったし、楽しいんです。家のことをやっていると徐々に庭のことが気になってきて、そのうち山のことを見るようになって、いまは地域のことを見るようになりました」
その言葉通り、大介くんたちの「実践」はやがて家を飛び出し、目の前に広がる里山の世界へと拡張していくのだ。
ここで大介くんたちの住む尾軽集落について触れておきたい。
尾軽集落の歴史は古い。なにせ集落のある里山にはかつて千本城という山城が築かれており、那須資隆の子である千本十郎為隆がその山城を築城したのは建久8年(1197年)と伝えられているのだ。そう考えてみると、およそ800年以上の時間が流れている計算になる。現在でも土塁や堀切などが遺構として残っており、山城マニアにはよく知られた場所らしい。
山城とは山の地形を活かして作られた城のことを指す。敵軍から身を守るのに適しているだけでなく、そこには生活に必要な自然環境、何よりも水があった。大介くんいわく、千本城のあった里山からは現在も水が沸いているのだという。
「最初は大変なんじゃないかと思ってましたけど、やればなんとかなる(笑)。こういうことをずっとやりたかったし、楽しいんです。家のことをやっていると徐々に庭のことが気になってきて、そのうち山のことを見るようになって、いまは地域のことを見るようになりました」
その言葉通り、大介くんたちの「実践」はやがて家を飛び出し、目の前に広がる里山の世界へと拡張していくのだ。
ここで大介くんたちの住む尾軽集落について触れておきたい。
尾軽集落の歴史は古い。なにせ集落のある里山にはかつて千本城という山城が築かれており、那須資隆の子である千本十郎為隆がその山城を築城したのは建久8年(1197年)と伝えられているのだ。そう考えてみると、およそ800年以上の時間が流れている計算になる。現在でも土塁や堀切などが遺構として残っており、山城マニアにはよく知られた場所らしい。
山城とは山の地形を活かして作られた城のことを指す。敵軍から身を守るのに適しているだけでなく、そこには生活に必要な自然環境、何よりも水があった。大介くんいわく、千本城のあった里山からは現在も水が沸いているのだという。

「ここの山は不思議と四方八方から水が染み出してんですよね。いわゆるコンコンと湧き出る湧水ではないんですけど、山からちょろちょろ染み出していて、ずっと枯れないんです。この山1個で多分ダム何個分かの水を保水してるんですよ。ここの水が巡って川に繋がり、やがて海へと注ぎ込まれるんです。
おそらく水があったから城を作ったということだと思います。山の恵みも取れるし、場所によっては断崖絶壁だから城に適していたんでしょうね」
ただし、その水は千本城のためだけに使われていたわけではなかった。大介くんが「里に暮らす人間たちもその水を利用できるようにしていたと思う」と推測するように、寛永年間に千本城が落城して以降も山の水は集落の人々に利用され、その習慣は近年まで続いていたのだという。尚子さんがこう話す。
「近所の人に話を聞いてみたら、高度経済成長期に入って水道事業が入る前はどこも山の水を取水して利用していたそうなんですよ。里山のシステムを使って昔の人は暮らしていたんです。井戸とか取水システムのタンクもあったみたいで、その形跡が出てくるんですよね。
でも、水道事業が入ってきた途端、みんな山の水は使わなくなって、一気に荒れてしまった。藪に覆われているし、水路もぐっちゃぐちゃで全然わからない状態。私たちはそういうものを少しずつ綺麗にしながら、山の水の流れを手入れするようになったんです」
そして大介くんは「僕らは杜(もり)になっていくプロセスを促してるんです」と続ける。
「杜」とは、単なる木の集合体である「森」とは異なり、神社やご神木など信仰対象を含む場所を指す。「鎮守の杜」という表現が使われるように、そこにはアニミズム的なイメージも込められている。ところが、水道や下水道が整備され、山中で採集していた山菜やキノコがスーパーで簡単に手に入るようになると、400年に渡って山城が築かれていた 「杜」は木の集合体と化した。
「集落でもおばあちゃんおじいちゃん世代はやっぱりすごいですね。山のどこに何の木が生えてるのか、すぐにわかりますもんね。すごいですよ、知識が。でも、団塊の世代の方たちはもう全然山に入らなくなっちゃったので山のことが全然分からないんです」
大介くんはそう嘆く。彼らがすごいのは、嘆くだけでなく、庭師である高田宏臣さんの著書などで勉強しながら水脈を整え、荒れ放題だった竹林や梅林を手入れし、里山をかつての「杜」の姿へと戻そうとしているのだ。
おそらく水があったから城を作ったということだと思います。山の恵みも取れるし、場所によっては断崖絶壁だから城に適していたんでしょうね」
ただし、その水は千本城のためだけに使われていたわけではなかった。大介くんが「里に暮らす人間たちもその水を利用できるようにしていたと思う」と推測するように、寛永年間に千本城が落城して以降も山の水は集落の人々に利用され、その習慣は近年まで続いていたのだという。尚子さんがこう話す。
「近所の人に話を聞いてみたら、高度経済成長期に入って水道事業が入る前はどこも山の水を取水して利用していたそうなんですよ。里山のシステムを使って昔の人は暮らしていたんです。井戸とか取水システムのタンクもあったみたいで、その形跡が出てくるんですよね。
でも、水道事業が入ってきた途端、みんな山の水は使わなくなって、一気に荒れてしまった。藪に覆われているし、水路もぐっちゃぐちゃで全然わからない状態。私たちはそういうものを少しずつ綺麗にしながら、山の水の流れを手入れするようになったんです」
そして大介くんは「僕らは杜(もり)になっていくプロセスを促してるんです」と続ける。
「杜」とは、単なる木の集合体である「森」とは異なり、神社やご神木など信仰対象を含む場所を指す。「鎮守の杜」という表現が使われるように、そこにはアニミズム的なイメージも込められている。ところが、水道や下水道が整備され、山中で採集していた山菜やキノコがスーパーで簡単に手に入るようになると、400年に渡って山城が築かれていた 「杜」は木の集合体と化した。
「集落でもおばあちゃんおじいちゃん世代はやっぱりすごいですね。山のどこに何の木が生えてるのか、すぐにわかりますもんね。すごいですよ、知識が。でも、団塊の世代の方たちはもう全然山に入らなくなっちゃったので山のことが全然分からないんです」
大介くんはそう嘆く。彼らがすごいのは、嘆くだけでなく、庭師である高田宏臣さんの著書などで勉強しながら水脈を整え、荒れ放題だった竹林や梅林を手入れし、里山をかつての「杜」の姿へと戻そうとしているのだ。

先に触れたように、彼らの住む里山には少なくとも800年以上の時が積み重なっている。大介くんが「もしかしたらもっと前からもしれませんよね。城ができる前から里山のシステムが存在していたかもしれないわけで」と話すように、彼らは1000年単位の時間の流れのなかに生きている。
僕の大好きなドキュメンタリー映画作家、小川紳介は山形県上山市の農村・牧野村を舞台に『1000年刻みの日時計 牧野村物語』(1987年)という一大傑作を作り上げた。その映画では農村の暮らしに執拗にカメラを向けながら、縄文時代から続く人々の営みが炙り出されている。大介くんたちもまた、1000年刻みの里山の歴史を土と水の側から見つめ、現代においてふたたび構築しようとしているのだ。なんとロマン溢れる試みだろうか。
「『山は負の遺産だ』といって、子供に引き継がせたくないから誰かに売り飛ばしてソーラーにしちゃうケースがよくあるんですよね。全然負の遺産なんかじゃないのに。山は宝ですよ」
大介くんはそう呟く。尚子さんによると茂木町や近隣の益子、那須烏山などではソーラーパネルが凄まじい勢いで増えているのだという。メガソーラーの先にあるヴィジョンとはいったい何なのだろうか。1000年後の未来から振り返ったとき、ただの鉄屑となっているだろうソーラーは何の役に立つのだろうか? 大介くんたちはまた、里山での体験をワークショップという形で訪れる人たちにシェアしている。茂木町に移住した当初、たったひとりでストイックに古民家を改築していたことを思うと、大きな違いだ。
「途中で気づいたんですけど、ここでの体験をシェアしたほうが楽しいんですよ。僕らがやっていることは素人に毛が生えたぐらいだけど、その学びをもっと得たい人もいるだろうし、僕らはお手伝いが必要なんですよね。お互いにとってそのほうがいいと思って、体験を共有していくっていうスタイルにだんだん変わってきました」
竹細工教室や水脈を整えるワークショップのほか、尚子さんの指導によるヨガ教室や創作舞のワークショップ、さらには石場建てのワークショップも行っている。石場建てとは古民家や寺社で見られる建築構法の一種。コンクリートの基礎の上に建物を組み上げていく現代の構法とは異なり、石場建ては礎石の上に直接柱を立てる。それでも数百年のあいだ倒れずにその形を残すこともあるというのだからすごい。大介くんたちはその構法を使って敷地内の納屋を改修し、いずれゲストが宿泊できるスペースにしようと考えている。大介くんはこう語る。
「石場建てって土を痛めないんですよ。なおかつ空気と水の流れを遮断しない家の建て方でもあって」
大介くんたちはまた、里山での体験をワークショップという形で訪れる人たちにシェアしている。茂木町に移住した当初、たったひとりでストイックに古民家を改築していたことを思うと、大きな違いだ。
「途中で気づいたんですけど、ここでの体験をシェアしたほうが楽しいんですよ。僕らがやっていることは素人に毛が生えたぐらいだけど、その学びをもっと得たい人もいるだろうし、僕らはお手伝いが必要なんですよね。お互いにとってそのほうがいいと思って、体験を共有していくっていうスタイルにだんだん変わってきました」
竹細工教室や水脈を整えるワークショップのほか、尚子さんの指導によるヨガ教室や創作舞のワークショップ、さらには石場建てのワークショップも行っている。石場建てとは古民家や寺社で見られる建築構法の一種。コンクリートの基礎の上に建物を組み上げていく現代の構法とは異なり、石場建ては礎石の上に直接柱を立てる。それでも数百年のあいだ倒れずにその形を残すこともあるというのだからすごい。大介くんたちはその構法を使って敷地内の納屋を改修し、いずれゲストが宿泊できるスペースにしようと考えている。大介くんはこう語る。
「石場建てって土を痛めないんですよ。なおかつ空気と水の流れを遮断しない家の建て方でもあって」
僕の大好きなドキュメンタリー映画作家、小川紳介は山形県上山市の農村・牧野村を舞台に『1000年刻みの日時計 牧野村物語』(1987年)という一大傑作を作り上げた。その映画では農村の暮らしに執拗にカメラを向けながら、縄文時代から続く人々の営みが炙り出されている。大介くんたちもまた、1000年刻みの里山の歴史を土と水の側から見つめ、現代においてふたたび構築しようとしているのだ。なんとロマン溢れる試みだろうか。
「『山は負の遺産だ』といって、子供に引き継がせたくないから誰かに売り飛ばしてソーラーにしちゃうケースがよくあるんですよね。全然負の遺産なんかじゃないのに。山は宝ですよ」
大介くんはそう呟く。尚子さんによると茂木町や近隣の益子、那須烏山などではソーラーパネルが凄まじい勢いで増えているのだという。メガソーラーの先にあるヴィジョンとはいったい何なのだろうか。1000年後の未来から振り返ったとき、ただの鉄屑となっているだろうソーラーは何の役に立つのだろうか?


昨年には里山の整備や納屋の改修を目的とするクラウドファンディングを実施し、目標金額を無事達成した。それだけふたりのヴィジョンに共感が広がっているということでもあるだろう。
「みんな今、『暮らし』に意識が向いていると思うんですよね。こないだも水の杜ワークショップのため福島から来た方がいて、まさに僕らみたいなことをやっていきたいと話していました。自分が2012年に栃木に戻ってきたときに持っていたヴィジョンに共感してくれる人が増えている。当時、生きるうえでの違うベクトルがあるんじゃないかと思っていたんですけど、まさにそういうベクトルに向かう人が増えているんです」
大介くんはそう力強く断言する。彼らのヴィジョンに共感する人々がひとりまたひとりと増え、体験や知識がシェアされるなかで、世界は少しずつ変わっていく。それは実にリアルで確実な世界の変え方だ。
メガソーラーの森が木一本一本を、ひと山ふた山を金へと変えるためのものだとすれば、大介くんたちは森を「杜」へと戻すことによって、貨幣経済を介在させない生き方を模索している。宝である山と共存し、そこから得られる恵を少しずついただきながら、つつましい生活を実現しようとしているのだ。そしてそこにメガソーラーの森にはなし得ない「豊かな暮らし」を見い出している。

自由を求めて東京のクラブでDJをやっていた大介くんは今、自律した里山の暮らしに本当の意味での自由を感じ取っている。試しにOxford Languagesで「自律」という言葉を引くと、「自分の気ままを押さえ、または自分で立てた規範に従って、自分の事は自分でやって行くこと」と書かれている。大介くんと尚子さんにこれ以上ぴったりな言葉はないのではないだろうか。

五月女 大介/竹細工職人。竹細工工房〈伍竹庵〉庵主。
1980年、栃木県生まれ。武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒。東京で音楽関係の仕事に従事した後、2011年の東日本大震災をきっかけに栃木へUターン。半農半Xを志す過程で竹細工に出会い、伝統工芸士・八木澤正に師事。3年間の内弟子修行の後、八溝山脈の麓・茂木町に工房を構え、伍竹庵として独立。同年、妻・尚子と結婚。制作と並行して、自然に根ざした暮らしと仕事の在り方や手仕事をワークショップやコミュニティ活動を通じて発信している。
-

FORESTER
Shigeaki Adachi
-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER
Kei Amano
-

BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER
Taiki Minakuchi
-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭 火付ぬ組
-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN
Yukihito Kanai
-

SAUNA BUILDER
nodaklaxonbebe