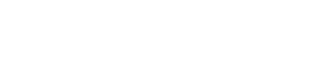Chapter 6 Vol.Two
BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
Daisuke Soutome
五月女大介
東日本大震災以降、自身の生き方を見つめ直した五月女大介は、故郷の栃木へ戻り、農業に新たな可能性を見い出すようになる。そうしたなかで何気なく始めたのが、自然と共に生きた祖父が日々編んでいた竹細工だった。ものづくりの原点をそこに見た五月女は、やがて竹細工の奥深い世界へと足を踏み入れていく。
2011年の東日本大震災は多くの人々にとって自身の生き方を見つめ直すきっかけとなった。都市機能が麻痺し、人々がパニック状態になっている光景を見て、都市生活の限界を感じた人は少なくなかったはずだ。
僕自身のことでいえば、津波によって集落が押し流されていくニュース映像を見たことによって、自分のなかに郷土愛というものが眠っていることに気づかされた。僕にとって東北は故郷でもなければ、それほど縁のある土地というわけでもない。だが、人々の営みが丸ごと破壊される映像を観て、言葉にならないほど胸が痛んだ。その痛みは、やがて日本列島各地の風土や土着文化への関心に変わり、祭りや盆踊りに関する数冊の著作へと結びついた。
だから、友人である五月女大介くんが東日本大震災をきっかけに故郷へと戻り、これからの生き方の基軸を農業に見い出していったことは理解できる。都市に生きる自分の足元がいかに不安定であるか知ってしまった大介くんは、大地に深く根ざした生き方を実践するべく故郷へと戻ったのだ。
僕自身のことでいえば、津波によって集落が押し流されていくニュース映像を見たことによって、自分のなかに郷土愛というものが眠っていることに気づかされた。僕にとって東北は故郷でもなければ、それほど縁のある土地というわけでもない。だが、人々の営みが丸ごと破壊される映像を観て、言葉にならないほど胸が痛んだ。その痛みは、やがて日本列島各地の風土や土着文化への関心に変わり、祭りや盆踊りに関する数冊の著作へと結びついた。
だから、友人である五月女大介くんが東日本大震災をきっかけに故郷へと戻り、これからの生き方の基軸を農業に見い出していったことは理解できる。都市に生きる自分の足元がいかに不安定であるか知ってしまった大介くんは、大地に深く根ざした生き方を実践するべく故郷へと戻ったのだ。

畑仕事に精を出すかたわら、大介くんはかつて祖父が漁の合間にやっていた竹細工にも取り組むようになる。そのことが彼の人生を大きく変えることになるわけだが、その経緯を大介くんはこう話す。
「自分で収穫したものを入れる籠が欲しかったんですよ。しかもプラスチックじゃなくて、自然素材のものを。買おうと思えばホームセンターで安く買えますけど、自分で手作りしたものを、愛着を持って使うという生き方をしてみたいなと思っていたんです。
あと、東京にいた10年間、音楽に情熱を注ぎ込んできたわけですけど、それを手放したとき、自分で何をやりたいかといったらものづくりしかなかったんですよ。小さいころから好きだったし、ワクワクすることだった。で、究極のものづくりってなんだろう、お金もないしどうしよう?と考えたときに、すべて合致したのが竹細工だったんです」
竹細工職人になる以前、東京でDJで活動していた時代から大介くんは手仕事の人だと感じていた。DJの際の繊細かつスムースなミックスには、迷路のように竹を編んでいく現在の手の動きとどこか重なり合うところがあった。やがて大介くんの関心は農業から竹細工へとシフトしていくことになるが、今思うと、それも必然的なものだったのだろう。
そして、一大決心をした大介くんは、栃木県大田原市の竹工芸家・八木澤正さんの内弟子として竹細工の基礎を3年間学ぶことになる。
「大田原って竹工芸をやってる方がすごく多いんですよ。八木澤正さんのお父様が竹工芸を広めた方で、民具としての竹細工がどんどん衰退していった高度経済成長期、伝統工芸としての竹工芸を追求していったんです。八木澤正さんもそれを受け継がれているんです」 八木澤さんが代表を務める八木澤竹芸のウェブサイトには、自身のプロフィールが綴られている。ここで引用してみよう。
1953年、栃木県大田原市生まれ。竹芸家の父・啓造に師事し、1978年、八木澤竹芸工房として独立。現在に至る。竹材料の弾性力と摩擦力の自然な力学的調和によって豊富なアイデアを実現する。伝統的な技法を用いて斬新で精神的な作品を作る。ジャズ演奏のような即興性を旨とする。そのときに使う竹材料の力学的特徴を直感的に見抜いて、作品の形が決まっていく。これは実演においてもよく見られる――。
八木澤さんが代表を務める八木澤竹芸のウェブサイトには、自身のプロフィールが綴られている。ここで引用してみよう。
1953年、栃木県大田原市生まれ。竹芸家の父・啓造に師事し、1978年、八木澤竹芸工房として独立。現在に至る。竹材料の弾性力と摩擦力の自然な力学的調和によって豊富なアイデアを実現する。伝統的な技法を用いて斬新で精神的な作品を作る。ジャズ演奏のような即興性を旨とする。そのときに使う竹材料の力学的特徴を直感的に見抜いて、作品の形が決まっていく。これは実演においてもよく見られる――。
「竹材料の特徴を見抜き、ジャズ演奏のような即興性を旨とする」という一文に、大介くんの美意識と共鳴するものがあるようにも感じる。
ただし、最初の段階から大介くんがこだわっているポイントがある。それは日々の道具としての竹細工ということだ。
「工芸は鑑賞するだけのものもあるんですよね。たとえば、茶室に飾る花器ようなものとか。僕は最初の農体験がきっかけで関心を持ち始めたので、暮らしの中でしっかり使えるものを作りたかったんです。ただ、工芸の世界を学んだことで逆に気づきになりました。これから僕がやりたいことは生きるための道具であり、暮らしを豊かにするための道具だと」
郷土資料館などに展示されている農具や民具を眺めていると、使いこまれた道具ならではの輝きに惚れ惚れしてしまうことがある。使われることを念頭に置いて制作された道具が、実際に長い間使われ続け、やがて役目を終えて資料館で余生を送っている。使っていた者の人生さえも刻み込まれたその佇まいに、気高くて凛とした美しさを感じてしまうのだ。
大介くんが作っている籠やざるもまた、使いこまれるうちにそうした輝きを放っていくのだろう。職人が丁寧に作った道具と共に年月を送っていけるなんて、なんて豊かな暮らしだろうか。
「自分で収穫したものを入れる籠が欲しかったんですよ。しかもプラスチックじゃなくて、自然素材のものを。買おうと思えばホームセンターで安く買えますけど、自分で手作りしたものを、愛着を持って使うという生き方をしてみたいなと思っていたんです。
あと、東京にいた10年間、音楽に情熱を注ぎ込んできたわけですけど、それを手放したとき、自分で何をやりたいかといったらものづくりしかなかったんですよ。小さいころから好きだったし、ワクワクすることだった。で、究極のものづくりってなんだろう、お金もないしどうしよう?と考えたときに、すべて合致したのが竹細工だったんです」
竹細工職人になる以前、東京でDJで活動していた時代から大介くんは手仕事の人だと感じていた。DJの際の繊細かつスムースなミックスには、迷路のように竹を編んでいく現在の手の動きとどこか重なり合うところがあった。やがて大介くんの関心は農業から竹細工へとシフトしていくことになるが、今思うと、それも必然的なものだったのだろう。
そして、一大決心をした大介くんは、栃木県大田原市の竹工芸家・八木澤正さんの内弟子として竹細工の基礎を3年間学ぶことになる。
「大田原って竹工芸をやってる方がすごく多いんですよ。八木澤正さんのお父様が竹工芸を広めた方で、民具としての竹細工がどんどん衰退していった高度経済成長期、伝統工芸としての竹工芸を追求していったんです。八木澤正さんもそれを受け継がれているんです」

「竹材料の特徴を見抜き、ジャズ演奏のような即興性を旨とする」という一文に、大介くんの美意識と共鳴するものがあるようにも感じる。
ただし、最初の段階から大介くんがこだわっているポイントがある。それは日々の道具としての竹細工ということだ。
「工芸は鑑賞するだけのものもあるんですよね。たとえば、茶室に飾る花器ようなものとか。僕は最初の農体験がきっかけで関心を持ち始めたので、暮らしの中でしっかり使えるものを作りたかったんです。ただ、工芸の世界を学んだことで逆に気づきになりました。これから僕がやりたいことは生きるための道具であり、暮らしを豊かにするための道具だと」
郷土資料館などに展示されている農具や民具を眺めていると、使いこまれた道具ならではの輝きに惚れ惚れしてしまうことがある。使われることを念頭に置いて制作された道具が、実際に長い間使われ続け、やがて役目を終えて資料館で余生を送っている。使っていた者の人生さえも刻み込まれたその佇まいに、気高くて凛とした美しさを感じてしまうのだ。
大介くんが作っている籠やざるもまた、使いこまれるうちにそうした輝きを放っていくのだろう。職人が丁寧に作った道具と共に年月を送っていけるなんて、なんて豊かな暮らしだろうか。

ちなみに、八木澤正さんの内弟子として修行中、大介くんはのちにパートナーとなる尚子さんと出会っている。ふたりが出会ったのは何と竹林だったという。
「竹林整備のイヴェントがあって、そこで出会ったんですよ。共通の知り合いがいて、その知り合いが尚ちゃんを連れてきたんです」
尚子さんも宇都宮の生まれ。育った環境について尚子さんはこう話す。
「宇都宮の端っこだったんで、周りは田んぼばっかり。私が小学校に入るまでは、ヘイケボタルがばあっと出るようなすごくいい環境だったんですけど、小学校のころに(農薬の)空中散布が始まったんですよね。そうしたら途端にホタルが出なくなりました」
高校まで宇都宮で暮らしたあと、大学進学で沖縄へ。尚子さんは「琉球大学で人類学を学んだあと、沖縄県立芸術大学の大学院でバリ島の竹ガムランを研究していました」と話す。
竹ガムランの研究者と竹細工の職人が竹林で出会い、ほどなくして結婚する。ちょっと出来すぎた話ではあるけれど、ふたりの話を聞いていると、彼らが出会うべくして出会ったという感じもしてくる。竹ガムランを研究したあと、尚子さんはパーマカルチャーやコミュニティー作りに関心を持ち、これからの生き方について考え続けていたらしい。ふたりは出会う前からさまざまな感覚とヴィジョンを共有していたのだ。
大田原で竹細工を学んだ大介くんは、2016年春、空き家バンクで探し出した茂木町の古民家に移住。その古民家を「かごめらぼ」と名付けて竹細工職人として独立を果たす。
「かごめらぼ」では尚子さんのヨガ・ワークショップや大介くんが講師となる竹細工教室も2年ほど続けてきた。
「竹林整備のイヴェントがあって、そこで出会ったんですよ。共通の知り合いがいて、その知り合いが尚ちゃんを連れてきたんです」
尚子さんも宇都宮の生まれ。育った環境について尚子さんはこう話す。
「宇都宮の端っこだったんで、周りは田んぼばっかり。私が小学校に入るまでは、ヘイケボタルがばあっと出るようなすごくいい環境だったんですけど、小学校のころに(農薬の)空中散布が始まったんですよね。そうしたら途端にホタルが出なくなりました」
高校まで宇都宮で暮らしたあと、大学進学で沖縄へ。尚子さんは「琉球大学で人類学を学んだあと、沖縄県立芸術大学の大学院でバリ島の竹ガムランを研究していました」と話す。
竹ガムランの研究者と竹細工の職人が竹林で出会い、ほどなくして結婚する。ちょっと出来すぎた話ではあるけれど、ふたりの話を聞いていると、彼らが出会うべくして出会ったという感じもしてくる。竹ガムランを研究したあと、尚子さんはパーマカルチャーやコミュニティー作りに関心を持ち、これからの生き方について考え続けていたらしい。ふたりは出会う前からさまざまな感覚とヴィジョンを共有していたのだ。
大田原で竹細工を学んだ大介くんは、2016年春、空き家バンクで探し出した茂木町の古民家に移住。その古民家を「かごめらぼ」と名付けて竹細工職人として独立を果たす。
「かごめらぼ」では尚子さんのヨガ・ワークショップや大介くんが講師となる竹細工教室も2年ほど続けてきた。

「竹細工教室もすごく面白いんですよ。仙台から通ってくれる方もいますし、群馬や厚木の方もいます。僕も最初は自分の作品だけ売って食べてこうと思ってたんですけど、やっぱり技術をシェアしたほうがいいなと思って」
近年、竹細工の世界も職人の高齢化が進んでいる。竹細工の技術や知識を広くシェアするということは、そうした現状を食い止めるためのものでもあるのだという。実際、こんな実例もあるらしい。
「独立した最初のころ、一緒に竹林に入って、竹の選び方や切り方、洗い方までを半日で教えるワークショップを結構やってたんです。それで竹にはまっちゃったという人が結構いて。当時バイク屋さんをやっていて、いま竹職人になったという人もいますね。その彼は今、いろんなところで教室をやっていて。だからね、撒いた種が確実に広がっているんですよ」
竹細工の職人として売上を独占したければ、技術を誰にも伝えずに独り占めしたほうがいいに決まっている。だが、職人の高齢化が進む竹細工の世界はそんな余裕などない。大介くんはひとりでも多くの人に技術をシェアし、裾野を広げていくことを重視している。「裾野を広げる」という表現が堅苦しければ、「仲間を増やす」といってもいいかもしれない。
現在、大介くんの竹細工はぼぼ店舗で買うことはできない。基本的に受注生産らしく、注文が山積みの状態なのだという。
「店舗の卸って今、大田原の知り合いのお店しかやってなくて、ほとんど個人の受注生産です。ヨガとかワークショップでここに来た人、あるいはインスタとかフェイスブックで僕の活動を見た人が注文してくれるんです。
近年、竹細工の世界も職人の高齢化が進んでいる。竹細工の技術や知識を広くシェアするということは、そうした現状を食い止めるためのものでもあるのだという。実際、こんな実例もあるらしい。
「独立した最初のころ、一緒に竹林に入って、竹の選び方や切り方、洗い方までを半日で教えるワークショップを結構やってたんです。それで竹にはまっちゃったという人が結構いて。当時バイク屋さんをやっていて、いま竹職人になったという人もいますね。その彼は今、いろんなところで教室をやっていて。だからね、撒いた種が確実に広がっているんですよ」
竹細工の職人として売上を独占したければ、技術を誰にも伝えずに独り占めしたほうがいいに決まっている。だが、職人の高齢化が進む竹細工の世界はそんな余裕などない。大介くんはひとりでも多くの人に技術をシェアし、裾野を広げていくことを重視している。「裾野を広げる」という表現が堅苦しければ、「仲間を増やす」といってもいいかもしれない。
現在、大介くんの竹細工はぼぼ店舗で買うことはできない。基本的に受注生産らしく、注文が山積みの状態なのだという。
「店舗の卸って今、大田原の知り合いのお店しかやってなくて、ほとんど個人の受注生産です。ヨガとかワークショップでここに来た人、あるいはインスタとかフェイスブックで僕の活動を見た人が注文してくれるんです。

工房を訪ねる体験っていうのもやっぱり高ぶるものがあるじゃないですか。モノと一緒に思い出も残るし、お金だけが僕の口座に入ってきてそれを元に作るというのも何か虚しいんですよね。昔の竹細工職人は身ひとつで農家さんのところに行って、敷地の竹でオーダーメイドで作ってたんですよ。それがめちゃくちゃかっこいいなと思っていて。それと同じ感覚なんです」
大介くんは注文した人の顔を思い浮かべながら、今日も竹を編む。ものづくりの原点がここにあるのもかもしれない。
竹細工の基本的なプロセスを見せてもらうことになった。
大介くんは作業スペースに腰を下ろすと、一本の青竹を手に取った。ピカピカに磨き上げられた竹は瑞々しい色彩を放っている。その横に茶色く染め上げられた年代ものの籠を並べると、色の違いがはっきりする。
「竹も30年とか50年経つと、柿渋を塗ったような色になるんです。何も塗ってないんですけど、こういう色になるんですよ」 大介くんのバイブルだという書籍『日之影の竹細工職人 廣島一夫の仕事』をめくりながら彼はこう続ける。
大介くんのバイブルだという書籍『日之影の竹細工職人 廣島一夫の仕事』をめくりながら彼はこう続ける。
「僕が影響を受けている廣島一夫さんという宮崎の日之影町の竹細工職人がいるんですけど、97歳まで現役でやっていたんですよ。作ってるものがまたとんでもなくて。(ページをめくりながら)これは飯籠です。九州は高温多湿なんで、飯籠にご飯を入れて吊るしておくんですよ。そうするとカビない。この時代にこういう繊細なものを作ってる人がいるということが驚きですよね」
本に掲載された柿渋色の飯籠は、素人目から見てもただごとではないオーラを放っている。細かい編み目は芸術的であると同時に、道具としての力強さが漲っている。こうした編み方も地域によって違うのだという。
「たとえば、菊底という編み方をするのは九州です。網代底は関東でよく見る編み方で、九州にはほぼないんですよ。青竹でこういう繊細なものを作っているのはほとんどが九州ですね」
僕はてっきり各職人ごとにオリジナルの編み方があるものと思っていたのだが、大介くんは「いや、それがないんですよ。編み方自体はそんなに種類がたくさんなくて」と話す。
大介くんは注文した人の顔を思い浮かべながら、今日も竹を編む。ものづくりの原点がここにあるのもかもしれない。
竹細工の基本的なプロセスを見せてもらうことになった。
大介くんは作業スペースに腰を下ろすと、一本の青竹を手に取った。ピカピカに磨き上げられた竹は瑞々しい色彩を放っている。その横に茶色く染め上げられた年代ものの籠を並べると、色の違いがはっきりする。
「竹も30年とか50年経つと、柿渋を塗ったような色になるんです。何も塗ってないんですけど、こういう色になるんですよ」

「僕が影響を受けている廣島一夫さんという宮崎の日之影町の竹細工職人がいるんですけど、97歳まで現役でやっていたんですよ。作ってるものがまたとんでもなくて。(ページをめくりながら)これは飯籠です。九州は高温多湿なんで、飯籠にご飯を入れて吊るしておくんですよ。そうするとカビない。この時代にこういう繊細なものを作ってる人がいるということが驚きですよね」
本に掲載された柿渋色の飯籠は、素人目から見てもただごとではないオーラを放っている。細かい編み目は芸術的であると同時に、道具としての力強さが漲っている。こうした編み方も地域によって違うのだという。
「たとえば、菊底という編み方をするのは九州です。網代底は関東でよく見る編み方で、九州にはほぼないんですよ。青竹でこういう繊細なものを作っているのはほとんどが九州ですね」
僕はてっきり各職人ごとにオリジナルの編み方があるものと思っていたのだが、大介くんは「いや、それがないんですよ。編み方自体はそんなに種類がたくさんなくて」と話す。

「工芸になってくるとめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、青竹細工に関してはほとんど一緒ですね。例えば四つ目とか籠目、ゴザ目。不思議なことにこの編み方って世界共通なんですよ。誰が編み出したとかもわからないし、人類の英知なんです。そこにめちゃくちゃロマンがあるんですね」
つまり、竹細工は作家としての独創性を競い合う世界ではないのだ。だが、誰が作っても同じかというと、決してそういうわけでもない。大介くんはこう語る。
「ただ、オリジナリティーを追求していないといっても、作ったものにはその人の個性が出ちゃうんです。十人十色にしか絶対にならない。そこがおもしろいんです」
話しながらも大介くんの手は動き続けている。一本の竹を磨き、何度も割りながら細い一本の竹ひごにしていく。極めて繊細な作業だ。そして、その竹ひごにすら大介くんの個性が表現されている。繊細で丁寧で力強い、まるで彼のDJみたいな竹ひごだ。 「微妙な厚さを調整しながら削り出していくんですけど、本当に0.1ミリ違うと編めなかったりするんですよね。折れちゃうこともあるし。人間の手って100分の1ミリの違いがわかるらしいんですよ。男性の毛と女性の毛があると、手で触ればだいたいわかると思うんです。師匠が言ってたのは『手が一番の道具だ』と。
「微妙な厚さを調整しながら削り出していくんですけど、本当に0.1ミリ違うと編めなかったりするんですよね。折れちゃうこともあるし。人間の手って100分の1ミリの違いがわかるらしいんですよ。男性の毛と女性の毛があると、手で触ればだいたいわかると思うんです。師匠が言ってたのは『手が一番の道具だ』と。
竹をやっていると、頭で考えるよりも手が先に動いちゃってることがあるんですよ。没頭していると手が勝手に動き出して、自然に形を作っていくんです」
まさに無我の境地である。確かにたった今も大介くんの手は猛スピードで動き続けている。気づくと、彼の顔つきも先ほどまでの柔和なものとは違い、厳しい職人の顔になっている。
部屋には竹を編む音が静かに流れている。スピーカーからは先ほどと同じくアコースティックギターのインストが静かに流れていて、時たま猫のキラちゃんがニャーと伸びをする。なんて平和な空間だろうか。大介くんはこの場所で日々作業を続けている。長いと1日10時間ほど竹細工を作り続けることもあるらしい。
つまり、竹細工は作家としての独創性を競い合う世界ではないのだ。だが、誰が作っても同じかというと、決してそういうわけでもない。大介くんはこう語る。
「ただ、オリジナリティーを追求していないといっても、作ったものにはその人の個性が出ちゃうんです。十人十色にしか絶対にならない。そこがおもしろいんです」
話しながらも大介くんの手は動き続けている。一本の竹を磨き、何度も割りながら細い一本の竹ひごにしていく。極めて繊細な作業だ。そして、その竹ひごにすら大介くんの個性が表現されている。繊細で丁寧で力強い、まるで彼のDJみたいな竹ひごだ。

竹をやっていると、頭で考えるよりも手が先に動いちゃってることがあるんですよ。没頭していると手が勝手に動き出して、自然に形を作っていくんです」
まさに無我の境地である。確かにたった今も大介くんの手は猛スピードで動き続けている。気づくと、彼の顔つきも先ほどまでの柔和なものとは違い、厳しい職人の顔になっている。
部屋には竹を編む音が静かに流れている。スピーカーからは先ほどと同じくアコースティックギターのインストが静かに流れていて、時たま猫のキラちゃんがニャーと伸びをする。なんて平和な空間だろうか。大介くんはこの場所で日々作業を続けている。長いと1日10時間ほど竹細工を作り続けることもあるらしい。

「座り続けていると、お尻や腰が疲れちゃうんですよ。なので、時間を見て外で作業をしたりします。だいたい朝4、5時に起きて、午前中はみっちり仕事をして、午後はゆるく。毎日そんな感じですね」
竹細工の材料となる竹もすぐ近くの竹林から切り出している。使うのは3年ものの竹だけ。竹の中にも太いものと細いものがあり、繊維の硬さも異なる。そうしたさまざまな竹を部位に合わせて使い分けているのだという。
「僕が使っているのは真竹なんですけど、昔は真竹が手に入る北限が栃木と言われていたらしいんですよ。今は温暖化で東北のほうにも少しは真竹が生えてるとは思いますけど、栃木っていろんな植生の境目らしくて。
栃木の真竹は張りがあっていいという人もいます。笹も美味しいらしくて、上野動物園のパンダは栃木の笹を食べてるという話を聞いたこともあります」 完成したタラシを尚子さんが持ってきてくれた。タラシとは茶碗籠の浅いもので、野菜や果物の搬送、水切りなどに使われてきた。大介くんは「今だったらパンクーラーとして使ってもいいでしょうね」と話す。
完成したタラシを尚子さんが持ってきてくれた。タラシとは茶碗籠の浅いもので、野菜や果物の搬送、水切りなどに使われてきた。大介くんは「今だったらパンクーラーとして使ってもいいでしょうね」と話す。
大介くんの竹細工は繊細で美しいが、現代に生きる僕らの生活とも違和感なく馴染むような雰囲気がある。彼が言うようにタラシの上にバゲットやクロワッサンを乗せてもいいだろう。大介くんはあくまでも現代の暮らしのなかで活きる道具を作ろうとしているのだ。
尚子さんは台所で摘んできたばかりの野菜を刻んでいる。雨は降り続けていて、到着したときよりもさらに雨足が強くなっている。シャッシャ、シャッシャ。大介くんが竹ひごを削り出す鋭い音が鳴り響いている。
竹細工の材料となる竹もすぐ近くの竹林から切り出している。使うのは3年ものの竹だけ。竹の中にも太いものと細いものがあり、繊維の硬さも異なる。そうしたさまざまな竹を部位に合わせて使い分けているのだという。
「僕が使っているのは真竹なんですけど、昔は真竹が手に入る北限が栃木と言われていたらしいんですよ。今は温暖化で東北のほうにも少しは真竹が生えてるとは思いますけど、栃木っていろんな植生の境目らしくて。
栃木の真竹は張りがあっていいという人もいます。笹も美味しいらしくて、上野動物園のパンダは栃木の笹を食べてるという話を聞いたこともあります」

大介くんの竹細工は繊細で美しいが、現代に生きる僕らの生活とも違和感なく馴染むような雰囲気がある。彼が言うようにタラシの上にバゲットやクロワッサンを乗せてもいいだろう。大介くんはあくまでも現代の暮らしのなかで活きる道具を作ろうとしているのだ。
尚子さんは台所で摘んできたばかりの野菜を刻んでいる。雨は降り続けていて、到着したときよりもさらに雨足が強くなっている。シャッシャ、シャッシャ。大介くんが竹ひごを削り出す鋭い音が鳴り響いている。

五月女 大介/竹細工職人。竹細工工房〈伍竹庵〉庵主。
1980年、栃木県生まれ。武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒。東京で音楽関係の仕事に従事した後、2011年の東日本大震災をきっかけに栃木へUターン。半農半Xを志す過程で竹細工に出会い、伝統工芸士・八木澤正に師事。3年間の内弟子修行の後、八溝山脈の麓・茂木町に工房を構え、伍竹庵として独立。同年、妻・尚子と結婚。制作と並行して、自然に根ざした暮らしと仕事の在り方や手仕事をワークショップやコミュニティ活動を通じて発信している。
-

FORESTER
Shigeaki Adachi
-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER
Kei Amano
-

BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER
Taiki Minakuchi
-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭 火付ぬ組
-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN
Yukihito Kanai
-

SAUNA BUILDER
nodaklaxonbebe