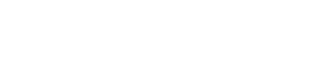Chapter 6 Vol.Four
BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
Daisuke Soutome
五月女大介
栃木県芳賀郡茂木町の里山に根を下ろし、竹細工職人として日々の暮らしを送る五月女大介。彼が妻とともにめざしているのは、「快適な暮らし」という名目のもと山をメガソーラーで覆い尽くすような発想とは真逆のサステナブルな「水の杜」の暮らしだ。4回目にして最終回となる今回は、実際に里山を案内してもらいながら、ふたりのヴィジョンを語ってもらった。
2022年5月末。大介くんたちの住む尾軽(おがるい)集落の里山には爽やかな風が吹いていた。前回訪れた際は雨がしとしとと木々を濡らし、それはそれで実に美しい光景だった。だが、いま目の前に広がる里山は春の光に包まれ、まばゆいばかりの輝きを放っている。大介くんも「ここは日によって風も違うんですよね」と話し、春の陽光に目を細める。この日は大介くんに里山を案内してもらうことになっていた。里山探訪にはこれ以上ない天候だ。
まず立ち寄ったのが、前回の記事でも触れた納屋。石場建てという昔ながらの建築構法によって蘇りつつあるこの納屋は、もともと煙草の乾燥小屋だった。かつての住人はこの納屋の前の畑で煙草と蒟蒻を育てていたのだという。大介くんはこう話す。
「このへんは煙草農家さんが多かったんですよ。おそらくこの納屋で火を焚いていたんじゃないかな。ここもちょっと崩れかけてたんですけど、それを石場建てで組み直そうとしているんです」
まず立ち寄ったのが、前回の記事でも触れた納屋。石場建てという昔ながらの建築構法によって蘇りつつあるこの納屋は、もともと煙草の乾燥小屋だった。かつての住人はこの納屋の前の畑で煙草と蒟蒻を育てていたのだという。大介くんはこう話す。
「このへんは煙草農家さんが多かったんですよ。おそらくこの納屋で火を焚いていたんじゃないかな。ここもちょっと崩れかけてたんですけど、それを石場建てで組み直そうとしているんです」

前回も触れたように、後々この場所はゲストが来たときに寝泊まりしたり、ワークショップをやったりと、さまざまな用途に使われる予定だ。解説する大介くんのすぐ真横では鳥たちが美しい鳴き声を響かせている。こんな声で目覚めたらさぞかし気分がいいだろう。大介くんも「ちょっとバリ島のリゾートみたいな感じかなと思ってて(笑)」と笑う。
この取材の直前に行われた石場建てワークショップでは、石場建ての専門家である今西友起さんを講師に招き、3日間にわたって延べ30人の人々が参加した。なかには関西からわざわざやってきた人もいたのだとか。
石場建ては古民家など古い建築物で用いられる工法であるものの、かといって大介くんはノスタルジーから昔ながらの建築方法を採用しているわけではない。彼によると、環境に対する影響を意識していているからこそ、土を痛めない石場建てという建築構法をチョイスしているらしい。大介くんは里山を歩くときも常に足袋を履いているが、それも土壌への配慮からだという。
「靴ってどうしても踵が地面につくんで、土地を痛めやすいんですね。でも、足袋だと地面にかかる圧が弱いので痛めないんですよ。直足袋は作業もしやすいですし」
この取材の直前に行われた石場建てワークショップでは、石場建ての専門家である今西友起さんを講師に招き、3日間にわたって延べ30人の人々が参加した。なかには関西からわざわざやってきた人もいたのだとか。
石場建ては古民家など古い建築物で用いられる工法であるものの、かといって大介くんはノスタルジーから昔ながらの建築方法を採用しているわけではない。彼によると、環境に対する影響を意識していているからこそ、土を痛めない石場建てという建築構法をチョイスしているらしい。大介くんは里山を歩くときも常に足袋を履いているが、それも土壌への配慮からだという。
「靴ってどうしても踵が地面につくんで、土地を痛めやすいんですね。でも、足袋だと地面にかかる圧が弱いので痛めないんですよ。直足袋は作業もしやすいですし」

なぜそこまで? この時点ではいまいち理解できなかったが、里山を案内されるなかでその理由は少しずつ明らかになっていく。
納屋の先に進むと、そこには鬱蒼とした竹林が広がっている。竹細工職人としては材料の宝庫である。実際、大介くんは竹が休眠状態に入る10月から12月にかけてこの竹林に入り、選び抜いた数本を伐採して自宅まで運ぶ。
「ここの竹林は最初誰かが植えたところが多いと思います。タケノコを取るためだったり、何かの道具を作るために竹を育てていたんじゃないかな。だから、放置された竹林を見るとかわいそうになっちゃうんですよ。そこに竹を植えた先人がいたわけで、その思いを汲んであげたいなと」
放置された竹林は猛烈なスピードで周囲の木々を侵食し、成長を阻んでしまう。そのため「竹害」などと呼んで悪者扱いされることも多いが、大介くんは仕事の材料を取るだけでなく、竹林の整備にも精を出している。竹が宝であり、財産でもあった時代の営みを現在も続けているのだ。
里山の一角にちょろちょろと水が湧き出る水源がある。そこから山肌を上がっていくと、小さな鳥居が立っている。尾軽集落に引っ越してきた当初、大介くんはここでこんな体験をしている。
「僕が引っ越してきたとき、集落の人たちがゴザを広げて、車座になってお酒を飲んでいたんですね。『今日越してきたものです』と声をかけたら『おお、一杯やっていけ』と言われて(笑)。それが4月10日だったのかな。年に2回はここを管理してる人たちが集まってお祭りをやってるんです」 この神様は集落で「タキタさん」と呼ばれている。尚子さんは「ここでは大事なところにお社が立っていたり、道祖神みたいな石が立ってるんですよね」と話す。山の麓に立っていることを考えると山の神を祀っているような感じもするが、まるで水源を守るように鎮座していることを考えると、水神さまなのかもしれない。僕らも「タキタさん」にお詣りし、山に入る赦しを乞う。小さな祠だけど、周囲は整備されていて、集落の人々が大切にしてきたことがわかる。「タキタさん」の前の開かれたスペースに立つ大介くんは、地面を指差しながらこう話す。
この神様は集落で「タキタさん」と呼ばれている。尚子さんは「ここでは大事なところにお社が立っていたり、道祖神みたいな石が立ってるんですよね」と話す。山の麓に立っていることを考えると山の神を祀っているような感じもするが、まるで水源を守るように鎮座していることを考えると、水神さまなのかもしれない。僕らも「タキタさん」にお詣りし、山に入る赦しを乞う。小さな祠だけど、周囲は整備されていて、集落の人々が大切にしてきたことがわかる。「タキタさん」の前の開かれたスペースに立つ大介くんは、地面を指差しながらこう話す。
「住環境的な視点でみると、ここは少し滞水している感じがするんですよ。土もぶよぶよしてる。(上を見上げて)そこにコンクリート擁壁をがっつり作っちゃったので、あそこで水と空気の流れが止まってるんですね」
大介くんの話によると、水や空気の流れを変えることで植生や日光の入り方も変わってくるのだという。大介くんたちは里山の水脈を整えるだけでなく、それによって里山の環境そのものを改善しようとしているのだ。僕はここで「山に手を入れる」ことの意味を初めて知ることになった。
さらに里山の上へ進もう。
しばらく進むと、こんもりとした丘が見えてきた。そこには聖地としての空気が充満していて、ひとりだったら足を踏み入れることに躊躇したことだろう。
納屋の先に進むと、そこには鬱蒼とした竹林が広がっている。竹細工職人としては材料の宝庫である。実際、大介くんは竹が休眠状態に入る10月から12月にかけてこの竹林に入り、選び抜いた数本を伐採して自宅まで運ぶ。
「ここの竹林は最初誰かが植えたところが多いと思います。タケノコを取るためだったり、何かの道具を作るために竹を育てていたんじゃないかな。だから、放置された竹林を見るとかわいそうになっちゃうんですよ。そこに竹を植えた先人がいたわけで、その思いを汲んであげたいなと」
放置された竹林は猛烈なスピードで周囲の木々を侵食し、成長を阻んでしまう。そのため「竹害」などと呼んで悪者扱いされることも多いが、大介くんは仕事の材料を取るだけでなく、竹林の整備にも精を出している。竹が宝であり、財産でもあった時代の営みを現在も続けているのだ。
里山の一角にちょろちょろと水が湧き出る水源がある。そこから山肌を上がっていくと、小さな鳥居が立っている。尾軽集落に引っ越してきた当初、大介くんはここでこんな体験をしている。
「僕が引っ越してきたとき、集落の人たちがゴザを広げて、車座になってお酒を飲んでいたんですね。『今日越してきたものです』と声をかけたら『おお、一杯やっていけ』と言われて(笑)。それが4月10日だったのかな。年に2回はここを管理してる人たちが集まってお祭りをやってるんです」

「住環境的な視点でみると、ここは少し滞水している感じがするんですよ。土もぶよぶよしてる。(上を見上げて)そこにコンクリート擁壁をがっつり作っちゃったので、あそこで水と空気の流れが止まってるんですね」
大介くんの話によると、水や空気の流れを変えることで植生や日光の入り方も変わってくるのだという。大介くんたちは里山の水脈を整えるだけでなく、それによって里山の環境そのものを改善しようとしているのだ。僕はここで「山に手を入れる」ことの意味を初めて知ることになった。
さらに里山の上へ進もう。
しばらく進むと、こんもりとした丘が見えてきた。そこには聖地としての空気が充満していて、ひとりだったら足を踏み入れることに躊躇したことだろう。

苔むした石段を上がっていくと、雰囲気のある鳥居が待ち構えていて、その先にまっすぐ参道が伸びている。参道の先に鎮座しているのが、集落の氏神である羽黒神社だ。大介くんはこう話す。
「大昔はここに出店が並んで賑やかにお祭りをやってたみたいですけど、今はこじんまりとやってる感じです。盆踊りもやってたみたいですね。中学の合唱部が発表会をやったり」
本堂の前の広場には落ち葉が敷き詰められていて、歩くとパリパリと音を立てる。大介くんは落ち葉を一枚手に取り、こう解説する。
「これはアカガシという常緑樹の葉っぱですね。ちょうど落葉する季節なんで、こんなに枯葉が落ちてるんですよ。夏のあいだ分解されないまま、表皮を乾燥しないよう守るんですね。で、秋冬に落ちた枯葉と混ざることで分解が進むんです」
「大昔はここに出店が並んで賑やかにお祭りをやってたみたいですけど、今はこじんまりとやってる感じです。盆踊りもやってたみたいですね。中学の合唱部が発表会をやったり」
本堂の前の広場には落ち葉が敷き詰められていて、歩くとパリパリと音を立てる。大介くんは落ち葉を一枚手に取り、こう解説する。
「これはアカガシという常緑樹の葉っぱですね。ちょうど落葉する季節なんで、こんなに枯葉が落ちてるんですよ。夏のあいだ分解されないまま、表皮を乾燥しないよう守るんですね。で、秋冬に落ちた枯葉と混ざることで分解が進むんです」

里山では一年を通じてそうしたサイクルが形成されていて、長い時間をかけてじっくりと土壌が形成されていく。この山からは、今もあちこちから水が湧いている。里山のなかにひとつの循環型システムが構築されているわけだ。
「これだけ巨木も立っているぐらいなので、ダム一個分の水が蓄えられてると思います。千本城があったころ、そうした水を利用していないはずがないんですよね」
大介くんの言葉に尚子さんも「水があったからこそ、城を築くことができたと思うんです」と続ける。前回の記事で触れたように、この里山には千本城という山城が築かれていた。千本十郎為隆がその山城を築城したのは建久8年(1197年)のことである。いくら敵からの攻撃を防ぐことのできる山城に適した地形であったとしても、水がなければそこに住むことはできない。千本十郎為隆はここが豊かな土地であることを見抜いていたのだろう。
羽黒神社から息を切らして坂道を登っていくと、突然視界が開けた。360度のパノラマが広がる展望台だ。標高はたった200メートルだが、あまりの見晴らしに声をあげてしまう。筑波山の山影が見えることに驚かされるが、冬になると富士山も見渡せるのだという。展望台から見える夕日がまた美しいらしい。それを夫婦で独占できるわけで、なんと贅沢な暮らしだろうか。
「これだけ巨木も立っているぐらいなので、ダム一個分の水が蓄えられてると思います。千本城があったころ、そうした水を利用していないはずがないんですよね」
大介くんの言葉に尚子さんも「水があったからこそ、城を築くことができたと思うんです」と続ける。前回の記事で触れたように、この里山には千本城という山城が築かれていた。千本十郎為隆がその山城を築城したのは建久8年(1197年)のことである。いくら敵からの攻撃を防ぐことのできる山城に適した地形であったとしても、水がなければそこに住むことはできない。千本十郎為隆はここが豊かな土地であることを見抜いていたのだろう。
羽黒神社から息を切らして坂道を登っていくと、突然視界が開けた。360度のパノラマが広がる展望台だ。標高はたった200メートルだが、あまりの見晴らしに声をあげてしまう。筑波山の山影が見えることに驚かされるが、冬になると富士山も見渡せるのだという。展望台から見える夕日がまた美しいらしい。それを夫婦で独占できるわけで、なんと贅沢な暮らしだろうか。

ところで、「水脈整備」とは具体的にいったい何をするのだろうか。水路を整えて、水の流れをよくする。素人考えではそれぐらいのことしかイメージできない。水脈整備を進めている場所を例にあげながら大介くんに解説してもらおう。
「ここはもともと風が通らなくて、藪が広がってたんですよ。雨で水が流れると表土がどろどろ流れてしまって、空気の通り道を塞いでいたんです。それで、まずは段切り(階段状に土を削ること)をしたんですね。段のところに落ち葉や炭を詰めていくと、土のなかに菌糸がしっとりと乗るんです。この菌糸が、水が浸透する起点となるんですよ」
大介くんがそう話しながら段切りした箇所を掘り起こすと、確かにしっとりと水が染み込んでいる。
「ここはスギのような針葉樹とケヤキが落ち葉を落とすので、混ざり合うことでいい土ができるんですよ。だから段切りとかで少し造作するだけで植生が変わってくるし、風の通りが変わってくるんです」 そうした作業を繰り返すことで森が再生し、風が流れ、水がふたたび通るようになる。昔の人は山中を歩きながら、鍬1本で段や道を作り、山を整備していたというが、今ではそうした作業をする村民もいなくなってしまった。そこに大介くんたちが移り住み、かつての村民たちが続けてきた営みを再開したわけだ。
そうした作業を繰り返すことで森が再生し、風が流れ、水がふたたび通るようになる。昔の人は山中を歩きながら、鍬1本で段や道を作り、山を整備していたというが、今ではそうした作業をする村民もいなくなってしまった。そこに大介くんたちが移り住み、かつての村民たちが続けてきた営みを再開したわけだ。
大介くんはこの地に生きた人々と感覚と重ね合わせ、記憶を重ね合わせながら山を蘇らせようとしている。彼は「山を育てながら仕事をしていく」という言葉を口にしたが、「山を育てる」というのはおもしろい表現だと思う。
感心している僕の横で大介くんは1本の竹が気になったのか、ナタでさっと切り出すと、20メートルほどある竹を片手で抱えながら野生動物のように急斜面を駆け降りていった。彼にとっては庭のようなものなのだろうが、その動きに僕は圧倒されてしまった。かつて東京のクラブでDJをやっていたときの大介くんはもうそこにはいなかった。
谷の底にはワークショップで作り上げたという石積みがあり、その隙間からちょろちょろと水が滲み出している。「さっきみたいな段切りをすることによって、ここから出てくる水も明らかに増えました」と大介くんは話す。汗をかいて手を動かしたぶんだけ、山は着実に変わっていくのである。
「ここはもともと風が通らなくて、藪が広がってたんですよ。雨で水が流れると表土がどろどろ流れてしまって、空気の通り道を塞いでいたんです。それで、まずは段切り(階段状に土を削ること)をしたんですね。段のところに落ち葉や炭を詰めていくと、土のなかに菌糸がしっとりと乗るんです。この菌糸が、水が浸透する起点となるんですよ」
大介くんがそう話しながら段切りした箇所を掘り起こすと、確かにしっとりと水が染み込んでいる。
「ここはスギのような針葉樹とケヤキが落ち葉を落とすので、混ざり合うことでいい土ができるんですよ。だから段切りとかで少し造作するだけで植生が変わってくるし、風の通りが変わってくるんです」

大介くんはこの地に生きた人々と感覚と重ね合わせ、記憶を重ね合わせながら山を蘇らせようとしている。彼は「山を育てながら仕事をしていく」という言葉を口にしたが、「山を育てる」というのはおもしろい表現だと思う。
感心している僕の横で大介くんは1本の竹が気になったのか、ナタでさっと切り出すと、20メートルほどある竹を片手で抱えながら野生動物のように急斜面を駆け降りていった。彼にとっては庭のようなものなのだろうが、その動きに僕は圧倒されてしまった。かつて東京のクラブでDJをやっていたときの大介くんはもうそこにはいなかった。
谷の底にはワークショップで作り上げたという石積みがあり、その隙間からちょろちょろと水が滲み出している。「さっきみたいな段切りをすることによって、ここから出てくる水も明らかに増えました」と大介くんは話す。汗をかいて手を動かしたぶんだけ、山は着実に変わっていくのである。

「ただ、変わらなかったら変わらなかったで『どうしてだろう?』と考えるし、自然を観察していると無限なんですよね。(足元の葉っぱを触りながら)なんでここにドクダミが生えてるんだろう? なんでこういう葉の形なんだろう? なんで匂いがあるんだろう? そうやって無限に疑問が出てくるんですけど、そこにはいつも理由があるんです。本当におもしろいですよね」
里山をぐるりと周り、大介くんたちの自宅に戻ってきた。家の前には坂の下へと続く広大な畑があり、さまざまな作物が育てられている。この取材時はマコモ、クレソン、コゴミ、三度豆。一角には去年開墾したという小さな田んぼまである。水路が畑の横を流れていて、覗き込むと1匹のサワガニがスタスタと歩いていた。 ただし、現在の大介くんの暮らしにおいて農業だけが重要な位置を占めているわけではない。彼は「無理せず、ゆるゆる続けてる感じですね」と話したあと、こう言葉を続ける。
ただし、現在の大介くんの暮らしにおいて農業だけが重要な位置を占めているわけではない。彼は「無理せず、ゆるゆる続けてる感じですね」と話したあと、こう言葉を続ける。
「いま畑の一角にも少しずつ植樹していて、山の植生に近づけていきたいと思ってるんですよ。僕はあくまでも『杜』を育てていきたいんです。こないだパーマカルチャーの本を読んだら、ビル・モリソンという創始者が『地球を森で覆い尽くすことがパーマカルチャーの目的だ』みたいなことを言ってたんですよ。表現としてはちょっと過激だけど、森の恩恵で暮らすということですよね。地球に対していい方向に動いていかないと。そこをめざしたいんです」
大介くんたちの前に古民家に住んでいたおばあさんが子供のころ、集落の人々は沢の水を引いた畑を耕し、自給自足的な生活を送っていた。だが、大介くんたちはその世代よりもさらに前、杜と共存するライフスタイルをイメージしている。
2021年、大介くんと尚子さんは「水の杜 育む『暮らしと生業』創造プロジェクト」と題したクラウドファンディングを立ち上げ、無事目標金額を達成した。クラウドファンディングのページには活動の目的についてこう記されている。
「地域の生態系を豊かにし、自然の循環が全体として健やかになる環境を作っていきたい」
里山をぐるりと周り、大介くんたちの自宅に戻ってきた。家の前には坂の下へと続く広大な畑があり、さまざまな作物が育てられている。この取材時はマコモ、クレソン、コゴミ、三度豆。一角には去年開墾したという小さな田んぼまである。水路が畑の横を流れていて、覗き込むと1匹のサワガニがスタスタと歩いていた。

「いま畑の一角にも少しずつ植樹していて、山の植生に近づけていきたいと思ってるんですよ。僕はあくまでも『杜』を育てていきたいんです。こないだパーマカルチャーの本を読んだら、ビル・モリソンという創始者が『地球を森で覆い尽くすことがパーマカルチャーの目的だ』みたいなことを言ってたんですよ。表現としてはちょっと過激だけど、森の恩恵で暮らすということですよね。地球に対していい方向に動いていかないと。そこをめざしたいんです」
大介くんたちの前に古民家に住んでいたおばあさんが子供のころ、集落の人々は沢の水を引いた畑を耕し、自給自足的な生活を送っていた。だが、大介くんたちはその世代よりもさらに前、杜と共存するライフスタイルをイメージしている。
2021年、大介くんと尚子さんは「水の杜 育む『暮らしと生業』創造プロジェクト」と題したクラウドファンディングを立ち上げ、無事目標金額を達成した。クラウドファンディングのページには活動の目的についてこう記されている。
「地域の生態系を豊かにし、自然の循環が全体として健やかになる環境を作っていきたい」

彼らの住む里山には古くからの循環型システムが構築されていた。「小さな宇宙」といってもいいかもしれない。そこには豊かな水があり、それを利用した農業が営まれ、集落の人々は山からの恵みを少しずついただきながらものづくりを続けてきた。そして、大介くんと尚子さんはそうした暮らしにインスパイアされながら、現代の里山の暮らしを創造しようとしている。木の集合体としての「森」ではなく、風が通り、太陽の光を浴び、いきものたちが躍動する「杜」の世界。そんな世界を彼らは夢見ているのだ。
大介くんはこう話す。
「ここってすごく意味ある場所だと思うんですよ。水源があったりお社があったり。昔の人はそれをわかっていてそこに立てているわけで、だから大事にしなきゃいけないと思うんですよね」
その言葉を受けて、尚子さんは「私たちがここまでせっかくやってきたことを後に繋いでくれる人にうまくバトンタッチしたいんです。それも血縁を超えて」と続ける。すると、大介くんも「そうだね、血縁を超えて繋いでいきたいんです」と言葉を繋げた。 東京へと戻る車の中で、僕は大介くんと尚子さんの言葉を何度も反芻していた。
東京へと戻る車の中で、僕は大介くんと尚子さんの言葉を何度も反芻していた。
ふたりの生きる里山は、まさに夢の世界であった。まぶしいほどに美しく、ふたりの表情からも日常の充実ぶりがはっきりと窺えた。だが、東京の片隅に生きる僕は、彼らのような生活を送ることはできないだろう。効率と合理性が追求された都市に生きる僕は、大介くんたちの暮らしに憧れはするものの、実践するだけの力と覚悟を持っていない。
しかし、彼らのヴィジョンを共有し、自分たちの生活に反映することはできるはずだ。私たちはこれからの世界をどのように創造していくことができるのだろうか? そうした問いをみずからに投げかけ、ヴィジョンを育み、暮らしのなかで少しずつ実践していくこと。そうした小さな積み重ねから世界は確かに変わっていく。
大介くんはこう話す。
「ここってすごく意味ある場所だと思うんですよ。水源があったりお社があったり。昔の人はそれをわかっていてそこに立てているわけで、だから大事にしなきゃいけないと思うんですよね」
その言葉を受けて、尚子さんは「私たちがここまでせっかくやってきたことを後に繋いでくれる人にうまくバトンタッチしたいんです。それも血縁を超えて」と続ける。すると、大介くんも「そうだね、血縁を超えて繋いでいきたいんです」と言葉を繋げた。

ふたりの生きる里山は、まさに夢の世界であった。まぶしいほどに美しく、ふたりの表情からも日常の充実ぶりがはっきりと窺えた。だが、東京の片隅に生きる僕は、彼らのような生活を送ることはできないだろう。効率と合理性が追求された都市に生きる僕は、大介くんたちの暮らしに憧れはするものの、実践するだけの力と覚悟を持っていない。
しかし、彼らのヴィジョンを共有し、自分たちの生活に反映することはできるはずだ。私たちはこれからの世界をどのように創造していくことができるのだろうか? そうした問いをみずからに投げかけ、ヴィジョンを育み、暮らしのなかで少しずつ実践していくこと。そうした小さな積み重ねから世界は確かに変わっていく。

取材の数週間後、栃木県芳賀郡益子町のギャラリーで大介くんの個展が行われた。そこには丹精を込めて作り上げられたザルやカゴが並んでいて、大介くんと尚子さんがいつものように僕を迎え入れてくれた。
僕は小さな水切り籠を購入すると、早速自宅に持ち帰り、妻の実家の畑で採れた野菜をその上に並べてみた。実にいい雰囲気である。
たったひとつの水切り籠。そこからも大介くんと尚子さんのヴィジョンが立ち上がってくるような気がした。
僕は小さな水切り籠を購入すると、早速自宅に持ち帰り、妻の実家の畑で採れた野菜をその上に並べてみた。実にいい雰囲気である。
たったひとつの水切り籠。そこからも大介くんと尚子さんのヴィジョンが立ち上がってくるような気がした。

五月女 大介/竹細工職人。竹細工工房〈伍竹庵〉庵主。
1980年、栃木県生まれ。武蔵野美術大学空間演出デザイン学科卒。東京で音楽関係の仕事に従事した後、2011年の東日本大震災をきっかけに栃木へUターン。半農半Xを志す過程で竹細工に出会い、伝統工芸士・八木澤正に師事。3年間の内弟子修行の後、八溝山脈の麓・茂木町に工房を構え、伍竹庵として独立。同年、妻・尚子と結婚。制作と並行して、自然に根ざした暮らしと仕事の在り方や手仕事をワークショップやコミュニティ活動を通じて発信している。
-

FORESTER
Shigeaki Adachi
-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER
Kei Amano
-

BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER
Taiki Minakuchi
-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭 火付ぬ組
-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN
Yukihito Kanai
-

SAUNA BUILDER
nodaklaxonbebe