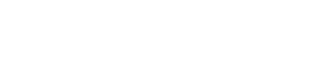林業従事者が山や森に出入りするための「森林作業道」を、まるで絵画の中のように美しくつくることで定評のある、〈outwoods〉こと足立成亮さん。なぜ彼は林業を生業とするようになったのか? どのようにして「小さな林業」を実践するようになったのか? 彼が道づくりを行う現場に同行し、瑞々しい森を共にさまよい歩きながら、独自の道づくりについて、教えてもらった。

足立成亮という人
足立さんは1982年に札幌で生まれた。ごく一般的なサラリーマン家庭で育ち、それなりに自然に触れる機会はあったものの、若いころは街での遊びに明け暮れるシティボーイだった。
ただ幼いころから、樹齢を重ねた大木に惹かれることが多かった。何十年も何百年も微動だにせずに、その場所の記憶を年輪に刻み続ける木々を見上げては、「ここでかつてなにが起きたんだろう? どんな人たちがいたんだろう?」と想像し、感じ取ったものを絵や詩にしたり写真に収めるナイーブな一面があった。
札幌市内の大学に入学し写真部に所属すると、カメラを片手にあちこちを徘徊しては暗室にこもる日々を過ごした。卒業後も写真撮影を請け負ったりギャラリーを運営したりして生計を立て、モノクロフィルムで木々を撮った作品群などが、一定の評価を得ていた。
就職せず、学生ノリのまま社会に出てしまった足立さんは、将来のことをさほど真剣に考えていなかった。写真家としてそれなりに充実していたが、次第に人生について逡巡することが多くなった。
「自分はなにをやりたいのか?」と自問自答を繰り返すうちに、出てきたのは「森で暮らす」という答えだった。幼いときから古い木や巨樹に惹かれてきた。それらを撮影した作品も評価された。「オレ、木に呼ばれているんじゃないかな?」と感じる瞬間も少なくなかった。やがて足立さんは「森に身を置くことが、自分にとっての幸せではないのか?」との思いに至った。 そして、ギャラリーと暗室を閉じて、木こりになる決心を固めた。2008年のことだった。
そして、ギャラリーと暗室を閉じて、木こりになる決心を固めた。2008年のことだった。
見つけたのは、道北の滝上町にある林業会社の仕事だった。当時の滝上町は人口が3,000人ほどという、山に囲まれた小さな町。足立さんは作業員として肉体を駆使するハードな日々を送りながらも、「暮らしも仕事も森の中」という、新たな生活を手に入れた。
しかし、現場で2年ほど経験を積んだころ、町役場から誘いを受けて転職を決意した。森を一旦離れて、町役場で働くことにしたのだ。
充実した森での生活を手放したことには、理由があった。配属されたのは、森林づくりや林業政策を取り仕切る林政係という部署。林業の全体像を見渡すことのできる絶好のポジションだった。「森にはいつでも戻ることができる」。彼はそう考えながら、デスクワークに明け暮れる日々を送った。事業の入札、発注、予算管理、計画書作成、補助金の申請など、森林に関するあらゆる業務に携わった。
田邊由喜男氏との出会い
ある時、森林の道づくりに関する講習会が開催されることを知り、足立さんは旭川に赴いた。
講師として招かれたのは、田邊由喜男さんという人物。かつて高知県の旧・大正町(現・四万十市)の林業担当職員として働いていた田邊氏は、「放置されていた森を再生させるためには、木を伐って運び出す必要性がある」と確信し、独自に作業道づくりを考案。そのユニークなメソッドが「田邊式作業道」「四万十式作業道」などと呼ばれ、全国的に注目されていた。
山に囲まれ、平坦な地形が少なく、雨の多い日本では、コンクリートを多用して山に道を開設するのが常識だった。林道は運転のしやすさを考慮して設計される。そのため、道が地形に沿わない場所では斜面を削り、沢を渡す橋をいくつも架けた。結果として山中に大量のコンクリート構造物をつくることからコストはかさみ、自然にも少なからず負荷がかかった。
作業道をつける際にも、将来的な再利用を想定しないことが多く、また、工事で出た不要な土砂を谷に捨てるなど、環境への配慮にも欠けていた。
一方の田邊氏は、森林になるべくダメージを与えず、林業の生産性を高める手法を考案し、全国各地の森林で技術を伝えていた。特に従来の道づくりの障害と見なされていた木々や根株、表土や石を破棄せず、徹底的に活用する点で画期的だった。
伐り倒した木の根株は土留めとして再利用し、土中から出る石などを活用して作業道の強度を高める。地表から深さ20cm程度までの土は無数の微生物の温床であり、植物の生育に欠かせない栄養素をたっぷりと含んでいるから、そうした表土で路肩を覆い、周囲の生態系と開設したての道がなるべく早く馴染むように工夫する。
さらに作業道の傾斜や勾配を利用して、雨水等が路面を川のにように流れないよう、分水や排水を促した。安易に橋をかけたり地中に管を埋めて水路をつくると、豪雨で破壊された際に復旧しづらく、自然への影響も甚大になる恐れがあるからだ。
道をつける上で生じる木の伐採と、地面の掘削による自然への負荷を最小限にとどめること。既存の資源を最大限に利用すること。その上で林業従事者が効率よく森に出入りできること。これらを満たすのが、田邊氏が編み出した手法なのだ。
足立さんは1982年に札幌で生まれた。ごく一般的なサラリーマン家庭で育ち、それなりに自然に触れる機会はあったものの、若いころは街での遊びに明け暮れるシティボーイだった。
ただ幼いころから、樹齢を重ねた大木に惹かれることが多かった。何十年も何百年も微動だにせずに、その場所の記憶を年輪に刻み続ける木々を見上げては、「ここでかつてなにが起きたんだろう? どんな人たちがいたんだろう?」と想像し、感じ取ったものを絵や詩にしたり写真に収めるナイーブな一面があった。
札幌市内の大学に入学し写真部に所属すると、カメラを片手にあちこちを徘徊しては暗室にこもる日々を過ごした。卒業後も写真撮影を請け負ったりギャラリーを運営したりして生計を立て、モノクロフィルムで木々を撮った作品群などが、一定の評価を得ていた。
就職せず、学生ノリのまま社会に出てしまった足立さんは、将来のことをさほど真剣に考えていなかった。写真家としてそれなりに充実していたが、次第に人生について逡巡することが多くなった。
「自分はなにをやりたいのか?」と自問自答を繰り返すうちに、出てきたのは「森で暮らす」という答えだった。幼いときから古い木や巨樹に惹かれてきた。それらを撮影した作品も評価された。「オレ、木に呼ばれているんじゃないかな?」と感じる瞬間も少なくなかった。やがて足立さんは「森に身を置くことが、自分にとっての幸せではないのか?」との思いに至った。

見つけたのは、道北の滝上町にある林業会社の仕事だった。当時の滝上町は人口が3,000人ほどという、山に囲まれた小さな町。足立さんは作業員として肉体を駆使するハードな日々を送りながらも、「暮らしも仕事も森の中」という、新たな生活を手に入れた。
しかし、現場で2年ほど経験を積んだころ、町役場から誘いを受けて転職を決意した。森を一旦離れて、町役場で働くことにしたのだ。
充実した森での生活を手放したことには、理由があった。配属されたのは、森林づくりや林業政策を取り仕切る林政係という部署。林業の全体像を見渡すことのできる絶好のポジションだった。「森にはいつでも戻ることができる」。彼はそう考えながら、デスクワークに明け暮れる日々を送った。事業の入札、発注、予算管理、計画書作成、補助金の申請など、森林に関するあらゆる業務に携わった。
田邊由喜男氏との出会い
ある時、森林の道づくりに関する講習会が開催されることを知り、足立さんは旭川に赴いた。
講師として招かれたのは、田邊由喜男さんという人物。かつて高知県の旧・大正町(現・四万十市)の林業担当職員として働いていた田邊氏は、「放置されていた森を再生させるためには、木を伐って運び出す必要性がある」と確信し、独自に作業道づくりを考案。そのユニークなメソッドが「田邊式作業道」「四万十式作業道」などと呼ばれ、全国的に注目されていた。
山に囲まれ、平坦な地形が少なく、雨の多い日本では、コンクリートを多用して山に道を開設するのが常識だった。林道は運転のしやすさを考慮して設計される。そのため、道が地形に沿わない場所では斜面を削り、沢を渡す橋をいくつも架けた。結果として山中に大量のコンクリート構造物をつくることからコストはかさみ、自然にも少なからず負荷がかかった。
作業道をつける際にも、将来的な再利用を想定しないことが多く、また、工事で出た不要な土砂を谷に捨てるなど、環境への配慮にも欠けていた。
一方の田邊氏は、森林になるべくダメージを与えず、林業の生産性を高める手法を考案し、全国各地の森林で技術を伝えていた。特に従来の道づくりの障害と見なされていた木々や根株、表土や石を破棄せず、徹底的に活用する点で画期的だった。
伐り倒した木の根株は土留めとして再利用し、土中から出る石などを活用して作業道の強度を高める。地表から深さ20cm程度までの土は無数の微生物の温床であり、植物の生育に欠かせない栄養素をたっぷりと含んでいるから、そうした表土で路肩を覆い、周囲の生態系と開設したての道がなるべく早く馴染むように工夫する。
さらに作業道の傾斜や勾配を利用して、雨水等が路面を川のにように流れないよう、分水や排水を促した。安易に橋をかけたり地中に管を埋めて水路をつくると、豪雨で破壊された際に復旧しづらく、自然への影響も甚大になる恐れがあるからだ。
道をつける上で生じる木の伐採と、地面の掘削による自然への負荷を最小限にとどめること。既存の資源を最大限に利用すること。その上で林業従事者が効率よく森に出入りできること。これらを満たすのが、田邊氏が編み出した手法なのだ。

独立して道づくりを始める
足立さんは林業会社で大規模で効率を重視した現場を経験し、行政の立場から森づくりに携わった。そして田邊氏のもとで作業道づくりの技術を身に付けたことで、自らが理想とする方向性を見つけた。
豊かな森林を未来に残すために自分ができることは、多様な樹木が集まる森を育てながら、必要に応じて木を伐り出すこと。それをおこなうために、林業者が優れたパフォーマンスを発揮できて、必要最小限の規模にとどめた作業道をつくること。
しかし現実には、そのような道は非常に少なく、伐採された木の多くは収穫されず森に残され、有意義に活用される機会を失っている。
「既存の林業にはもったいないことが多い」と足立さんは常々感じていた。
大規模な土木工事が不要な作業道を増やすことは、決して難しいことではない。もし道があれば、いつでも森から丸太を運び出すことができるようになり、「もったいない」を減らしていける。
道の用途は林業だけにはとどまらない。グリーンツーリズムや教育、林業体験などにも活用できる。様々な目的のために山や森が利用されるようになれば、一般の人々が気軽に森と接する機会が増える。それは林業への理解を深めることにもつながる。「木こりになりたい」と思う若い世代も増えるに違いない。
森の未来像をはっきりと描くようになった足立さんは、当時の林業界ではまだ注目されていなかった「環境保全型林業」を実践すべく、役場の仕事を辞めて森に戻ることにした。
こうして"森林作業道づくりに明け暮れる木こり"が誕生したのだった。
足立さんは林業会社で大規模で効率を重視した現場を経験し、行政の立場から森づくりに携わった。そして田邊氏のもとで作業道づくりの技術を身に付けたことで、自らが理想とする方向性を見つけた。
豊かな森林を未来に残すために自分ができることは、多様な樹木が集まる森を育てながら、必要に応じて木を伐り出すこと。それをおこなうために、林業者が優れたパフォーマンスを発揮できて、必要最小限の規模にとどめた作業道をつくること。
しかし現実には、そのような道は非常に少なく、伐採された木の多くは収穫されず森に残され、有意義に活用される機会を失っている。
「既存の林業にはもったいないことが多い」と足立さんは常々感じていた。
大規模な土木工事が不要な作業道を増やすことは、決して難しいことではない。もし道があれば、いつでも森から丸太を運び出すことができるようになり、「もったいない」を減らしていける。
道の用途は林業だけにはとどまらない。グリーンツーリズムや教育、林業体験などにも活用できる。様々な目的のために山や森が利用されるようになれば、一般の人々が気軽に森と接する機会が増える。それは林業への理解を深めることにもつながる。「木こりになりたい」と思う若い世代も増えるに違いない。
森の未来像をはっきりと描くようになった足立さんは、当時の林業界ではまだ注目されていなかった「環境保全型林業」を実践すべく、役場の仕事を辞めて森に戻ることにした。
こうして"森林作業道づくりに明け暮れる木こり"が誕生したのだった。

作業道のつくり方
奥三角山を歩いた翌日、足立さんと僕は札幌市の北にある手稲山に赴いた。かつて北海道や東北地方の一部に存在した、馬で丸太を搬出する「馬搬(ばはん)」を復興させる友人から依頼で、作業道づくりの現地調査をおこなうためだ。足立さんは今回の仕事を、ガイさんとユズルくんという、まだ経験の浅いふたりの木こり仲間と進めていた。
森の入口に立つと、背の高いチシマザサが立ちはだかっていた。まるでイスラエルとパレスチナを隔てる無慈悲な分離壁のようだ。この大型のササは積雪しても枯死することなく、春になると再び成長する生命力の強い植物だ。若芽は「ネマガリダケ」と呼ばれ食用にされる他、竹細工の素材として、または万病に効く薬草として古来より重宝がられてきた。 3人の木こりたちが草刈機でリズムよく下草を刈り始める。しばらくすると森の中を見渡せるようになり、地形が明らかになってきた。
3人の木こりたちが草刈機でリズムよく下草を刈り始める。しばらくすると森の中を見渡せるようになり、地形が明らかになってきた。
デジタルの粗いドットのような光が差し込む森に足を踏み入れる。当然ながら、そこに道はなく、ぬかるみや急斜面に足を取られ、簡単には前に進めない。登山道を歩くのと藪を漕ぎ進むのでは、消費する体力が全く異なると、僕は汗だくになりながら痛感した。
足元から川の流れる音が聞こえてきた。この沢が、この山に道をつける上での最初の難関のようだ。
困難な地形に頭を悩ませる足立さん。地形図を手に、ふたりの木こりと話し合う。迂回するか、いっそ橋を渡してしまうか。ありったけの可能性を洗い出しながら、利用しやすく、かつ森林への負担を最小限に抑える方法を模索する。
奥三角山を歩いた翌日、足立さんと僕は札幌市の北にある手稲山に赴いた。かつて北海道や東北地方の一部に存在した、馬で丸太を搬出する「馬搬(ばはん)」を復興させる友人から依頼で、作業道づくりの現地調査をおこなうためだ。足立さんは今回の仕事を、ガイさんとユズルくんという、まだ経験の浅いふたりの木こり仲間と進めていた。
森の入口に立つと、背の高いチシマザサが立ちはだかっていた。まるでイスラエルとパレスチナを隔てる無慈悲な分離壁のようだ。この大型のササは積雪しても枯死することなく、春になると再び成長する生命力の強い植物だ。若芽は「ネマガリダケ」と呼ばれ食用にされる他、竹細工の素材として、または万病に効く薬草として古来より重宝がられてきた。

デジタルの粗いドットのような光が差し込む森に足を踏み入れる。当然ながら、そこに道はなく、ぬかるみや急斜面に足を取られ、簡単には前に進めない。登山道を歩くのと藪を漕ぎ進むのでは、消費する体力が全く異なると、僕は汗だくになりながら痛感した。
足元から川の流れる音が聞こえてきた。この沢が、この山に道をつける上での最初の難関のようだ。
困難な地形に頭を悩ませる足立さん。地形図を手に、ふたりの木こりと話し合う。迂回するか、いっそ橋を渡してしまうか。ありったけの可能性を洗い出しながら、利用しやすく、かつ森林への負担を最小限に抑える方法を模索する。

「多分こっちのルートだな」
「でも、あそこの木は残しておきたいよね」
さらに森の奥へと進むと、かつてブルドーザーを通行させるためにつけられた、直線的な道が残されていた。熊よけのベルを付けた地元の老人が、轍の上を歩いてきのこを探している。
周囲にはニレの大木がいくつも立っていた。木こりたちはあたりを見渡しながら話し合う。
「ここ、なんか嫌だな」
「掘ったら大水が出るね、きっと」
ニレは水を好む植物だから、近くに沢があってもいいはずなのに、どこにも見えない。ということは地下に水脈がある可能性が高い。別のルートを取ったほうが賢明だ。
さらに木こりたちは二手に分かれて調査を続けた。きつい斜面や入り組んだ沢をものともせず、まるで野生動物のような軽やかさで森を徘徊する3人。足立さんは藪を狩りながら奥へ進み、高い地点を目指した。ときどき木に登ってあたりを見回し、森の全体像を把握しようと試みる。 彼らのペースには到底ついていけないと感じた僕は、一緒に行動することを諦めて、近くの自然歩道に出て休憩を取ることにした。
彼らのペースには到底ついていけないと感じた僕は、一緒に行動することを諦めて、近くの自然歩道に出て休憩を取ることにした。
丸太で作られたベンチを見つけて腰を掛ける。藪漕ぎの苦労から開放された私は、深呼吸をしてまわりを見渡した。依頼人の話と地形図から、木こりたちはカラマツ林を想像していたようだが、実際には広葉樹がかなりの割合を占める、天然林に近い森だ。エゾマツ、シラカバ、ナラ、シナ、キハダなどが混在する、これぞ北海道の森という植生が広がっている。クリスマスツリーのような葉を持つハイイヌガヤが生い茂っていたので、実を取って手で潰してみると、蒸留酒のジンとよく似たウッディな香りが広がった。光の差し込み方、木々の密度、湧き水が集まる音。北方の天然林は、どこまでも端正で清々しい。
「でも、あそこの木は残しておきたいよね」
さらに森の奥へと進むと、かつてブルドーザーを通行させるためにつけられた、直線的な道が残されていた。熊よけのベルを付けた地元の老人が、轍の上を歩いてきのこを探している。
周囲にはニレの大木がいくつも立っていた。木こりたちはあたりを見渡しながら話し合う。
「ここ、なんか嫌だな」
「掘ったら大水が出るね、きっと」
ニレは水を好む植物だから、近くに沢があってもいいはずなのに、どこにも見えない。ということは地下に水脈がある可能性が高い。別のルートを取ったほうが賢明だ。
さらに木こりたちは二手に分かれて調査を続けた。きつい斜面や入り組んだ沢をものともせず、まるで野生動物のような軽やかさで森を徘徊する3人。足立さんは藪を狩りながら奥へ進み、高い地点を目指した。ときどき木に登ってあたりを見回し、森の全体像を把握しようと試みる。

丸太で作られたベンチを見つけて腰を掛ける。藪漕ぎの苦労から開放された私は、深呼吸をしてまわりを見渡した。依頼人の話と地形図から、木こりたちはカラマツ林を想像していたようだが、実際には広葉樹がかなりの割合を占める、天然林に近い森だ。エゾマツ、シラカバ、ナラ、シナ、キハダなどが混在する、これぞ北海道の森という植生が広がっている。クリスマスツリーのような葉を持つハイイヌガヤが生い茂っていたので、実を取って手で潰してみると、蒸留酒のジンとよく似たウッディな香りが広がった。光の差し込み方、木々の密度、湧き水が集まる音。北方の天然林は、どこまでも端正で清々しい。

しばらくすると藪の方からガサガサと音が聞こえてきた。ヒグマかもと思い身構えると、2メートル近いクマザサが立ちはだかる茂みの奥から、ガイさんが目を輝かせて現れた。
「この森はすごく気持ちいい。死ぬほど笹を漕いだけどね」
やがて足立さんの声が近づいてきたので、私は快適な自然歩道を後にして、再び藪に入って彼と合流した。彼は息を切らせながら僕に説明した。
「本来なら、もっと時間をかけて道をつけるのが自分のやり方です。地域の歴史や文化的背景をリサーチして、グーグルマップを眺めてイメージを膨らませる。冬の間に森をくまなく歩いて調査する時間も欲しい。今回は『雪が降り始める前に道をつけてほしい』という依頼なので、仕方なく笹薮をガサゴソ漕ぎながらやっているわけですが」
足立さんの道づくりは、田邊氏の手法をベースに、北海道の環境を考慮して編み出した独自のもの。田邊氏が拠点とする高知県と違い、北海道の山岳部は1年のうちのおよそ半分が雪で閉ざされる。それは林業にとって大きなハンデだが、その気候条件を逆手に取って調査を進めることも可能なのだ。普段は見通しの悪い森も冬の間は落葉して視界が開け、足元を遮る強靭なササは雪の中で眠っている。雪上をスキーで滑れば、歩き回るよりもずっと効率的に調査を進められる。彼は「ゾンメルスキー」という、板のソールにアザラシの毛皮を貼った骨董品のようなスキーを履いて動き回り、地形を把握しながら、冬の間に作業道の大まかなルートを決めてゆく。
「この森はすごく気持ちいい。死ぬほど笹を漕いだけどね」
やがて足立さんの声が近づいてきたので、私は快適な自然歩道を後にして、再び藪に入って彼と合流した。彼は息を切らせながら僕に説明した。
「本来なら、もっと時間をかけて道をつけるのが自分のやり方です。地域の歴史や文化的背景をリサーチして、グーグルマップを眺めてイメージを膨らませる。冬の間に森をくまなく歩いて調査する時間も欲しい。今回は『雪が降り始める前に道をつけてほしい』という依頼なので、仕方なく笹薮をガサゴソ漕ぎながらやっているわけですが」
足立さんの道づくりは、田邊氏の手法をベースに、北海道の環境を考慮して編み出した独自のもの。田邊氏が拠点とする高知県と違い、北海道の山岳部は1年のうちのおよそ半分が雪で閉ざされる。それは林業にとって大きなハンデだが、その気候条件を逆手に取って調査を進めることも可能なのだ。普段は見通しの悪い森も冬の間は落葉して視界が開け、足元を遮る強靭なササは雪の中で眠っている。雪上をスキーで滑れば、歩き回るよりもずっと効率的に調査を進められる。彼は「ゾンメルスキー」という、板のソールにアザラシの毛皮を貼った骨董品のようなスキーを履いて動き回り、地形を把握しながら、冬の間に作業道の大まかなルートを決めてゆく。

実際に道をつけるのは春になってからである。暖かくなり雪が溶けてから、冬の間に決めておいた道筋に沿って下草を刈る。そして地形を確認しながらルートを確定する。作業道と重なる木や道をさえぎる倒木を伐採して、パワーショベルで慎重に地面を剥がし、地中から出る土砂や根株、岩などを利用して地面を締め固めれば、作業道はひととおり完成する。

足立成亮/林業家
1982年・札幌生まれ。2009年に林業の世界へ。2013年に独立して〈outwoods〉を名乗る。自分たちが関わる山や森林を「ヤマ」と呼び、そこで生きるものや朽ちてゆくもの、すべての生態系が共存する未来を描いて、日々「ヤマ仕事」に明け暮れる。過去から現在に繋がる森の姿や、木こりが見る景色を、ワークショップなどを通じて積極的に発信し続けている。
-

FORESTER
Shigeaki Adachi
-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER
Kei Amano
-

BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER
Taiki Minakuchi
-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭 火付ぬ組
-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN
Yukihito Kanai
-

SAUNA BUILDER
nodaklaxonbebe