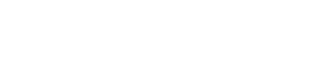Chapter 4 Vol.Four
SOUL BEAT ASIA
Hitsuke Nugumi
Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭
火付ぬ組
TEXT by TEXT by HAJIME OISHI
PHOTOGRAPHS by KANJI FURUKAWA
PHOTOGRAPHS by KANJI FURUKAWA
パンデミックによって橋の下世界音楽祭の開催を断念せざるを得ないなか、中心メンバーは突如農園を作り、土を耕し始めた。そこには「アートも音楽もすべて暮らしから生まれたものであり、今こそ暮らしを捉え直さなくてはいけない」という永山愛樹の信念があった。2022年ならではのルーツ&カルチャーなライフスタイルを切り開く橋の下世界音楽祭一派の現在をレポートする。
今回の記事を書くにあたって、最後にめざすべき場所は最初の段階から決まっていた。愛知県みよし市三好丘緑行政区で愛樹くんたちが始めた橋ノ下農園だ。
この記事の2回目で紹介したように、愛樹くんは以前から農業に強い関心を持っていたという。「結局すべては暮らしなんだよな。何を食べ、何を着るか、すべては暮らしから始まっている。そこを捉え直すことで自分の音楽も変わってくるんじゃないか」。そうした発想の延長上で、愛樹くんは仲間たちと畑を始めた。それが2021年5月のことだった。
橋ノ下農園を中心とする現在の彼らの活動は、2012年に始まった橋の下世界音楽祭のひとつの発展型ともいえる。そして、小難しい話を抜きにしても、SNSに日々アップされる農園での作業風景にどこかそそられるものがあったのだ。愛樹くんたちがまたおもしろそうなことを始めたみたいだ――そんなそわそわした思いを抱えながら、根木くんの運転する車に乗って西へと向かった。
橋ノ下農園のある三好丘行政区は、昭和50年代から住宅・都市整備公団(現在のUR都市機構)によって開発された新しい街だ。隣接する豊田市の自動車関連工場で働く人々が住むほか、名古屋市のベッドタウンとしても発展を遂げてきた。
東名高速の三好ICを降り、小高い丘を突き進んでいくと、広大なスペースの広がる橋ノ下農園に到着した。風が吹き抜け、空が広い。そこには数分前までの開発都市然とした景観とは異なる、清々しい農園風景が広がっていた。一角には開発時期に建てられたであろう住宅が並んでいて、そう古くはない時期に丘の一角が宅地化されたことが見て取れる。
この記事の2回目で紹介したように、愛樹くんは以前から農業に強い関心を持っていたという。「結局すべては暮らしなんだよな。何を食べ、何を着るか、すべては暮らしから始まっている。そこを捉え直すことで自分の音楽も変わってくるんじゃないか」。そうした発想の延長上で、愛樹くんは仲間たちと畑を始めた。それが2021年5月のことだった。
橋ノ下農園を中心とする現在の彼らの活動は、2012年に始まった橋の下世界音楽祭のひとつの発展型ともいえる。そして、小難しい話を抜きにしても、SNSに日々アップされる農園での作業風景にどこかそそられるものがあったのだ。愛樹くんたちがまたおもしろそうなことを始めたみたいだ――そんなそわそわした思いを抱えながら、根木くんの運転する車に乗って西へと向かった。
橋ノ下農園のある三好丘行政区は、昭和50年代から住宅・都市整備公団(現在のUR都市機構)によって開発された新しい街だ。隣接する豊田市の自動車関連工場で働く人々が住むほか、名古屋市のベッドタウンとしても発展を遂げてきた。
東名高速の三好ICを降り、小高い丘を突き進んでいくと、広大なスペースの広がる橋ノ下農園に到着した。風が吹き抜け、空が広い。そこには数分前までの開発都市然とした景観とは異なる、清々しい農園風景が広がっていた。一角には開発時期に建てられたであろう住宅が並んでいて、そう古くはない時期に丘の一角が宅地化されたことが見て取れる。

広々とした畑の奥へと目をやると、一台の軽トラックが停まっていて、「おー、大石くん、おつかれさまです!」という声が聞こえてきた。橋の下世界音楽祭運営チーム「火付ぬ組」の一員であるノブさんだ。
軽トラックの荷台には大きな窯がセットされていて、その上には2、3メートルはあるだろう煙突が空に向かって真っ直ぐ伸びている。実はこの窯、金属造形作家の戸谷真也さんとノブさんが作り上げた世界でひとつのオリジナル。橋の下世界音楽祭では横丁の一角に「鍛鐡(たんてつ)組」が現れ、参加者の目を楽しませているが、戸谷さんはその鍛冶屋のチームのひとりだという。まさか窯まで自分たちで作り上げてしまうとは、なんでもかんでも自作してしまう橋の下の本領発揮である。
「結局、この10年間で培ってきた人間関係のおかげで、こういうものをすぐ形にできるんだよね」
ノブさんはそう話しながら、自慢の窯でサツマイモをころころと焼いている。もちろんサツマイモも橋ノ下農園で収穫したもの。ノブさんはときたま自分たちで育てたサツマイモを自分たちの窯で調理し、畑で汗を流す仲間たちに振る舞っているらしい。農園で穫れた新鮮な野菜を乗せた自家製ピザは子供たちにも大人気だという。話を聞いているだけでヨダレが出てきてしまう。
なお、収穫されたサツマイモの一部は近隣の酒蔵にて委託製造され、今春には芋焼酎になる予定。彼らのことだから、いずれ焼酎の醸造システム自体作ってしまいそうだが、まずはひとつひとつ計画を実現しているといったところか。ノブさんはこう話す。
「産直でイモを売らないかという話も来たんだけど、そうすると、他の農家さんとの価格競争になっちゃう。こっちは自然農法でやってるし、どうしても高くなるんだよね。流通を否定しないけれど、ライヴのときに物販でCDを売るようにフェイストゥフェイスで売るのが一番いいし、だったら焼き芋にして売るのがいいんじゃないかと思ってね。で、『焼き芋を作るんだったら窯も自分たちで作りたいね』っていういつもの橋の下精神が出てきちゃって(笑)」
ノブさんはそう話し、慣れた手つきでサツマイモを転がす。完成してさほど時間が経っていないにもかかわらず、ノブさん自慢の窯は早くも風格を漂わせていた。今後使い込まれることでさらに輝きを増していくのだろう。窯ひとつ、サツマイモひとつにも橋の下のスピリットが宿っているように思えた。
 ノブさんと話していたら、美岳小屋の林剛さんがやってきた。林さんは三好丘や豊田市内で無農薬農業に取り組む人物。橋ノ下農園は林さんの農園の一部を間借りしており、愛樹くんたちの農業の師匠ともいうべき存在だ。ノブさんや根木くんと「今日のイチゴは出来がよくなくて」と会話をするその光景は、農家同士のコミュニケーションといった感じもする。
ノブさんと話していたら、美岳小屋の林剛さんがやってきた。林さんは三好丘や豊田市内で無農薬農業に取り組む人物。橋ノ下農園は林さんの農園の一部を間借りしており、愛樹くんたちの農業の師匠ともいうべき存在だ。ノブさんや根木くんと「今日のイチゴは出来がよくなくて」と会話をするその光景は、農家同士のコミュニケーションといった感じもする。
豊田市で10年間消防士として働いていたという林さんは、その経歴どおりの爽やかな青年だった。自然栽培で育てた落花生をたっぷり使い、みずから加工したというピーナッツバターを挨拶がてら僕に手渡すと、この土地の歴史について語り始めた(ちなみに、いただいたピーナッツバターは衝撃的な美味しさだった)。
「ここはおじいちゃんの開拓仲間の畑なんです。このあたりは戦後まもなくの時期、いろんな土地からやってきた人たちが開拓した場所で、おじいちゃんももともとは長野からやってきたんですよ。宅地が広がったのはここ20年ぐらいで、もともとは山と農地です。若い農家さんがいないこともあって、農地を売っちゃうか継ぐかという決断を迫られて、やってくれないかと相談されたんです。消防士をやっていたころから、いずれ自分も農業をやるのかなとは思っていました」
軽トラックの荷台には大きな窯がセットされていて、その上には2、3メートルはあるだろう煙突が空に向かって真っ直ぐ伸びている。実はこの窯、金属造形作家の戸谷真也さんとノブさんが作り上げた世界でひとつのオリジナル。橋の下世界音楽祭では横丁の一角に「鍛鐡(たんてつ)組」が現れ、参加者の目を楽しませているが、戸谷さんはその鍛冶屋のチームのひとりだという。まさか窯まで自分たちで作り上げてしまうとは、なんでもかんでも自作してしまう橋の下の本領発揮である。
「結局、この10年間で培ってきた人間関係のおかげで、こういうものをすぐ形にできるんだよね」
ノブさんはそう話しながら、自慢の窯でサツマイモをころころと焼いている。もちろんサツマイモも橋ノ下農園で収穫したもの。ノブさんはときたま自分たちで育てたサツマイモを自分たちの窯で調理し、畑で汗を流す仲間たちに振る舞っているらしい。農園で穫れた新鮮な野菜を乗せた自家製ピザは子供たちにも大人気だという。話を聞いているだけでヨダレが出てきてしまう。
なお、収穫されたサツマイモの一部は近隣の酒蔵にて委託製造され、今春には芋焼酎になる予定。彼らのことだから、いずれ焼酎の醸造システム自体作ってしまいそうだが、まずはひとつひとつ計画を実現しているといったところか。ノブさんはこう話す。
「産直でイモを売らないかという話も来たんだけど、そうすると、他の農家さんとの価格競争になっちゃう。こっちは自然農法でやってるし、どうしても高くなるんだよね。流通を否定しないけれど、ライヴのときに物販でCDを売るようにフェイストゥフェイスで売るのが一番いいし、だったら焼き芋にして売るのがいいんじゃないかと思ってね。で、『焼き芋を作るんだったら窯も自分たちで作りたいね』っていういつもの橋の下精神が出てきちゃって(笑)」
ノブさんはそう話し、慣れた手つきでサツマイモを転がす。完成してさほど時間が経っていないにもかかわらず、ノブさん自慢の窯は早くも風格を漂わせていた。今後使い込まれることでさらに輝きを増していくのだろう。窯ひとつ、サツマイモひとつにも橋の下のスピリットが宿っているように思えた。

豊田市で10年間消防士として働いていたという林さんは、その経歴どおりの爽やかな青年だった。自然栽培で育てた落花生をたっぷり使い、みずから加工したというピーナッツバターを挨拶がてら僕に手渡すと、この土地の歴史について語り始めた(ちなみに、いただいたピーナッツバターは衝撃的な美味しさだった)。
「ここはおじいちゃんの開拓仲間の畑なんです。このあたりは戦後まもなくの時期、いろんな土地からやってきた人たちが開拓した場所で、おじいちゃんももともとは長野からやってきたんですよ。宅地が広がったのはここ20年ぐらいで、もともとは山と農地です。若い農家さんがいないこともあって、農地を売っちゃうか継ぐかという決断を迫られて、やってくれないかと相談されたんです。消防士をやっていたころから、いずれ自分も農業をやるのかなとは思っていました」

林さんの農業の中心はイチゴと落花生である。ここに来るまでに大規模な畑をいくつも見かけたが、このあたりはイチゴと落花生を作る農家が多いのだろうか。
「いや、僕らだけですね。だいたいスイカとか、冬は大根と白菜、以前はサツマイモをやってたエリアもあったみたいで。僕は単純にそういうものをやりたくなかったんですよ」
「どうして?」
「スイカは子供のときに食べすぎて好きじゃないんですよ(笑)。あと、おじいさんはこのへんのJAから抜けているので、ハナっからこれを育てないといけないという縛りが僕にはないんですよ。自然農法でイチゴを作ってる農家さんが豊田にいて、僕も単純な挑戦心でイチゴ栽培を始めました」
この発言を少し解説しておこう。通常の場合、農家はJA(農協)に加入することで、農業にまつわるさまざまなサポートを受けることができる。たとえば、JAを通じて種や肥料などを安価で購入することができるし、販売にまつわる相談を聞いてもらったりと、経営や技術に関する営農指導を受けることもできる。農業にまつわるあらゆる面でのサポートを受けられるJAの存在は、決して悪いことばかりではないのだ。だが、その一方で、特定の作物の栽培が推奨されたりと、JAに加入することで収穫する品目や農法がある程度制限されることもあるという。
林さんの場合、JAからのサポートを受けない代わりに制約のない農業に挑んでいるのだ。
「おじいさんは肥料や農薬を使った農業をやっていて、自分も手伝ってたんですよ。でも、どうも違和感があって……」
「どんな違和感?」
「農業って自然と対峙するものというイメージがあったんだけど、肥料を決まった分量まいて、決まった時期に農薬を散布すれば、基本的に決まった時期に収穫することができる。自然のもののはずなのに、工業製品みたいに作られていて、機械的な感じがしたんです。天気によってうまくいかないこともあるはずなのに、ある程度操作できちゃう。そうやって食べ物が作られていたことを知らなかったので、余計に違和感があって」
「そういえば、先ほど林さんは『今日のイチゴは出来がよくなかった』と言ってましたよね」
「そうですね。イチゴに限らず、農作物って前日の天候が影響してくるんですよ。二日間ぐらい晴れの日が続かないと、実に養分が送られなくて美味しくない。でも、大量に生産してる農家は輸送のタイミングで収穫する日を決めるんですね。収穫してから1日かけてパック詰めされて、スーパーとかに順次配送されていくので、収穫してからのタイムラグが大きい。僕らは収穫した日に直接お店に持っていくので、穫った日が出荷日になるんです」
こうやって書き起こすと、肥料や農薬を使用し、JAを通して出荷する通常の農家を批判しているように思われるかもしれない。だが、林さんは「通常の農法が一概に悪いというわけじゃなくて」と前置きしたうえで、こう続ける。
「そういう農法のおかげで日本どこに行ってもどんな農産物も手に入るわけで。だから、自分がやってる農法が正しいというわけじゃなくて、両方あっていいと思うんですよ」
林さんも理想だけで金を稼げるわけではない。仕事として成立させるためにさまざまな苦労をしている。
「自然農法だと穫れる量も通常の1/3ぐらいになるんで、通常のイチゴより販売価格は高くなっちゃうんですよね。出荷する場所もなかなかなくて、最初は県外ばかり。一週間に一度東京のFarmers Marketに出店して、そこで出会った方が買ってくれるようになりました。やっぱり農業としてはハードルが高いし、だからこそ自然農法のいちご農家が増えないんですよね」
林さんとそんな話をしていたら、今度は年季の入ったハイエースに乗って愛樹くんがやってきた。
林さんと愛樹くんが出会ったのは2020年初頭のこと。林さんはもともと橋の下世界音楽祭に観客として遊びに行った経験があったほか、BRAHMANのTOSHI-LOWさんが立ち上げたNPO法人「幡ヶ谷再生大学」に参加している経緯もあり、ミュージシャンによる被災地の復興支援や農業体験に刺激を受けていたという。会うべくして会ったという感じがするが、愛樹くんや根木くんには人を招き寄せる引力みたいなものがあるのだ。
「いや、僕らだけですね。だいたいスイカとか、冬は大根と白菜、以前はサツマイモをやってたエリアもあったみたいで。僕は単純にそういうものをやりたくなかったんですよ」
「どうして?」
「スイカは子供のときに食べすぎて好きじゃないんですよ(笑)。あと、おじいさんはこのへんのJAから抜けているので、ハナっからこれを育てないといけないという縛りが僕にはないんですよ。自然農法でイチゴを作ってる農家さんが豊田にいて、僕も単純な挑戦心でイチゴ栽培を始めました」
この発言を少し解説しておこう。通常の場合、農家はJA(農協)に加入することで、農業にまつわるさまざまなサポートを受けることができる。たとえば、JAを通じて種や肥料などを安価で購入することができるし、販売にまつわる相談を聞いてもらったりと、経営や技術に関する営農指導を受けることもできる。農業にまつわるあらゆる面でのサポートを受けられるJAの存在は、決して悪いことばかりではないのだ。だが、その一方で、特定の作物の栽培が推奨されたりと、JAに加入することで収穫する品目や農法がある程度制限されることもあるという。
林さんの場合、JAからのサポートを受けない代わりに制約のない農業に挑んでいるのだ。
「おじいさんは肥料や農薬を使った農業をやっていて、自分も手伝ってたんですよ。でも、どうも違和感があって……」
「どんな違和感?」
「農業って自然と対峙するものというイメージがあったんだけど、肥料を決まった分量まいて、決まった時期に農薬を散布すれば、基本的に決まった時期に収穫することができる。自然のもののはずなのに、工業製品みたいに作られていて、機械的な感じがしたんです。天気によってうまくいかないこともあるはずなのに、ある程度操作できちゃう。そうやって食べ物が作られていたことを知らなかったので、余計に違和感があって」
「そういえば、先ほど林さんは『今日のイチゴは出来がよくなかった』と言ってましたよね」
「そうですね。イチゴに限らず、農作物って前日の天候が影響してくるんですよ。二日間ぐらい晴れの日が続かないと、実に養分が送られなくて美味しくない。でも、大量に生産してる農家は輸送のタイミングで収穫する日を決めるんですね。収穫してから1日かけてパック詰めされて、スーパーとかに順次配送されていくので、収穫してからのタイムラグが大きい。僕らは収穫した日に直接お店に持っていくので、穫った日が出荷日になるんです」
こうやって書き起こすと、肥料や農薬を使用し、JAを通して出荷する通常の農家を批判しているように思われるかもしれない。だが、林さんは「通常の農法が一概に悪いというわけじゃなくて」と前置きしたうえで、こう続ける。
「そういう農法のおかげで日本どこに行ってもどんな農産物も手に入るわけで。だから、自分がやってる農法が正しいというわけじゃなくて、両方あっていいと思うんですよ」
林さんも理想だけで金を稼げるわけではない。仕事として成立させるためにさまざまな苦労をしている。
「自然農法だと穫れる量も通常の1/3ぐらいになるんで、通常のイチゴより販売価格は高くなっちゃうんですよね。出荷する場所もなかなかなくて、最初は県外ばかり。一週間に一度東京のFarmers Marketに出店して、そこで出会った方が買ってくれるようになりました。やっぱり農業としてはハードルが高いし、だからこそ自然農法のいちご農家が増えないんですよね」
林さんとそんな話をしていたら、今度は年季の入ったハイエースに乗って愛樹くんがやってきた。
林さんと愛樹くんが出会ったのは2020年初頭のこと。林さんはもともと橋の下世界音楽祭に観客として遊びに行った経験があったほか、BRAHMANのTOSHI-LOWさんが立ち上げたNPO法人「幡ヶ谷再生大学」に参加している経緯もあり、ミュージシャンによる被災地の復興支援や農業体験に刺激を受けていたという。会うべくして会ったという感じがするが、愛樹くんや根木くんには人を招き寄せる引力みたいなものがあるのだ。

林さんは橋の下世界音楽祭のどのような部分に共感しているのだろうか?
「ないものを作っていくところですね。何もないところから始めて、続けるなかで人がついていく。何よりもみんな楽しそうだし、やりたいからやってる。僕らも変な使命感じゃなくて、自然農法でイチゴを作りたいからやってるんです。現代って右なら右、左なら左っていう傾向が強いし、自然農法のイチゴって評価されにくいんですよ。『そんなんじゃ生活できないよ』とも言われるし。でも、橋の下のみんなを見てると、これでいいんだと思えるんです」
「畑なんてそれまでやったこともなかったし、まったく生活が変わりましたね」――そう話すのは、TURTLE ISLANDのメンバー、竹舞さんだ。彼女も林さんの美岳小屋で週3、4日働いており、夏場ともなると、さらに日数は増えるという。
「コロナ禍になって今までやってきたことがやれなくなったし、その不自由さについていくことしかできなかった。受け止めようとしても受け止めきれないというか、心がついていかなかったんですよ。そんなときに農業を始めたんです」
「ないものを作っていくところですね。何もないところから始めて、続けるなかで人がついていく。何よりもみんな楽しそうだし、やりたいからやってる。僕らも変な使命感じゃなくて、自然農法でイチゴを作りたいからやってるんです。現代って右なら右、左なら左っていう傾向が強いし、自然農法のイチゴって評価されにくいんですよ。『そんなんじゃ生活できないよ』とも言われるし。でも、橋の下のみんなを見てると、これでいいんだと思えるんです」
「畑なんてそれまでやったこともなかったし、まったく生活が変わりましたね」――そう話すのは、TURTLE ISLANDのメンバー、竹舞さんだ。彼女も林さんの美岳小屋で週3、4日働いており、夏場ともなると、さらに日数は増えるという。
「コロナ禍になって今までやってきたことがやれなくなったし、その不自由さについていくことしかできなかった。受け止めようとしても受け止めきれないというか、心がついていかなかったんですよ。そんなときに農業を始めたんです」

音楽活動と農業はどんなところに共通点があるのだろうか。竹舞さんはこう話す。
「ものを食べたときの感覚は、舞台上で感じる感覚と近いかもしれない。ひと口食べたときに瞬時に違う世界に飛んでしまうというか。林くんはそこを追求してる感じがしますね。
愛樹くんはずっと農業をやりたいと言ってたし、自分の表現をやっていくうえで必要なことなんだと言ってたんです。私にはその言葉の意味がずっと分からなかったんだけど、ここで働き始めて少し分かった気がする」
竹舞さんはそう話すと、「ただ、ここにいるみんなは私よりももっと先を見てると思いますけどね」とつけ加えた。
そうやって橋ノ下農園に集う人々にひとりひとり話を聞いているうちに、いつのまにか愛樹くんを囲んで人の輪ができていた。そうこうするうちに、ノブさんが焼きたてのサツマイモを配り出す。熱々のサツマイモをポキッと折り、ほふほふと頬張ると、自然な甘さが口いっぱいに広がった。
その横で愛樹くんが畑からサンチュをむしってきて、ノブさんと同じようにみんなに配り始めた。愛樹くん持参の辛味噌をつけてむしゃむしゃと食らいつくと、これまた美味しい。畑の上なのに次々と食べ物が出てくるのだから、なんとも楽しい。
 取材が一通り終わったので、畑の一角に建てられた農楽堂の前で集合写真を撮影することになった。橋の下世界音楽祭の下町ステージを手がける米子のZERO ACTIONチームが短時間で作り上げたそうで、愛樹くんはいずれこの農楽堂でワークショップや芝居をやったりと、構想を膨らませているのだという。
取材が一通り終わったので、畑の一角に建てられた農楽堂の前で集合写真を撮影することになった。橋の下世界音楽祭の下町ステージを手がける米子のZERO ACTIONチームが短時間で作り上げたそうで、愛樹くんはいずれこの農楽堂でワークショップや芝居をやったりと、構想を膨らませているのだという。
つまり、愛樹くんがやりたかったのは、こういうことなのだ。天候を気にかけながら田畑を耕し、成長の度合いを見ながら野菜を収穫し、仲間たちとそれを食べ、語り合い、音楽を奏で、芸能を楽しむ。現代を生き抜くためのエネルギーと知恵を育み、自分たちのことを自分たちで治める。なるほど、自治とはこういうことなのか――僕は畑の上でひとりごちた。
新鮮なサンチュを頬張りながら、愛樹くんたちがあまりに巨大化してしまった橋の下世界音楽祭の代わりに、畑の上に自治空間を追い求めた訳が理解できた気がした。「魂の解放、命の洗濯」という橋の下世界音楽祭の理念は、土の上に生きていたのだ。
夜は橋の下世界音楽祭が運営するコミュニティースペース、橋ノ下舎で宴となった。豊田市駅にもほど近い空き家の二階を利用した橋ノ下舎はカルチャーセンターとしての側面もあり、民謡のワークショップや木遣り寺子屋、アコースティックライヴ、映画上映会がたびたび開催されている。
「ものを食べたときの感覚は、舞台上で感じる感覚と近いかもしれない。ひと口食べたときに瞬時に違う世界に飛んでしまうというか。林くんはそこを追求してる感じがしますね。
愛樹くんはずっと農業をやりたいと言ってたし、自分の表現をやっていくうえで必要なことなんだと言ってたんです。私にはその言葉の意味がずっと分からなかったんだけど、ここで働き始めて少し分かった気がする」
竹舞さんはそう話すと、「ただ、ここにいるみんなは私よりももっと先を見てると思いますけどね」とつけ加えた。
そうやって橋ノ下農園に集う人々にひとりひとり話を聞いているうちに、いつのまにか愛樹くんを囲んで人の輪ができていた。そうこうするうちに、ノブさんが焼きたてのサツマイモを配り出す。熱々のサツマイモをポキッと折り、ほふほふと頬張ると、自然な甘さが口いっぱいに広がった。
その横で愛樹くんが畑からサンチュをむしってきて、ノブさんと同じようにみんなに配り始めた。愛樹くん持参の辛味噌をつけてむしゃむしゃと食らいつくと、これまた美味しい。畑の上なのに次々と食べ物が出てくるのだから、なんとも楽しい。

つまり、愛樹くんがやりたかったのは、こういうことなのだ。天候を気にかけながら田畑を耕し、成長の度合いを見ながら野菜を収穫し、仲間たちとそれを食べ、語り合い、音楽を奏で、芸能を楽しむ。現代を生き抜くためのエネルギーと知恵を育み、自分たちのことを自分たちで治める。なるほど、自治とはこういうことなのか――僕は畑の上でひとりごちた。
新鮮なサンチュを頬張りながら、愛樹くんたちがあまりに巨大化してしまった橋の下世界音楽祭の代わりに、畑の上に自治空間を追い求めた訳が理解できた気がした。「魂の解放、命の洗濯」という橋の下世界音楽祭の理念は、土の上に生きていたのだ。
夜は橋の下世界音楽祭が運営するコミュニティースペース、橋ノ下舎で宴となった。豊田市駅にもほど近い空き家の二階を利用した橋ノ下舎はカルチャーセンターとしての側面もあり、民謡のワークショップや木遣り寺子屋、アコースティックライヴ、映画上映会がたびたび開催されている。

夕飯のメインディッシュは、愛樹くん特製のカムジャタンとチヂミだ。愛樹くんの作ったエゴマがたっぷり乗ったカムジャタンには深い味わいがあり、スープを飲み干してもなお皿を舐めまわしたくなるほどの美味さ。橋ノ下農園で収穫した野菜もたっぷり使われていて、食べれば食べるほど体内からエネルギーが湧き上がってくる。最高の料理のおかげで、大量に買ってきたはずのマッコリのボトルが次々と空いていく。
僕らはいったい何時ごろまで話していたのだろうか? 携帯電話で時間やメールをチェックするのは早い時間でやめてしまった。その代わりに今後のアイデアやヴィジョンを語り合い、くだらない冗談で笑い転げた。これほどまでに希望に溢れた夜は久々だった。
橋の下に集う面々も、かつては特定のカルチャーに憧れ、そのカルチャーに同化することで自分という存在を構築してきた。愛樹くんならばパンク、根木くんならば横浜のアンダーグラウンドなサブカルチャー。僕だって中学生のころは欧米のロックにのめり込み、一時はアメリカへの移住を本気で考えたこともあった。
だが、すべての「カルチャー」とは暮らしの上に成り立っている。暮らしとは、生きることに関わるすべてのことと同義であり、音楽にしてもアートにしても、それこそ祭りや芸能だって暮らしの上に成り立っている。地盤を耕さないことには、どんな「カルチャー」だって実ることはない。
僕らはいったい何時ごろまで話していたのだろうか? 携帯電話で時間やメールをチェックするのは早い時間でやめてしまった。その代わりに今後のアイデアやヴィジョンを語り合い、くだらない冗談で笑い転げた。これほどまでに希望に溢れた夜は久々だった。
橋の下に集う面々も、かつては特定のカルチャーに憧れ、そのカルチャーに同化することで自分という存在を構築してきた。愛樹くんならばパンク、根木くんならば横浜のアンダーグラウンドなサブカルチャー。僕だって中学生のころは欧米のロックにのめり込み、一時はアメリカへの移住を本気で考えたこともあった。
だが、すべての「カルチャー」とは暮らしの上に成り立っている。暮らしとは、生きることに関わるすべてのことと同義であり、音楽にしてもアートにしても、それこそ祭りや芸能だって暮らしの上に成り立っている。地盤を耕さないことには、どんな「カルチャー」だって実ることはない。

愛樹くんや根木くんたちは、メディアによってコントロールされた社会システムとは別の場所に、自立した自分たちの暮らしを作り上げようとしている。そして、2012年の橋の下世界音楽祭以降、彼らのそうした思想に賛同する人々が少しずつ増えているのだ。
重機ひとつ動かせず、土木の知識も体力もない僕から見ると、なにもかも自分たちで作ってしまう彼らは特殊能力の持ち主にも思えるが、橋の下に集う面々は決して特別な人間ではない。長い時間をかけて、生きるために必要な知識と技術を蓄えてきただけのことなのだ。
今からだって遅くはない。やる気になれば橋の下世界音楽祭は誰だって始めることができるはずだ。
重機ひとつ動かせず、土木の知識も体力もない僕から見ると、なにもかも自分たちで作ってしまう彼らは特殊能力の持ち主にも思えるが、橋の下に集う面々は決して特別な人間ではない。長い時間をかけて、生きるために必要な知識と技術を蓄えてきただけのことなのだ。
今からだって遅くはない。やる気になれば橋の下世界音楽祭は誰だって始めることができるはずだ。

橋の下世界音楽祭・火付ぬ組
2012年9月、愛知県豊田市で始まった音楽祭。豊田大橋の下に広がる広大なスペースを会場としており、ジャンルを超えたパフォーマーが登場するほか、さまざまなワークショップも行われる。運営チームには個性豊かな顔ぶれが揃っており、彼らは「火付(ひつけ)ぬ組」という集団を構成している。これまでの主な出演者は、TURTLE ISLAND、ハンガイ、マージナル、切腹ピストルズ、OKI DUB AINU BAND、大城美佐子、折坂悠太、THA BLUE HERB、阿波踊り太閤連、T字路s、遠藤ミチロウなど。2021年7月は東京オリンピックに合わせて「橋の下盆踊りンピック」が開催。こちらも大きな話題となった。
-

FORESTER
Shigeaki Adachi
-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER
Kei Amano
-

BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER
Taiki Minakuchi
-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭 火付ぬ組
-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN
Yukihito Kanai
-

SAUNA BUILDER
nodaklaxonbebe