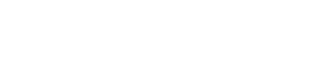Chapter 8 Vol.Two
EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
Tomoki Koharu
小春友樹
江戸和竿を使った小物釣りでは、2センチ以下の小さなタナゴやコブナが対象魚となる。釣り上げた魚の数や大きさは重要ではない。むしろその小ささが競われるのだという。埼玉県川越市で江戸和竿の職人として腕を磨く小春友樹は、そうした小物釣りに魅了され、職人としての道を歩み始めた。江戸の庶民文化の奥深さを伝える江戸和竿の世界。そこには合理性や効率を度外視したものづくりの美学があった。
パンデミックの最中、国内での釣り人気は大きく回復した。屋外のため感染リスクが低く、なおかつ遠方まで出かけずとも近隣の河川や港で楽しむことができるため、手軽なレジャーとして注目を集めているというのだ。
では、江戸和竿に対する注目度に変化はあったのだろうか。試しにYouTubeで「江戸和竿」と検索をかけてみると、思いのほか多くの動画がアップされているではないか(なかには小春さんのインタヴュー動画もある)。だが、その多くは「今、江戸和竿が人気!」というような浮ついたものではない。時代の流れとは無関係にその世界を楽しもうという、どこかストイックな雰囲気をまとっている。
東京都産業労働局のウェブサイトでは江戸和竿の伝統的な技術・技法についてこのように解説されている。
1. 切り組みは、作ろうとする竿の種類に応じて、全長・調子などを考え、竹を選別して切る。
2. 火入れ(矯め)は、竹に火をとおしながら、油抜きをし、矯め木にて真直ぐにする。
3. 継ぎは、継ぎ口を寸分のヌキのないように仕上げる。継ぎ方は、並継ぎと印篭継ぎとする。
4. 塗りは、精製漆の摺り漆仕上げとする。
かなり簡略化した解説ではあるものの、この一文だけで江戸和竿が大量生産のレジャー用品ではなく、職人の手による伝統工芸品として生産されてきたことが伝わってくる。江戸和竿を制作するうえでのポイントを小春さんに解説していただこう。 「まず、いい竹を手に入れること。西洋の竿は竹を削って好きな形にしちゃうんですけど、和竿は削らないんです。なので、最初に選ぶ竹が重要なんですよね。そのあとにくるのが、竹をまっすぐにする火入れ。ここが難しいんですよ」
 火入れによってまっすぐに成形した竹には糸を巻き、漆を塗る。ただし、一度塗っては磨き、塗っては磨きと、その工程を実に30回も繰り返すのである。
火入れによってまっすぐに成形した竹には糸を巻き、漆を塗る。ただし、一度塗っては磨き、塗っては磨きと、その工程を実に30回も繰り返すのである。
「漆を塗るのは大変なんですよ。乾かす際には(工房の)湿度や温度を一定にしないといけないし、それがうまくいかないと次の日も乾いていなかったり、シワができちゃったりするんです」
竿を乾かすスペースには温度計がセッティングされていて、小春さんはこれでこまめに室温をチェックするのである。ペンキのように確実に乾くものではないだけに、実に手間がかかる作業だ。
では、実際に磨きの工程を見せていただこう。研磨剤として使うのは鹿のツノを粉末にしたもの。今はコンパウンドでやる職人も多いそうだが、小春さんは昔の作り方にこだわっている。粉末に油を垂らし、指でこすってクリーム状にすると、それを竿にこすりつけ、磨きをかけていく。
では、江戸和竿に対する注目度に変化はあったのだろうか。試しにYouTubeで「江戸和竿」と検索をかけてみると、思いのほか多くの動画がアップされているではないか(なかには小春さんのインタヴュー動画もある)。だが、その多くは「今、江戸和竿が人気!」というような浮ついたものではない。時代の流れとは無関係にその世界を楽しもうという、どこかストイックな雰囲気をまとっている。
東京都産業労働局のウェブサイトでは江戸和竿の伝統的な技術・技法についてこのように解説されている。
1. 切り組みは、作ろうとする竿の種類に応じて、全長・調子などを考え、竹を選別して切る。
2. 火入れ(矯め)は、竹に火をとおしながら、油抜きをし、矯め木にて真直ぐにする。
3. 継ぎは、継ぎ口を寸分のヌキのないように仕上げる。継ぎ方は、並継ぎと印篭継ぎとする。
4. 塗りは、精製漆の摺り漆仕上げとする。
かなり簡略化した解説ではあるものの、この一文だけで江戸和竿が大量生産のレジャー用品ではなく、職人の手による伝統工芸品として生産されてきたことが伝わってくる。江戸和竿を制作するうえでのポイントを小春さんに解説していただこう。 「まず、いい竹を手に入れること。西洋の竿は竹を削って好きな形にしちゃうんですけど、和竿は削らないんです。なので、最初に選ぶ竹が重要なんですよね。そのあとにくるのが、竹をまっすぐにする火入れ。ここが難しいんですよ」

「漆を塗るのは大変なんですよ。乾かす際には(工房の)湿度や温度を一定にしないといけないし、それがうまくいかないと次の日も乾いていなかったり、シワができちゃったりするんです」
竿を乾かすスペースには温度計がセッティングされていて、小春さんはこれでこまめに室温をチェックするのである。ペンキのように確実に乾くものではないだけに、実に手間がかかる作業だ。
では、実際に磨きの工程を見せていただこう。研磨剤として使うのは鹿のツノを粉末にしたもの。今はコンパウンドでやる職人も多いそうだが、小春さんは昔の作り方にこだわっている。粉末に油を垂らし、指でこすってクリーム状にすると、それを竿にこすりつけ、磨きをかけていく。

「竿師って漆も指でやる人が多いんですよ。最初かぶれるんですけど、だんだん慣れてきました」
小春さんは大きな身体を丸めながら、爪楊枝のように細い和竿を慎重に磨いていく。工房の窓は開け放たれていて、簾の隙間から暖かな秋の陽光が差し込んでいる。そこには静かで穏やかな空気が流れている。観光客で賑わう表通りとはまるで別世界だ。
小春さんが「小春」という屋号で自身の竿を作り始めたのが8年前のことだった。当時のことについて、小春さんはこのように回想する。
「いっぱしの竿師をきどっていたけど、今思うと全然ダメだったと思いますね。それほど受注があるわけでもないし、とにかく竹を集めるのに必死だったんです。オーダーを受けてもそれに適した素材がないと、それはできませんと断るしかないんですよ。竹のことでずっと悩んでましたね」
竹を集めるのに必死だった――いまいちピンとこないが、どういうことなのだろうか。
「昔は竹屋さんがいて、そこで扱っている竹を仕入れればよかったんですよ。でも、今は竹屋自体がないので、冬になると山に繰り出して自分で取ってくるしかない。いくら名人でも、いい竹が手に入らないといい竿は作れないんです。まっすぐで硬い竹ってほとんどなくて、そこが一番大変なんですよ。毎日夢に見るぐらい」
小春さんはそう言って、押し入れにストックしてある竹を何本か手に取った。確かにどれも細くて真っ直ぐである。東京でも郊外にいけばいくらでも竹林はあるし、そのへんから切り出してくればいくらでも材料はあるんじゃないかと考えてしまうが、竿となる竹はやはり特別なのだ。
小春さんは大きな身体を丸めながら、爪楊枝のように細い和竿を慎重に磨いていく。工房の窓は開け放たれていて、簾の隙間から暖かな秋の陽光が差し込んでいる。そこには静かで穏やかな空気が流れている。観光客で賑わう表通りとはまるで別世界だ。
小春さんが「小春」という屋号で自身の竿を作り始めたのが8年前のことだった。当時のことについて、小春さんはこのように回想する。
「いっぱしの竿師をきどっていたけど、今思うと全然ダメだったと思いますね。それほど受注があるわけでもないし、とにかく竹を集めるのに必死だったんです。オーダーを受けてもそれに適した素材がないと、それはできませんと断るしかないんですよ。竹のことでずっと悩んでましたね」
竹を集めるのに必死だった――いまいちピンとこないが、どういうことなのだろうか。
「昔は竹屋さんがいて、そこで扱っている竹を仕入れればよかったんですよ。でも、今は竹屋自体がないので、冬になると山に繰り出して自分で取ってくるしかない。いくら名人でも、いい竹が手に入らないといい竿は作れないんです。まっすぐで硬い竹ってほとんどなくて、そこが一番大変なんですよ。毎日夢に見るぐらい」
小春さんはそう言って、押し入れにストックしてある竹を何本か手に取った。確かにどれも細くて真っ直ぐである。東京でも郊外にいけばいくらでも竹林はあるし、そのへんから切り出してくればいくらでも材料はあるんじゃないかと考えてしまうが、竿となる竹はやはり特別なのだ。

小春さんの竹ハンティングは九州がメインだ。季節は11月から1月にかけて。真冬の真っ只中、特別な竹を追い求めて山中を這いずり回る。どこに生えているのか事前にわかっているわけではないし、当然ネットで検索をかければすぐに辿り着けるというわけでもない。目を凝らし、手と足を使って和竿となる竹を追い求めるのである。そこまでしてもわずかな竹しか手に入らないのだというのだから、大変な苦労だ。伝統工芸品の現場では合理性や効率を度外視したものづくりが続けられてきたが、江戸和竿もその一例といえるだろう。しかも苦労して作った和竿で2センチ足らずのタナゴを狙うわけで、なんとも酔狂な遊びである。
「竹は100年ぐらい保つらしいんですね。だから、竿師のなかでもおじいちゃんが竹屋から買っていた竹をストックしているところもあるんですよ。昔は農家が竿師向けに竹を栽培していたらしいんです。いい竹を育てる技術があったそうなんですけど、今はもうわからない。僕も知りたいんですけど(笑)」 そう話しながらも、竿に磨きをかける小春さんの手は止まらない。その手つきは山中を這いつくばってようやく手にすることができた1本の竹を愛でているようにも感じられた。まるで1枚のレア盤を丁寧にクリーニングするレコードコレクターのようだ。そういえば、かつて友人のコレクターが赤ん坊を風呂に入れるかのように慎重な手つきでレコードをクリーニングしている光景を見て、レコードコレクターというのは恐ろしい人種だ、と思ったことがある。目の前で竿を磨く小春さんもまた、まるで自分の子供を慈しむかのように、今まさに和竿へと成長を遂げつつある1本の竹を磨いている。やはり現代における伝統工芸品の職人とは、小春さんのように少々クレイジーな情熱と好奇心の持ち主がめざすものなのかもしれない。
そう話しながらも、竿に磨きをかける小春さんの手は止まらない。その手つきは山中を這いつくばってようやく手にすることができた1本の竹を愛でているようにも感じられた。まるで1枚のレア盤を丁寧にクリーニングするレコードコレクターのようだ。そういえば、かつて友人のコレクターが赤ん坊を風呂に入れるかのように慎重な手つきでレコードをクリーニングしている光景を見て、レコードコレクターというのは恐ろしい人種だ、と思ったことがある。目の前で竿を磨く小春さんもまた、まるで自分の子供を慈しむかのように、今まさに和竿へと成長を遂げつつある1本の竹を磨いている。やはり現代における伝統工芸品の職人とは、小春さんのように少々クレイジーな情熱と好奇心の持ち主がめざすものなのかもしれない。
職人として歩み始めた当初、苦悩する小春さんを強烈に後押しする人物がいたらしい。その人物について、小春さんはどこか苦笑い混じりで話し始めた。
「江戸和竿の世界には3、40代の若手職人って僕を含めて数人しかいないんですけど、若手ということで期待をかけてくれたんでしょうね、『お前はセンスもないし、どうしようもないから俺が教えてやる』っていう人がいたんです」
ただし、その人物とは職人ではない。和竿の愛好家、それも並外れた情熱と知識を持った人物で、「旦那的でもあるし、心意気のある人でしたね」と話す。
「厳しいことを言うんですけど、一方では僕がどうやって生き残っていけるのか、ヒントをくれたんですよ。最初は昔の竿師の真似をしていたんですけど、それじゃやっぱりダメで。『現代的な配色を研究しろ』とか徹底的に考えさせられました。そこで作風が変わりましたね」
小春さんの技術は師匠たちから受け継いだものだが、配色や装飾には現代的感覚と小春さんのオリジナリティーが反映されている。独立当初は若い職人を応援するため小春さんの和竿を購入していた愛好家たちも、やがて彼の竿が持つオリジナリティーを認めたうえで購入してくれるようになったという。
「竹は100年ぐらい保つらしいんですね。だから、竿師のなかでもおじいちゃんが竹屋から買っていた竹をストックしているところもあるんですよ。昔は農家が竿師向けに竹を栽培していたらしいんです。いい竹を育てる技術があったそうなんですけど、今はもうわからない。僕も知りたいんですけど(笑)」

職人として歩み始めた当初、苦悩する小春さんを強烈に後押しする人物がいたらしい。その人物について、小春さんはどこか苦笑い混じりで話し始めた。
「江戸和竿の世界には3、40代の若手職人って僕を含めて数人しかいないんですけど、若手ということで期待をかけてくれたんでしょうね、『お前はセンスもないし、どうしようもないから俺が教えてやる』っていう人がいたんです」
ただし、その人物とは職人ではない。和竿の愛好家、それも並外れた情熱と知識を持った人物で、「旦那的でもあるし、心意気のある人でしたね」と話す。
「厳しいことを言うんですけど、一方では僕がどうやって生き残っていけるのか、ヒントをくれたんですよ。最初は昔の竿師の真似をしていたんですけど、それじゃやっぱりダメで。『現代的な配色を研究しろ』とか徹底的に考えさせられました。そこで作風が変わりましたね」
小春さんの技術は師匠たちから受け継いだものだが、配色や装飾には現代的感覚と小春さんのオリジナリティーが反映されている。独立当初は若い職人を応援するため小春さんの和竿を購入していた愛好家たちも、やがて彼の竿が持つオリジナリティーを認めたうえで購入してくれるようになったという。

現在小春さんの和竿を購入できるのは東京都文京区千石の「つり具すがも」のみ。あるいは小春さん自身にオーダーするしかない。サイズによって異なるが、完成まで1本に2か月ほどはかかるそうで、辛抱強くそれを待てる者だけが彼の和竿を手にすることができるのだ。
小春さんが工房を構える喜多町弁天長屋がオープンしたのは2021年のことだ。それまでは自宅の一室を工房としていた小春さんにとって、他の入居者と同居しながらものづくりに励む現在の環境は大きな刺激となった。
「ここには革製品の修理をやってる人もいるし、織物をやってる人も彫金の方もいる。そういう環境が僕にとっても重要なんですよ。夜帰るときに電気がついていたりすると、僕も頑張んなきゃなと思いますし」
職人とは基本的に孤独なものだ。僕もフリーランスの文筆家として日々仕事をしているので、ひとり原稿に向かっていると孤独を感じることもある。だが、弁天長屋には心の隙間を埋めてくれる人々がいる。そうした環境のなか仕事をする小春さんが僕には少し羨ましく思えた。
その一方で、僕にはひとつわからないことがあった。「川越も昔は本当につまらない町でしたよね?」と話す小春さんは、なぜ川越にこだわりながら活動を続けているのだろうか。江戸和竿の職人として独立するのであれば、顧客の多い都心を拠点とするほうが得策だろう。そもそも江戸和竿の本場は下町なのだ。
「確かに江戸和竿は下町の文化だし、お客さんや目の肥えた方も多いので、自分もあっちでやりたいという気持ちもありました。でも、川越を離れられない。それがなぜなのかわからないんですけど…町が少しずつ良くなっているのを見てきているので、もう少し見ていたい、という気持ちもあ るのかもしれない。そこに自分が加われて嬉しいという感覚もあるんですよ」
小春さんはそう話し、「川越の人って川越が好きな人が多いんですよ。自分も好きですし」と続けた。
小春さんはなぜ「川越を離れられない」のだろうか。その理由を知りたくて、小春さんの小物釣りに同行させてもらうことになった。
小春さんが工房を構える喜多町弁天長屋がオープンしたのは2021年のことだ。それまでは自宅の一室を工房としていた小春さんにとって、他の入居者と同居しながらものづくりに励む現在の環境は大きな刺激となった。
「ここには革製品の修理をやってる人もいるし、織物をやってる人も彫金の方もいる。そういう環境が僕にとっても重要なんですよ。夜帰るときに電気がついていたりすると、僕も頑張んなきゃなと思いますし」
職人とは基本的に孤独なものだ。僕もフリーランスの文筆家として日々仕事をしているので、ひとり原稿に向かっていると孤独を感じることもある。だが、弁天長屋には心の隙間を埋めてくれる人々がいる。そうした環境のなか仕事をする小春さんが僕には少し羨ましく思えた。
その一方で、僕にはひとつわからないことがあった。「川越も昔は本当につまらない町でしたよね?」と話す小春さんは、なぜ川越にこだわりながら活動を続けているのだろうか。江戸和竿の職人として独立するのであれば、顧客の多い都心を拠点とするほうが得策だろう。そもそも江戸和竿の本場は下町なのだ。
「確かに江戸和竿は下町の文化だし、お客さんや目の肥えた方も多いので、自分もあっちでやりたいという気持ちもありました。でも、川越を離れられない。それがなぜなのかわからないんですけど…町が少しずつ良くなっているのを見てきているので、もう少し見ていたい、という気持ちもあ るのかもしれない。そこに自分が加われて嬉しいという感覚もあるんですよ」
小春さんはそう話し、「川越の人って川越が好きな人が多いんですよ。自分も好きですし」と続けた。
小春さんはなぜ「川越を離れられない」のだろうか。その理由を知りたくて、小春さんの小物釣りに同行させてもらうことになった。

2022年11月5日、晴天。川越の旧市街から車で15分ほど走った田園地帯で小春さんと待ち合わせた。約束の場所に向かうと、用水路にかかる橋に腰を下ろし、竿を垂らす小春さんの姿が見えた。狙う獲物はタナゴとコブナである。
「子供のころは伊佐沼でもタナゴがずいぶん釣れたんですけど、護岸工事をやってから釣れなくなっちゃったんですよ。このあたりは今も残っていて、魚の量が多い。昔の伊佐沼みたいな感じなんです」
タナゴはドブ貝に卵を産む。だが、護岸工事によってこのドブ貝が減ってしまい、その結果タナゴが減ってしまうのだという。小春さんはそのことを嘆きながら、何の前触れもなくひょいと竿を上げた。糸の先に小さな魚がついていて、ぴちぴちと元気よく動いている。
「これがコブナですね。秋は柿の種サイズのものが釣れるんですよ」
そう話すと、小春さんは流れるような動作で魚を木箱に入れた。木箱はりくと呼ぶそうで、今もこうした木箱を作る職人がいるのだという。小春さんの釣り道具は多くが手作りによるものだ。釣り道具を入れる箱は合切箱。一切合切を入れられるからそう呼ばれ、ふたを閉じると椅子にもなる。もちろん手にする竿は小春さんが作った和竿。餌はグルテンで、小魚の口に合うよう小さな針に米粒大の餌をつける。今日の仕掛けはタナゴ用のものだ。
「子供のころは伊佐沼でもタナゴがずいぶん釣れたんですけど、護岸工事をやってから釣れなくなっちゃったんですよ。このあたりは今も残っていて、魚の量が多い。昔の伊佐沼みたいな感じなんです」
タナゴはドブ貝に卵を産む。だが、護岸工事によってこのドブ貝が減ってしまい、その結果タナゴが減ってしまうのだという。小春さんはそのことを嘆きながら、何の前触れもなくひょいと竿を上げた。糸の先に小さな魚がついていて、ぴちぴちと元気よく動いている。
「これがコブナですね。秋は柿の種サイズのものが釣れるんですよ」
そう話すと、小春さんは流れるような動作で魚を木箱に入れた。木箱はりくと呼ぶそうで、今もこうした木箱を作る職人がいるのだという。小春さんの釣り道具は多くが手作りによるものだ。釣り道具を入れる箱は合切箱。一切合切を入れられるからそう呼ばれ、ふたを閉じると椅子にもなる。もちろん手にする竿は小春さんが作った和竿。餌はグルテンで、小魚の口に合うよう小さな針に米粒大の餌をつける。今日の仕掛けはタナゴ用のものだ。

「江戸時代から小物釣りでは2センチ以下の小さなものを釣るのが目的なんです。大きいものは誰でも釣れますからね。今では200匹とか釣ることを目標にする人もいるんですけど、僕は適当。2、3時間やったら終わりにするようにしてます」
小春さんによると、小物釣りとは日本ならではの釣りらしい。そういえば、小春さんが大好きだという漫画『釣りキチ三平』の「小さなビッグゲーム」という回は、大物を釣るため日本にやってきたアメリカ人のフィッシャーマンに対し、三平が小物釣りの楽しさを教えるという内容だった。小春さんと三平の姿が重なり合うような気がした。
そうこうしているうちに、小春さんがタナゴを釣り上げた。
小春さんによると、小物釣りとは日本ならではの釣りらしい。そういえば、小春さんが大好きだという漫画『釣りキチ三平』の「小さなビッグゲーム」という回は、大物を釣るため日本にやってきたアメリカ人のフィッシャーマンに対し、三平が小物釣りの楽しさを教えるという内容だった。小春さんと三平の姿が重なり合うような気がした。
そうこうしているうちに、小春さんがタナゴを釣り上げた。

「やった! 釣れるとは思わなかった。ここにもタナゴがいるんですね!」と嬉しそうだ。近年タナゴは数が減少していて、川越近辺でも釣るのが難しくなっているのだという。
水面を見ると、小さなメダカがウヨウヨしている。日本の在来種である真メダカだ。その横を小さなウキがすーっと移動するので、それに合わせる。ズンというわかりやすいアタリではない。見逃してしまうような小さな動きであるが、小春さんはその動きに合わせてどんどんタナゴやコブナを釣りあげていく。どうやらその前日雨が降ったことがよかったらしい。暖かい雨が降ると、魚の活性が上がるのだという。
天気もよく、まさに釣り日和。小春さんも水面に差し込む陽光に目を細めながら、「このあたり、大好きなんですよ」とつぶやく。
小春さんの指導のもと、僕も竿を握らせてもらう。不器用にグルテンを丸め、針につけて水路に落とすと、さほど時間がたたずにコブナが釣れた。柿の種ほどのサイズだが、竿を通して魚の動きがブルブルと伝わってくる。手の平に乗せると、透き通るように美しい。調子づいてふたたび糸を垂らすと、今度はメダカが釣れた。コブナよりもさらに小さいため、ウキの動きは微々たるものだが、その動きに合わせられたという喜びが湧き上がってくる。なるほど、これは楽しい。
コブナやメダカもいいが、今日狙っているのはタナゴである。仕掛けを落とすポイントを探りながら時間をかけてタナゴを狙っていくと、ついに釣れた!
「やった、タナゴだ!」
思わず大きな声をあげてしまう。目の前で観察すると、ほれぼれするような形と色彩である。春になるとさらに美しいのだという。新緑の季節の小物釣りはさらに楽しいだろう。
写真を撮影していた妻も小春さんの竿を借り、釣りにチャレンジ。あっという間にいいサイズのコブナを釣り上げた。メダカなどを見ていたため、4、5センチほどのコブナでも巨大に見える。その後、妻も時間をかけてタナゴを釣り上げた。 小春さんの指導のもと釣りをするなかで、ひとつ発見があった。小物釣りとはひたすら水面を凝視するような渋い釣りかとばかり思っていたのだが、意外とスピーディーだったということだ。餌はすぐなくなるうえに、どんどん釣れるので慌ただしい。坐禅のような釣りをイメージしていたけれど、案外現代の生活ペースに合っているような気もする。もちろん疲れたら休めばいいし、短時間で終わらせてもいい。この日の小春さんもまた2時間ほど糸を垂らすと、「今日はこんなところですかね」とさっさと後片付けを始めた。これならば気軽だし、いい気分転換になるだろう。
小春さんの指導のもと釣りをするなかで、ひとつ発見があった。小物釣りとはひたすら水面を凝視するような渋い釣りかとばかり思っていたのだが、意外とスピーディーだったということだ。餌はすぐなくなるうえに、どんどん釣れるので慌ただしい。坐禅のような釣りをイメージしていたけれど、案外現代の生活ペースに合っているような気もする。もちろん疲れたら休めばいいし、短時間で終わらせてもいい。この日の小春さんもまた2時間ほど糸を垂らすと、「今日はこんなところですかね」とさっさと後片付けを始めた。これならば気軽だし、いい気分転換になるだろう。
水面を見ると、小さなメダカがウヨウヨしている。日本の在来種である真メダカだ。その横を小さなウキがすーっと移動するので、それに合わせる。ズンというわかりやすいアタリではない。見逃してしまうような小さな動きであるが、小春さんはその動きに合わせてどんどんタナゴやコブナを釣りあげていく。どうやらその前日雨が降ったことがよかったらしい。暖かい雨が降ると、魚の活性が上がるのだという。
天気もよく、まさに釣り日和。小春さんも水面に差し込む陽光に目を細めながら、「このあたり、大好きなんですよ」とつぶやく。
小春さんの指導のもと、僕も竿を握らせてもらう。不器用にグルテンを丸め、針につけて水路に落とすと、さほど時間がたたずにコブナが釣れた。柿の種ほどのサイズだが、竿を通して魚の動きがブルブルと伝わってくる。手の平に乗せると、透き通るように美しい。調子づいてふたたび糸を垂らすと、今度はメダカが釣れた。コブナよりもさらに小さいため、ウキの動きは微々たるものだが、その動きに合わせられたという喜びが湧き上がってくる。なるほど、これは楽しい。
コブナやメダカもいいが、今日狙っているのはタナゴである。仕掛けを落とすポイントを探りながら時間をかけてタナゴを狙っていくと、ついに釣れた!
「やった、タナゴだ!」
思わず大きな声をあげてしまう。目の前で観察すると、ほれぼれするような形と色彩である。春になるとさらに美しいのだという。新緑の季節の小物釣りはさらに楽しいだろう。
写真を撮影していた妻も小春さんの竿を借り、釣りにチャレンジ。あっという間にいいサイズのコブナを釣り上げた。メダカなどを見ていたため、4、5センチほどのコブナでも巨大に見える。その後、妻も時間をかけてタナゴを釣り上げた。


僕自身、釣りをしているうちに心身のこわばりが取れたのか、温泉に入ったあとのような気分で帰路についた。体調を崩したかつての小春さんはひたすら小物釣りに出かけていたというが、その気持ちが理解できた。小春さんはこんなふうに空いた時間に近隣の用水路へと出かけ、ふたたび工房に戻っては和竿作りに励んでいるのだ。なんと素晴らしいライフスタイルだろうか。

小春友樹/江戸和竿師
1973年、東京生まれ。幼年期より埼玉県川越市在住。服飾メーカー営業職を経て、竿職人の道を目指す。川越市に工房を構える東作系江戸和竿師「寿代作」工房の門を叩き、1年間師事。その後、同市内の「俊秀作」の元へ2年間師事した後、独立。2020年より江戸和竿組合に加入。
-

FORESTER
Shigeaki Adachi
-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER
Kei Amano
-

BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER
Taiki Minakuchi
-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭 火付ぬ組
-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN
Yukihito Kanai
-

SAUNA BUILDER
nodaklaxonbebe