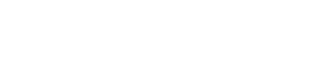Chapter 8 Vol.Three
EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
Tomoki Koharu
小春友樹
活気のなかった埼玉県川越市の旧市街を、市民団体から始まったひとつの会が変えた。それが〈NPO法人・川越蔵の会〉だ。若手の商店主や建築の専門家などから構成されるこの会は、1960年代以降、衰退の一途を辿っていた川越の旧市街地を少しずつ変えてきた。江戸和竿の職人である小春友樹が入居する喜多町弁天長屋もまた、〈川越蔵の会〉主導のリノヴェーションによって生まれ変わった物件のひとつだ。まちづくりとものづくりが交差する場所、川越旧市街をふたたび訪ねた。
この日も川越の旧市街は多くの観光客で賑わっていた。蔵造りの雰囲気を活かしたレトロな街並みを、幅広い年齢層の観光客がそぞろ歩いている。ここは訪れるものを明治の街にタイムスリップしたような気分にしてくれる、ある種のアミューズメントパークのようなものなのかもしれない。
ただし、こうしたまちづくりは決して行政主導で強引に進められたわけでもなければ、大手ディヴェロッパーが町ごとガラッと変えてしまったわけでもない。1983年に市民団体として発足した〈NPO法人・川越蔵の会〉が中心となって、あくまでも市民主導で進められた。〈蔵の会〉で事務局長を務める秋山修志さんは、発足の経緯をこのように説明する。
 「当時の一番街はかなり寂れていて、なんとかしないといけないという危機感があったそうなんです。そのため商店街の若手や市役所の職員、研究者が集まって話し合いを重ねていたんですよ。その勉強会が〈蔵の会〉の前身になったと聞いています」
「当時の一番街はかなり寂れていて、なんとかしないといけないという危機感があったそうなんです。そのため商店街の若手や市役所の職員、研究者が集まって話し合いを重ねていたんですよ。その勉強会が〈蔵の会〉の前身になったと聞いています」
僕は幼少時代を川越で過ごしたので、当時の川越旧市街のことはなんとなく記憶している。小学生だった僕にとって活気のない旧市街は薄暗いイメージがあり、みずから好んで出かけるような場所ではなかった。子供でもそう感じるぐらいだから、地元住民のあいだで「なんとかしないといけない」という危機感があったのは当然のことだろう。そうしたなか、1987年には住民と専門家、行政が対等の立場で町づくりの議論をする「町並み委員会」が発足。少しずつまちづくりに向けた体制が整っていく。
ただし、こうしたまちづくりは決して行政主導で強引に進められたわけでもなければ、大手ディヴェロッパーが町ごとガラッと変えてしまったわけでもない。1983年に市民団体として発足した〈NPO法人・川越蔵の会〉が中心となって、あくまでも市民主導で進められた。〈蔵の会〉で事務局長を務める秋山修志さんは、発足の経緯をこのように説明する。

僕は幼少時代を川越で過ごしたので、当時の川越旧市街のことはなんとなく記憶している。小学生だった僕にとって活気のない旧市街は薄暗いイメージがあり、みずから好んで出かけるような場所ではなかった。子供でもそう感じるぐらいだから、地元住民のあいだで「なんとかしないといけない」という危機感があったのは当然のことだろう。そうしたなか、1987年には住民と専門家、行政が対等の立場で町づくりの議論をする「町並み委員会」が発足。少しずつまちづくりに向けた体制が整っていく。

特定の地域を「伝統的建造物群保存地区」として指定し、街並みそのものを保存しようという動きが全国各地で本格化したのは70年代以降のことだ。1976年には秋田県仙北市角館の武家町、長野県南木曽町妻籠宿、岐阜県白川村の山村集落など保存地区として選定されており、川越もまた、早い段階で選定が検討されていたという。だが、実際に指定されたのは1999年。20年以上のタイムラグがあった理由について秋山さんはこう話す。
「国としては川越の一番街を保存地区第1号にするつもりだったようなんですが、住民のあいだでは保存地区になると自分の建物に釘1本打てなくなるんじゃないかという危惧があったんです。当時は古い建物を壊してマンションを建てたいという方が大半でしたし」
古い街並みを壊してマンションにしたい住民と、古い街並みを保存しながら新しい町を作ろうとする住民。その両者が共存していたのが70年代から90年代にかけての川越だったわけだ。言うまでもなく、現在の〈蔵の会〉に繋がるのは後者の人々である。
秋山さんが都市計画コンサルタントとして川越に関わり始めたのは1997年のこと。その後、2003年からは蔵の会の活動に加わるようになった。当時は「古い建物を活用したいのだが、どうしたらいいのだろう?」という依頼が多かったというが、ここ数年、世代が変わったことで物件をリノベーションして活用したいという住民が増加。それを受けて〈蔵の会〉は景観を損なわず、なおかつ川越らしさを伝える改修のアイデアをまとめた冊子を作成する。
「国としては川越の一番街を保存地区第1号にするつもりだったようなんですが、住民のあいだでは保存地区になると自分の建物に釘1本打てなくなるんじゃないかという危惧があったんです。当時は古い建物を壊してマンションを建てたいという方が大半でしたし」
古い街並みを壊してマンションにしたい住民と、古い街並みを保存しながら新しい町を作ろうとする住民。その両者が共存していたのが70年代から90年代にかけての川越だったわけだ。言うまでもなく、現在の〈蔵の会〉に繋がるのは後者の人々である。
秋山さんが都市計画コンサルタントとして川越に関わり始めたのは1997年のこと。その後、2003年からは蔵の会の活動に加わるようになった。当時は「古い建物を活用したいのだが、どうしたらいいのだろう?」という依頼が多かったというが、ここ数年、世代が変わったことで物件をリノベーションして活用したいという住民が増加。それを受けて〈蔵の会〉は景観を損なわず、なおかつ川越らしさを伝える改修のアイデアをまとめた冊子を作成する。

僕が幼少時代、川越の旧市街では蔵造りのまちなみの狭間に没個性的なビルが次々に作られ、町の風景が急激に変容しつつあった。どこにでもあるようなマンションやビルばかりが立ち並ぶ街並みは住民にとっては使いやすいかもしれないけれど、決して魅力的とはいえない。「近代的」とされたビルも20年30年が経過するとかえって古臭いものになってしまう。一時の収益や賑わいを求めたものではない、魅力あるまちづくりとはどのようなものだろうか。〈蔵の会〉が作成した冊子では蔵造りの良さを残しながら、現代でも使いやすい建築様式が提案されている。
「川越の旧市街は駅から1、2キロ離れてるんですよ。駅前だったらビルやマンションをどんどん建てて効率のいいまちづくりが必要かもしれないけれど、同じものをここに作っても難しい。この情報集で自分たちの建物の価値を知ってもらえたらというのが一番ですね。あと、設計の方にも『川越らしさ』を意識していただくきっかけになればと思いまして」
「川越らしさ」とは何なのだろうか。それは住民のなかで無意識のうちに共有されている感覚でもあるだろうが、〈蔵の会〉は建築様式という極めて具体的な観点から「川越らしさ」を定義していったのだ。そして、住民たちは「川越らしさ」を定義するなかで自分たちの住む町と向かい合い、「らしさ」を自問自答していくことになる。
〈蔵の会〉が手がけた物件のなかでも喜多町弁天長屋は代表的なもののひとつといえる。〈蔵の会〉は基本的にアドバイザーとして物件に関わることが多いが、弁天長屋の場合、みずからリノベーションまで手掛けたという。 「あの長屋は10年ぐらい空き家になっていて、大家さんから『なんとかしてもらえないか』と相談を受けていたんですよ。〈蔵の会〉として入居希望の方とのマッチングをやってたんですけど、傷みがひどかったのでなかなか成約しなく。だったら思い切って〈蔵の会〉でこの物件を借り、改修してからひと部屋ずつ借りてもらおうという話になったんです」
「あの長屋は10年ぐらい空き家になっていて、大家さんから『なんとかしてもらえないか』と相談を受けていたんですよ。〈蔵の会〉として入居希望の方とのマッチングをやってたんですけど、傷みがひどかったのでなかなか成約しなく。だったら思い切って〈蔵の会〉でこの物件を借り、改修してからひと部屋ずつ借りてもらおうという話になったんです」
ここまでに何度も書いているように、この長屋はもともと芸者の置屋だった。「置屋」とは芸者たちを抱える事務所のようなもので、芸者たちは客の求めに応じて料亭や茶屋に派遣される。喜多町弁天長屋の周辺にはそうした置屋や料亭が集まっていたという。ただし、花街だったのは昭和30年代まで。しばらくすると花街はスナック街へと移り変わり、一部も芸者は小料理屋の店員へと転職した。昭和の終わりごろにはスナックや飲食店も閉店。以降、一部の店舗は廃墟のような状態で放置されていた。
「川越の旧市街は駅から1、2キロ離れてるんですよ。駅前だったらビルやマンションをどんどん建てて効率のいいまちづくりが必要かもしれないけれど、同じものをここに作っても難しい。この情報集で自分たちの建物の価値を知ってもらえたらというのが一番ですね。あと、設計の方にも『川越らしさ』を意識していただくきっかけになればと思いまして」
「川越らしさ」とは何なのだろうか。それは住民のなかで無意識のうちに共有されている感覚でもあるだろうが、〈蔵の会〉は建築様式という極めて具体的な観点から「川越らしさ」を定義していったのだ。そして、住民たちは「川越らしさ」を定義するなかで自分たちの住む町と向かい合い、「らしさ」を自問自答していくことになる。
〈蔵の会〉が手がけた物件のなかでも喜多町弁天長屋は代表的なもののひとつといえる。〈蔵の会〉は基本的にアドバイザーとして物件に関わることが多いが、弁天長屋の場合、みずからリノベーションまで手掛けたという。

ここまでに何度も書いているように、この長屋はもともと芸者の置屋だった。「置屋」とは芸者たちを抱える事務所のようなもので、芸者たちは客の求めに応じて料亭や茶屋に派遣される。喜多町弁天長屋の周辺にはそうした置屋や料亭が集まっていたという。ただし、花街だったのは昭和30年代まで。しばらくすると花街はスナック街へと移り変わり、一部も芸者は小料理屋の店員へと転職した。昭和の終わりごろにはスナックや飲食店も閉店。以降、一部の店舗は廃墟のような状態で放置されていた。

弁天長屋のリノベーションが始まったのは2020年のことである。水道、ガス、電気などは業者が入ったが、そのほかの作業は〈蔵の会〉のスタッフが中心となって進められた。作業するのは週末。そのため、完成まで1年ほどの期間がかかったという。
「柱や梁といった建物の駆体自体はいじってないんです。塀をとって土間を作ったり、漆喰を塗ったり、太鼓貼りという方法で和紙を壁に貼ったり。今までの雰囲気を活かしつつリノベーションした感じですね」
では、秋山さんたちはリノベーションした長屋をなぜものづくりの拠点にしようと考えたのだろうか。一番街の他の蔵造りの建物のように飲食店を複数入れれば多くの観光客がやってきそうなものだが、そこには「ものづくりの街としての川越を発信する」という明確な目的があった。
「弁天長屋はちょっと奥まった場所にあって、観光客がどっと入ってくるような地域でもないんですよね。そのことを活かして川越の職人を育てつつ、訪れる方にも川越のものづくりに興味を持ってもらえるエリアになったらというコンセプトからスタートしているんです」
弁天長屋は川越の内部と外部を繋ぐ場でもある。外部からやってきた観光客にとっては「ものづくりの街としての川越」と出会う場であり、入居者という内部の人々にとっては、ものづくりを通じて街と繋がる場でもある。つまり、どちらの場合であっても、ものづくりが接着剤となっているわけだ。
ちなみに、弁天長屋のコンセプトはかつて〈蔵の会〉の中心を担っていた福田喜文さんが発案したものだった。福田さんは明治後期に芝居小屋として建てられた〈鶴川座〉の復興にもかかわるなど、街の復興に情熱を注いだ方だったという。だが、福田さんは若くしてこの世を去ってしまう。弁天長屋を工房とする小春さんは福田さんについてこう話す。
「一番最初にお世話になったのが福田さんだったんですよ。僕はその方が大好きで、福田さんにここに入れてもらったんです。でも、49歳っていう若さで亡くなってしまって…」
秋山さんにとっても福田さんの死は大きなものだった。福田さんが夢見た川越の再生。その目的を継ぐことも蔵の会のミッションのひとつなのだ。
ここで弁天長屋の入居者をもう一組ご紹介しよう。錬鉄を使った家具であるロートアイアンの職人、中井貴史さんとグラフィックデザイナーの小林チエさん夫妻が経営する〈bero弁天長屋〉だ。
「柱や梁といった建物の駆体自体はいじってないんです。塀をとって土間を作ったり、漆喰を塗ったり、太鼓貼りという方法で和紙を壁に貼ったり。今までの雰囲気を活かしつつリノベーションした感じですね」
では、秋山さんたちはリノベーションした長屋をなぜものづくりの拠点にしようと考えたのだろうか。一番街の他の蔵造りの建物のように飲食店を複数入れれば多くの観光客がやってきそうなものだが、そこには「ものづくりの街としての川越を発信する」という明確な目的があった。
「弁天長屋はちょっと奥まった場所にあって、観光客がどっと入ってくるような地域でもないんですよね。そのことを活かして川越の職人を育てつつ、訪れる方にも川越のものづくりに興味を持ってもらえるエリアになったらというコンセプトからスタートしているんです」
弁天長屋は川越の内部と外部を繋ぐ場でもある。外部からやってきた観光客にとっては「ものづくりの街としての川越」と出会う場であり、入居者という内部の人々にとっては、ものづくりを通じて街と繋がる場でもある。つまり、どちらの場合であっても、ものづくりが接着剤となっているわけだ。
ちなみに、弁天長屋のコンセプトはかつて〈蔵の会〉の中心を担っていた福田喜文さんが発案したものだった。福田さんは明治後期に芝居小屋として建てられた〈鶴川座〉の復興にもかかわるなど、街の復興に情熱を注いだ方だったという。だが、福田さんは若くしてこの世を去ってしまう。弁天長屋を工房とする小春さんは福田さんについてこう話す。
「一番最初にお世話になったのが福田さんだったんですよ。僕はその方が大好きで、福田さんにここに入れてもらったんです。でも、49歳っていう若さで亡くなってしまって…」
秋山さんにとっても福田さんの死は大きなものだった。福田さんが夢見た川越の再生。その目的を継ぐことも蔵の会のミッションのひとつなのだ。
ここで弁天長屋の入居者をもう一組ご紹介しよう。錬鉄を使った家具であるロートアイアンの職人、中井貴史さんとグラフィックデザイナーの小林チエさん夫妻が経営する〈bero弁天長屋〉だ。

中井さんは埼玉県所沢市の生まれ。2012年に自身が主催する鉄工房〈bero iron works〉を設立し、埼玉県所沢市に工房を構えた。チエさんはこう話す。
「最初のころは工房が所沢で、自宅が野方(東京都中野区)だったので、自宅と工房を一緒にしたくなったんですね。そんなときに高島平(東京都板橋区)の物件を見つけたんです。鉄の工房は大きな音が出るので場所の制限があったんですけど、高島平の物件はもともと鉄のプレスをやってる町工場だったんです。今は1階を工房、2階と3階を住居にしています」
〈bero弁天長屋〉は〈bero iron works〉のショウルームとして2022年4月1日にオープン。チエさんは「いつか自分たちの店が持てたらいいなと思ってましたけど、老後かなとも思っていたんですよ。この場所と出会わなかったら今のタイミングで店も始めてないと思います」と話す。
「中井くんが12年間勤めていた工房の先輩が川越のほうに住んでいたんですよ。その方に弁天長屋のことを教えていただきました。最初は古い酒屋さんの蔵を紹介されたんですけど、改修にだいぶ手間がかかりそうだったんですね。そこの物件を見た帰りに長屋を見せてもらったら一目惚れしてしまいました」
チエさんは一目惚れの理由として、長屋特有の空間を挙げる。
「弁天長屋には仕切りがあるようでないんですよね。人が行き来できるようになっていて、空気も人も流れるようになっている。そこがおもしろいなと思いました。それと、私たちが作っている鉄製の家具のコンセプトに『デザインの力で古いものに新しい価値を与える』というものがあって、長屋はそのコンセプトにもフィットすると思ったんです」
弁天長屋に足を踏み入れると、そこにはまず土間が広がっていて、土間を囲むように複数の部屋が共存している。その間には明確な仕切りがなく、外に向けて開かれている。
「最初のころは工房が所沢で、自宅が野方(東京都中野区)だったので、自宅と工房を一緒にしたくなったんですね。そんなときに高島平(東京都板橋区)の物件を見つけたんです。鉄の工房は大きな音が出るので場所の制限があったんですけど、高島平の物件はもともと鉄のプレスをやってる町工場だったんです。今は1階を工房、2階と3階を住居にしています」
〈bero弁天長屋〉は〈bero iron works〉のショウルームとして2022年4月1日にオープン。チエさんは「いつか自分たちの店が持てたらいいなと思ってましたけど、老後かなとも思っていたんですよ。この場所と出会わなかったら今のタイミングで店も始めてないと思います」と話す。
「中井くんが12年間勤めていた工房の先輩が川越のほうに住んでいたんですよ。その方に弁天長屋のことを教えていただきました。最初は古い酒屋さんの蔵を紹介されたんですけど、改修にだいぶ手間がかかりそうだったんですね。そこの物件を見た帰りに長屋を見せてもらったら一目惚れしてしまいました」
チエさんは一目惚れの理由として、長屋特有の空間を挙げる。
「弁天長屋には仕切りがあるようでないんですよね。人が行き来できるようになっていて、空気も人も流れるようになっている。そこがおもしろいなと思いました。それと、私たちが作っている鉄製の家具のコンセプトに『デザインの力で古いものに新しい価値を与える』というものがあって、長屋はそのコンセプトにもフィットすると思ったんです」
弁天長屋に足を踏み入れると、そこにはまず土間が広がっていて、土間を囲むように複数の部屋が共存している。その間には明確な仕切りがなく、外に向けて開かれている。

「こういう作りなんで、入居者同士のコミュニケーションも頻繁にあるんですよ。暇なときは土間にみんな集まってきて、雑談することもあります。近所のおばあちゃんがそこに加わることもありますね」
そう話しているうちに数人の観光客がやってきて、引き戸の上に飾られた花街時代の写真を見ながら何気ない会話が始まった。こうしたコミュニケーションもまた弁天長屋の日常なのだ。
〈bero弁天長屋〉で扱っている製品を紹介しておこう。
まずは〈bero iron works〉の鍛鉄品。チエさんいわく「鉄を熱して加工した建築装飾品や店舗什器が多いですね。仕事の半分ぐらいはハウスメーカーや建築家・設計士さんから依頼をいただいて生産するものです」とのこと。個人でオーダーを受け、家具やポスト、門扉を制作することもあるのだという。
「〈蔵の会〉関係の方からご自宅の門とポストをご依頼いただいたこともあります。川越の歴史にも詳しい方だったので、家紋のモチーフをつけたり、お正月飾り用の金具をつけたり。今までそういうオーダーを受けたことがなかったので、中井くんも気合いが入ると言っていました」 〈bero iron works〉ではそのほかに北欧で買い付けてきたヴィンテージ食器、川越育ちのガラス作家である戸田晶子さんの作品なども販売している。「北欧には食器をリユースする文化があって、そうした文化の魅力もここから発信していきたいんです」――そう話すチエさんの頭の中では、弁天長屋ならではのものづくりのスタイルがイメージされているようだ。
〈bero iron works〉ではそのほかに北欧で買い付けてきたヴィンテージ食器、川越育ちのガラス作家である戸田晶子さんの作品なども販売している。「北欧には食器をリユースする文化があって、そうした文化の魅力もここから発信していきたいんです」――そう話すチエさんの頭の中では、弁天長屋ならではのものづくりのスタイルがイメージされているようだ。
「ここには小春さんのような伝統工芸の職人もいるし、皮職人の方もいるので、同じものづくりの職人として中井くんはすごく刺激を受けているようですね。あと、ここに関わる人は川越愛に溢れている方が多いんですよ。私たちも地元の素材や伝統を意識して何かできたらなと考えています」
弁天長屋ではberoとトモリ食堂のコラボ立ち飲み屋「ベロベロバー」が定期的に開催されているほか、蔵の会の事務局がある本町の長屋では蔵の会主催の長屋バーも開催され、訪れる人々には川越のクラフトビールである「おとなり」が振る舞われる。〈蔵の会〉の秋山さんはこう話す。
「〈蔵の会〉でも交流のきっかけになるような何かができればと思い、長屋バーが始まったんです。純粋にみんなで飲もうよと。昨年の9月、ひさびさに開催したんですけど、たくさんの方にお越しいただきました」
秋山さんたちもまた長屋を閉じた世界ではなく、外部へ開いていこうとしているのだ。チエさんもこう話す。
「私は外の人間なので最初はアウェイな感じもしたんですけど、みなさん受け入れてくれて、すぐに馴染むことができました。古い町って排他的なイメージがあったんですけど、川越は外からやってきた人たちのことも受け入れてくれるので、ちょっと意外でした。小春さんみたいに変な人もいるし(笑)」
そう話しているうちに数人の観光客がやってきて、引き戸の上に飾られた花街時代の写真を見ながら何気ない会話が始まった。こうしたコミュニケーションもまた弁天長屋の日常なのだ。
〈bero弁天長屋〉で扱っている製品を紹介しておこう。
まずは〈bero iron works〉の鍛鉄品。チエさんいわく「鉄を熱して加工した建築装飾品や店舗什器が多いですね。仕事の半分ぐらいはハウスメーカーや建築家・設計士さんから依頼をいただいて生産するものです」とのこと。個人でオーダーを受け、家具やポスト、門扉を制作することもあるのだという。
「〈蔵の会〉関係の方からご自宅の門とポストをご依頼いただいたこともあります。川越の歴史にも詳しい方だったので、家紋のモチーフをつけたり、お正月飾り用の金具をつけたり。今までそういうオーダーを受けたことがなかったので、中井くんも気合いが入ると言っていました」

「ここには小春さんのような伝統工芸の職人もいるし、皮職人の方もいるので、同じものづくりの職人として中井くんはすごく刺激を受けているようですね。あと、ここに関わる人は川越愛に溢れている方が多いんですよ。私たちも地元の素材や伝統を意識して何かできたらなと考えています」
弁天長屋ではberoとトモリ食堂のコラボ立ち飲み屋「ベロベロバー」が定期的に開催されているほか、蔵の会の事務局がある本町の長屋では蔵の会主催の長屋バーも開催され、訪れる人々には川越のクラフトビールである「おとなり」が振る舞われる。〈蔵の会〉の秋山さんはこう話す。
「〈蔵の会〉でも交流のきっかけになるような何かができればと思い、長屋バーが始まったんです。純粋にみんなで飲もうよと。昨年の9月、ひさびさに開催したんですけど、たくさんの方にお越しいただきました」
秋山さんたちもまた長屋を閉じた世界ではなく、外部へ開いていこうとしているのだ。チエさんもこう話す。
「私は外の人間なので最初はアウェイな感じもしたんですけど、みなさん受け入れてくれて、すぐに馴染むことができました。古い町って排他的なイメージがあったんですけど、川越は外からやってきた人たちのことも受け入れてくれるので、ちょっと意外でした。小春さんみたいに変な人もいるし(笑)」

秋山さんもこう言う。
「外の話にもまず耳を傾けるという気風はあるように思います。多様な価値観を受け入れてきた小江戸ならではの性質があるように思いますね」
ところで、旧市街の上の世代は川越の変化をどのように捉えているのだろうか? 秋山さんはこう話す。
「川越独特の気風でもあると思うんですけど、若者たちに任せるのが早い感じがしますね。地方の商店街って60代が若手で、70、80代が現役っていうところが少なくないんです。でも、一番街商店街の理事長さんはまだ40代ですし、女性陣もいて活気があるんですよ」
川越独特の気風――それはもともと外部の人間として川越のまちづくりに関わるようになった秋山さんだからこそ見えてくる部分でもあるだろう。秋山さんはこう続ける。
「『まちづくりは人づくり』ということがよく言われますけど、熱意のある人たちがいて初めて街がいい方向に進んでいくと思うんですよ。いろんな考えがあると思うんですけど、『川越のこのエリアが好き』という思いはみなさん同じなんじゃないかと」
最後に都市計画コンサルタントの視点から見た川越の魅力を秋山さんに語っていただいた。
「外の話にもまず耳を傾けるという気風はあるように思います。多様な価値観を受け入れてきた小江戸ならではの性質があるように思いますね」
ところで、旧市街の上の世代は川越の変化をどのように捉えているのだろうか? 秋山さんはこう話す。
「川越独特の気風でもあると思うんですけど、若者たちに任せるのが早い感じがしますね。地方の商店街って60代が若手で、70、80代が現役っていうところが少なくないんです。でも、一番街商店街の理事長さんはまだ40代ですし、女性陣もいて活気があるんですよ」
川越独特の気風――それはもともと外部の人間として川越のまちづくりに関わるようになった秋山さんだからこそ見えてくる部分でもあるだろう。秋山さんはこう続ける。
「『まちづくりは人づくり』ということがよく言われますけど、熱意のある人たちがいて初めて街がいい方向に進んでいくと思うんですよ。いろんな考えがあると思うんですけど、『川越のこのエリアが好き』という思いはみなさん同じなんじゃないかと」
最後に都市計画コンサルタントの視点から見た川越の魅力を秋山さんに語っていただいた。

「伝建地区(伝統的建造物群保存地区)って立ち上げた当初は地元の人たちが頑張っていても、数年経つと行政任せになってしまうことが多いんですよ。でも、川越は地元主導でまちづくりをやってきて、それぞれの営みがあったうえで街が成り立っている。行政主導じゃないぶん、建物もひとつひとつ違うし、個々の魅力があるんですよ。おもしろい街だと思います」
川越は今、誇りと愛着を持てる街になっているようだ。長い時間を川越で過ごしながら、何ひとつ愛着を持てずにこの街を去ってしまった僕もまた、秋山さんやチエさんと会話を重ねるなかで少しずつ川越に対する意識を変えようとしていた。
川越は今、誇りと愛着を持てる街になっているようだ。長い時間を川越で過ごしながら、何ひとつ愛着を持てずにこの街を去ってしまった僕もまた、秋山さんやチエさんと会話を重ねるなかで少しずつ川越に対する意識を変えようとしていた。

小春友樹/江戸和竿師
1973年、東京生まれ。幼年期より埼玉県川越市在住。服飾メーカー営業職を経て、竿職人の道を目指す。川越市に工房を構える東作系江戸和竿師「寿代作」工房の門を叩き、1年間師事。その後、同市内の「俊秀作」の元へ2年間師事した後、独立。2020年より江戸和竿組合に加入。
-

FORESTER
Shigeaki Adachi
-

EDO-WAZAO CRAFTSMAN
Tomoki Koharu
-

LANDSCAPE ARCHITECT DESIGNER
Kei Amano
-

BAMBOO CRAFTSMAN
Daisuke Soutome
-

CRAFTSMAN, BUILDER, PLASTERER
Taiki Minakuchi
-

SOUL BEAT ASIA Hitsuke Nugumi
橋の下世界音楽祭 火付ぬ組
-

SNOWBOARD BUILDER & WOOD WORKER
Naoyuki Watanabe
-

NATURAL DYEING CRAFTSMAN
Yukihito Kanai
-

SAUNA BUILDER
nodaklaxonbebe